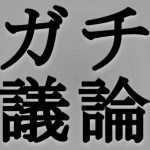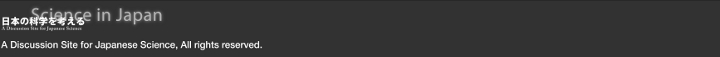トピックス
ガチ議論企画2015、始動!
2015.03.10 トピックス

ヘンに厳しい競争、不安定な研究費とポジション、研究への集中を妨げるムダな諸手続き、etc。研究者のみなさん、こういった問題に悩まされたことはないでしょうか?そして、もしあれがこうだったら、これがああだったら、もっと研究に没頭できて面白い成果を挙げることができるに違いないのに、などと思ったことはないでしょうか?学会に来て、旧知の仲間と酒を飲むと、こういった話題になることがきっとあるでしょう。しかし、単なる愚痴で終わらせてしまうなら、ストレス解消にこそなりますが、生産性はありません。ガチ議論企画では、そういった研究者のみなさんの不満や苦悩から生まれる「より良い仕組みの構築」についてのアイデアや提案をこのサイトに掲載し、徹底的に議論します。そして、議論で揉んだ提案を、実際の施策にむすびつけ、より良い研究環境の構築を実現するための活動を行います。 こういった発想とモチベーションのもと、2013年の分子生物学会年会で、第一回のガチ議論企画を開催しました。会場参加者400名とネット中継の視聴者2,800名の前で、サイトに集まった提案について、現役研究者と科学政策にかかわる人々が直接対話を行い、3時間以上にわたって熱い議論が繰り広げられました。 その後、総合科学技術会議有識者会議の意見交換会でのプレゼンをはじめ、サイエンストークスの「勝手に『第5期科学技術基本計画』みんなで作っちゃいました!」企画との連携とその提案書の総合科学技術・イノベーション会議での発表、などの形で、ガチ議論企画での提案を実際に実現する努力をしてきました。 こうした我々の熱意が文科省に届き…と思いたいのですが…、先日、文科省に新たに対話型政策形成室という部門が設置されたようです。これは、双方向のコミュニケーションを通じて文科省が吸い上げた現場(の研究者)の意見を、今後の日本の(科学)政策のデザインに反映していくためのセクションのように思われます。まさに、我々の声を実際の施策に結びつける、そのお膳立てが整ったと言えるかと思います。 そこで、今年もやります、ガチ議論企画! 今年は、前回の経験も踏まえ、1)研究者間で絞り込んだテーマを行政サイドと本番前からじっくり議論し、2) さらに厳選した1、2件の提案について、それを実際に施策化に結びつけることを目指します。これには、この種の活動の継続や普及のための基盤となるような成功例・モデルケースを提示するという意味合いもあります。この第二回の企画は、次のような段取りで進めていこうという話になっています(下図参照; 前回企画と同様に、サイエンストークスにもご協力をいただく予定です)。 ガチ議論本番にさきがけて、まず「プレ企画」を実施します。この「プレ企画」では、 [i] まず、研究者の皆さんから募ったご意見(トピック)をガチ議論サイト上で議論を行います。 [ii] これをガチ議論委員が取りまとめ、前述の文科省・対話型政策形成室を窓口として科学政策決定に関わる方々と直接議論します。 [iii] そして、この議論内容について、実現へむけてポイントを整理し、ガチ議論サイト上において再度、議論を行います。 以上を1サイクルとし、これを本番までに3、4回(件)程度行う予定です。 12月のガチ議論本番では、プレ企画で検討されたテーマを中心に、現役研究者と科学政策にかかわる人で徹底討論を行います。今回もパワフルなパネリストにご登壇いただく予定です。本番での議論に基づき、施策化を見据えた具体的なアイデアを1、2件、取りまとめ、これについて提案を行っていきます。 ガチ議論企画2015でどんな提案を取り上げていくかは、現時点ではもちろん、まったくの白紙です。ということで、再び、みなさんから広くご意見を募集します! これまでの提案・議論もご参照いただいた上で、日本の科学研究について、現状への批判だけでなく、望ましい仕組みや理想的なあり方についての前向きで具体的な提案を中心にしたご意見(詳細はご意見募集の要項をご参照ください)と、そのご意見に対する活発な議論をお願いします。 また、私たちと一緒にこの企画を創りあげていく、委員(スタッフ)メンバーを募集します。日本の科学の仕組みをより良いものにしようという意気込みをお持ちの方は奮って下記までご連絡を! admin[at]scienceinjapan.org *[at]と@と変えてください *件名は「ガチ議論スタッフ募集」としてください ガチ議論2015委員会一同
続きを読む
2015年3月10日
ガチ議論サイトについての説明とコメントの投稿規定(暫定)
2015.01.19 トピックス

ガチ議論サイトについての説明(暫定) 1:「日本の科学を考える(ガチ議論)」は、生命科学研究環境に対する諸問題を、研究者だけでなく政策サイドの人も巻き込んで議論することを目指し、2013年1月に立ち上げたフォーラムです。現在、4名のスタッフ、近藤滋(阪大生命機能)、宮川剛(藤田保健衛生大)、中川真一(理研)、小清水久嗣(藤田保健衛生大)で運営しています。 2:分子生物学会の2013年の年会で近藤が年会長を務めたことから、年会の一企画として、文科省、総合科学技術会議、政治家等を集めて、「第1回ガチ議論」と題したイベントが行われました。詳細は、このサイト内の記事をご覧ください。 ・企画の詳細 http://scienceinjapan.org/topics/20131125.html ・参加パネリストの紹介 http://scienceinjapan.org/topics/20131122.html ・議論のテープ起こし http://scienceinjapan.org/topics/032414-1.html 3:2014年度以降、現在は分子生物学会との直接の関係はありません(現在、近藤は理事ではなく一般会員です)。ガチ議論イベントは、どこかの学会に固定して行うのでなく、いろいろな場を移動しながら続けるのが理想と考えています。 コメント投稿に関する(暫定)ルール 生命科学研究の現状を改善するための、建設的な議論が行われることを希望しています。また、主な批判の対象となる政策サイドの関係者にも、読んでもらわなければ意味がありません。書き込みの内容は厳しくても構いませんが、表現には節度と他の投稿者への配慮を持っていただければと思います。匿名での投稿も可能ですができるだけ実名でお願いします。実名が困難である場合も、投稿者の同一性は保たれる形にしてください(ニックネームは他の投稿者とは異なるものを用いて同一性がわかるようにしてください)。また、以下に当てはまるコメントは削除させていただくことがありますので、ご了承ください。 1:具体的な研究不正の告発(関係機関に直接行ってください) 2:他の投稿者を非難する以外の内容を含まない投稿 3:建設的な意見を含まない一人語り 追記(1/27) なお、トピックスに記事をご投稿いただく際は、こちらの投稿規定をご一読ください。お名前・ご所属・肩書(匿名も可能ですが、その場合はニックネームやペンネームなどで議論参加時のユーザーネームと同一であるもの)が必須となっております。また、原稿の修正・確認などを行う場合がありますので、匿名の方も連絡のつくメールアドレスを用いてください。
続きを読む
2015年1月19日
研究者の議論をどう活かすか
2014.07.18 トピックス

研究不正について当事者である研究者が議論することには一定の意義があることは間違いありませんが、一方でこれは研究者の間でコンセンサスが取れれば自ずと解決するという性質の問題ではないことは明らかです。特に再現性の検証が難しく、学説が定着するまでに時間のかかる生命科学領域では、一種のモラルハザードが起きやすいという弱点があり、この点を直視した制度設計が必要です。米国でNIHが研究の再現性検証のために取り組みを始めていることは、再現性のない生命科学研究が国際的な問題でもあることを示しています。研究者が健全に振る舞うためには、それを促すような制度設計と、科学研究の発展を損なう行為に対してこれを適切に排除していく仕組みが必要です。 以前、文科省の官僚の方に受けた助言として、その問題は誰が解決するべきなのか、レイヤーを明瞭にするべきという指摘がありました。研究者の多くは科学技術政策決定のプロセスに関心が低いため、自らの負担が増えるような施策が出る度に文科省を悪者にしがちですが、そういう認識を改めて大きな視野で物事を考えるべきと言うことです。研究者ができること、研究機関ができること、文科省ができること、さらに上の意思決定が必要なことといった仕分けをして考えることが大事ということです。そして可能ならばどのレイヤーの構成員も自らが出来ることはすすんでやるべきです。 これまで研究者側では何ができるのかについては様々な議論があり、その中には非常に優れたアイデアもあったように思います。ただ、現状では研究者側ができることは限られていて、こうしたアイデアの中から研究者の多くが納得できそうなものを選択して提案するところまでだと思います。しかもそれらはとりあえず公表して、科学技術政策に関わる人の目にとまるのを待つという、神への祈りのような状況です。また、研究者にはいろいろな背景の方がいらっしゃるので、議論がまとまるということはなく、積極的に議論する研究者たちもいずれは疲れ果ててしまうかもしれません。これはあまりに辛い状況ですので、ここではこれまでの議論とは別の軸で意見を述べたいと思います。 ・研究不正に対する対策 研究公正局的な組織の設置についてはここでも議論があり、具体的なアイデアもでています。組織の有無という論点にしぼれば、必要と考える研究者が多数派かも知れません。一方で、現在のように公正局がなくてもガバナンスを発揮できるはずという見方もあり、これもある程度は正しいように思います。理化学研究所のガバナンス担当理事や、東北大学の井上総長の事件の際の副学長はいずれも文科省出身者であり、彼らが本来の職分を果たせば混乱はもう少し小さかったかもしれません。彼らは退職者ではありますが、研究機関と文科省をつなぐ存在として価値があるというのは容易に想像できることです。様々な議論はありますが、研究不正は国家にとってマイナスという真摯な意識を文科省出身者が持つことは非常に大事だと思います。外形的な事実からは、文科省が研究不正を重要な問題と認識しているようには見えないので、この点は改善していただきたいです。個人的には公正局は必要という意見ですが、米国のORIで問題となっているように運営する人間の姿勢が正しくなければうまく機能しないと思います。 ・人材育成のあり方について 人材育成については様々な意見や試みがありますが、研究人材に絞って考えれば、プレゼンテーションや人付き合いが上手であることより、むしろ一つ一つのブロックを確実に積み上げるような誠実さが重要であることは明らかです。斬新な研究を実施するためには自由な発想も欠かせませんが、それは荒唐無稽な妄想とは区別されるべきものです。早稲田大学先進理工学部の一部における学位認定には明らかな問題があり、それは大学院教育そのものが適切に行われていないことを示唆しています。大学院修了者が今後被ることが予想される不利益を考慮すれば、当該研究室における大学院進学は直ちに停止されてしかるべきですが、放置されているのではないでしょうか。次の項目とも関連しますが、科学の訓練を受けた人材の価値を文科省自身が軽視していることが様々な問題の根底にあるように思います。他の官庁ならばいざ知らず、文科省は博士人材の有用性を社会に訴えるべき立場だと思いますし、有用でないと考えているのであれば、他の先進国と同程度に博士人材の価値が認められるような大学院となるよう改革を進めるべきです。 ・科学の専門性に対する姿勢 理化学研究所の迷走ぶりは、スポーツの審判の判定に対して観客の異議を取り上げることによる混乱に似ています。あるいは、これまでの研究不正に関する裁判では、科学的な判断を司法に委ねてしまうという失敗が何度も繰り返されてきました。今回の早稲田大学の調査委員会の結論はとても科学者の議論に堪えるような内容とは言えませんが、科学の専門性を科学の外に委ねてしまうとここまで恐ろしいことが起こることを示していると思います。こうした判断が公的に承認されるようであれば、早稲田大学のみならず日本の博士の学位の価値は地に落ちることでしょう。 研究不正問題では明らかに科学者による判断が必要な範囲が存在し、その点は全体の評価とは切り離されなければいけません。一方、最終的な判断は社会的なものであり、研究者の感覚とは相容れないこともあるでしょう。文科省は、科学の訓練を受けた人材をこれまで以上に受け入れることを通じて、科学と社会の間の境界をふまえた判断を自らできるような官庁を目指すべきだと思います。「科学的にナンセンスなので再実験は必要ありません」あるいは「科学的にはナンセンスですが、社会的な判断として再実験を必要と考えます」ということが、官庁から明言できることが大事です。現在のように何の説明もないまま物事が進行し、文科省はこう考えているのだろうと忖度されるような状況は、責任を問われないという意味では好都合かも知れませんが、海外や多くの科学者との信頼関係を毀損するものです。また、政治家と研究者の間のレイヤーとしても文科省には重要な役割があるはずですが、今のところそうした機能は発揮されているとは言えません(むしろノーベル賞受賞者であっても科学の倫理を曲げざるを得ない状況です)。こうした構図は特異であり、国際的に説明可能な状態ではありません。 少しでも研究者間の議論に実効性を持たせたければ、科学技術政策に身を捧げる研究者を送り込むしかないと思われます。研究活動も、科学技術政策も、いずれも片手間でできるようなことではないでしょう。現在のところ、代表とする組織を持たず(該当しそうな組織は全くの沈黙状態です)、延々と議論を続けるしかない研究者は、相当不利な立場です。他のレイヤーのプレイヤーにも責任をもった発言や行動を求めなければ、解決を目指すことは難しいのではないでしょうか。 Satoshi Tanaka
続きを読む
2014年7月18日
STAP問題を受けて②:CDB解体を考える
2014.06.21 トピックス

理研の「研究不正再発防止のための改革委員会」(以下、改革委)は「研究不正再発防止のための提言書」をまとめたが、これにより真の研究不正防止が果たされるのであろうか。 本コメントでは、改革委の提言の問題点と、日本の科学界全体への影響を検討したい。 尚、本コメントには充分な裏付け調査がなされていない点が含まれていると思われる。誤りはすべて率直にご指摘いただければと願う。 1.STAP問題発生の直接的原因、個人に帰する問題の解明 改革委は、STAP問題発生の原因分析の問いとして、「問題は、研究不正行為の発生が、誘惑に負けた一人が引き起こした、偶然の不幸な出来事にすぎないのか、それとも、研究不正行為を誘発する、あるいは研究不正行為を抑止できない、組織の構造的な欠陥が背景にあったのか」を設定し、組織の構造的な欠陥が背景にあったと結論づけた。個人の問題か組織の問題かを天秤にかけ、組織の責任が重いとする判断である。 しかしながら、この両者を比較考量するには、今回改革委が分析した組織の問題と同様に、個人の問題についてもさらなる分析が必要と思われる。 改革委は小保方氏の研究データの記録・管理のずさんさとそれを許容したCDB(理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター)の問題点を指摘し、実験データの記録・管理を実行する具体的なシステムの構築・普及、CDB解体を含む理研によるガバナンス強化等をもって研究不正の再発を防止することを提言している。これは、STAP問題における個人的要因が、データ管理の問題であり、つまりは小保方氏のデータ取り違えは単純ミスであるとする主張にある程度沿ったものであるとも言える。しかしながら、細胞の由来が違うといった複数の疑義は、生データや実験記録の管理システムの構築やガバナンスの強化で防げる問題なのであろうか。論文のデータ作成・編集が人の手を経て行われる以上、その人がある意図をもってデータを入れ替える、加工する、あるいは細胞そのものを入れ替える可能性はデータ管理システムの構築をもって防げるものとは思えない。 STAP論文に対して、信じられるデータはひとつもないのではないかと言われるまでに至っている。研究データの記録・管理の徹底は疑義が生じた際の検証を容易にさせるであろうし、ねつ造や改ざんへの抑止力とはなり得るであろう。しかし、STAP問題における直接的問題、つまりは小保方氏によって何がなされたのかが明らかにならない限りにおいては、個人の問題と組織の問題を天秤にかけることはできないのではないか。 2.CDB解体への疑問 CDBの自己点検報告書では、CDBの採用システムによる若手PIの抜擢・育成、を一定評価した上で、ガバナンスや人事制度の改善策等を提案している。一方で、改革委の改革案では、硬直化したガバナンスの問題を理由にCDBそのものを解体し、「理研が最も必要とする分野を構築すべき」としている。その理由のひとつとして、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の設立をあげ、発生・再生科学分野の状況の変化を説明している。極端な見方をすれば、iPS細胞の開発でもって、発生・再生科学分野の終焉を告げているともとれる内容である。 理研の中期目標ではCDBについて「発生生物学は、生命の基本原理を明らかにすることを目的とした基礎科学的側面と、その成果が再生医療等の先進医療の進展や、疾患メカニズムの特定等に直結するという応用的側面を併せ持つ学問分野であり、社会からも大きな期待が寄せられている」とし、CDB HPでも同様のミッションの説明がなされている。 小保方氏のPI登用や、疑義発覚後の対応の遅れ、情報開示の不適切さは、改革委やCDB報告書が指摘したCDBのガバナンスの硬直化、つまりは相互批判による経営判断がなされなかった結果であることを示している。客観的な見解が取り入れられない、あるいは強い主張が押し通されるような歪んだ経営を生んでいる可能性もある。ガバナンスの問題は明らかであり、それはこれまで定期的に経営体制を見直さなかったことに大きな原因がある。提言を受けた組織体制の見直しは不可欠であり、速やかに実行に移されるべきである。 しかしながら、CDBそのものの解体を求めるのであれば、STAP問題とミッションの直接的因果関係が示され、ミッションそのものにSTAP問題を引き起こす原因があり、ミッション設定そのものに誤りがあるとの説明がなされた上でなければならないはずである。しかし、提言書ではSTAP問題とCDBのミッションとの因果関係はもとより、発生・再生科学分野の果たしている役割の検討や、CDBのこれまでの業績の検討はなされず、CDBのミッション再定義を求める合理的な説明は、iPS細胞研究所の設置のみでしか示されていない。このように合理的な説明がなされないまま解体を求めるのであれば、「見せしめ」との批判は免れない。 尚、CDBではここ数年、センター長交代に向けた議論が進められており、具体的な候補について理事会に打診するものの承認されないということが複数回あり、理事長もしくは理事会の依頼によりセンター長留任を竹市氏が引き受けたと聞く。「理研が最も必要とする分野を構築すべきである」とする改革委の提言にこれまでの理事会の意図が反映されているのではないか、これまでのセンター長候補打診を理事会が拒否した理由とともに、気になるところである。また、改革委が理研理事長により設置されたものであることも、忘れてはならない。 3.基礎科学への理解と自由な研究環境の必要性 改革委は、「仮に理研がCDB解体後に、新たに発生・再生科学分野を含む新組織を立ち上げる場合は、(中略)、真に国益に合致する組織とすべきである」とした。この“国益”と表現されるとき、それは直接的な応用に結びつくイノベーション、つまりは産業界に利益をもたらすものであることが政策の立案過程や予算編成でも示されている。 しかしながら、生物学のこれまでの偉大な発見において、研究者の知的好奇心を動機としてなされた研究が、予想外の応用に結びついた例は少なくないのではないか。GFPの研究によりノーベル化学賞を受賞した生物学者である下村氏は、応用には興味がなかったと聞く。現在の政府による公的研究費(競争的資金)はそのほとんどが応用を直接的なテーマとしている。基礎研究が軽視されがちな我が国において、CDBは応用への基礎的な知見を提供することをその任務として認められた貴重な存在であったが、一方で短期的な応用の成果を求められすぎた側面も推測される。運営費交付金は、センター設立時から半減しており、予算面での締め付けは大きい。改革委の提言書にて「STAP研究は、そのインパクトの大きさから、新しいプロジェクト予算、それも巨額な予算の獲得につながる研究と期待された可能性があり、笹井GD自身も当然、そのような期待の下に行動した、と推測される」としたが、例え予算要求担当GDである笹井氏がそのような考えによって行動していたとして、その背景にある、基礎科学の軽視と応用の偏重、応用分野における短期的な成果の過剰な期待という、日本の科学分野をとりまく根源的な問題が笹井氏の行動の背景にあったのではないかと検討されなかったことは残念である。 生物学の知見の多くは、応用を前提に得られているものではない。自由な発想の下進められた研究に応用への可能性が内在しているのである。生命の基本原理を明らかにするというCDBの基礎科学の側面を軽視して応用を偏重するのであれば、我が国における生命科学研究の根幹にダメージを与える事態になりかねない。 4.細胞の初期化メカニズム、もしくは分化細胞における多能性細胞内包の可能性への期待 改革委の提言書では、「iPS細胞研究を凌駕する画期的な成果を獲得したいとの強い動機に導かれて小保方氏を採用した可能性が極めて高い」としたが、この説明は、STAP細胞の報道発表において強調されたiPS細胞との比較と小保方氏採用時におけるCDBの推薦理由を根拠にしているものと思われる。しかし、報道発表資料が笹井氏の独断で作成・配布されたことは確認されており、iPS細胞との比較をCDBが組織的に行った根拠とはならない。小保方氏採用時における推薦理由「iPSの技術が遺伝子導入によるゲノムの改変を伴うことから癌化などのリスクを排除できないことをあげ、ヒトの体細胞を用いて、卵子の提供やゲノムの改変を伴わない新規の手法の開発が急務である」としたものは、iPS細胞研究を凌駕する画期的な成果を獲得したいという思惑というよりも、iPS細胞研究があれば多能性細胞の研究は充分とされがちな見方に警鐘を鳴らすものであり、ゲノム改変によらない体細胞の多能性獲得の可能性が否定できない学問の積み重ねを背景にしているものと思われる。 iPS細胞の開発が大きな驚きとともに受け止められたことと同様に、STAP細胞研究も大きな驚きを研究者にもたらした。それは、細胞の初期化メカニズム、もしくは分化細胞と多能性の関係にもまだまだ解明されていないことがあり、STAP現象で説明される事柄があると多くの研究者が思ったからではないか。 STAP細胞がNature誌掲載によって一度はアカデミィアに受け入れられた。これは、細胞の初期化メカニズムはiPS細胞でもってしても未だ解明されてはいないことの裏返しでもあり、発生・再生科学分野において探求されなくてはならない生命の基本原理がまだまだあることを示している。 CDBの解体を求める改革委の提言書は、発生・再生科学分野のみならず、多くの研究者にとって衝撃をもって受け止められたのではないだろうか。 理研は、日本で唯一の自然科学の総合研究所である。科学の研究は、個々の研究者の自由な発想から生み出されるものであり、それなくしては、偉大な研究成果は生まれない。これまで理研は、個人の研究を支えるための各研究センター、各研究センターを支えるための和光本部というボトムアップの組織として研究者を受け入れて来た。トップダウン型の組織への改組や経営層における過度の管理は、個人による自由な研究活動を阻害する組織へと理研を変貌させる危険を孕んでいる。 また、CDB解体は、これまでの基礎科学軽視の傾向を決定的にするものである。度々聞かれるSTAP細胞があったらいいのではないかという見解は、生命科学研究の発展を阻害するものでしかない。STAP問題をCDB解体で終わらせることなく、我が国における生命科学研究の発展という視点にたった真摯な議論を期待したい。 匿名M
続きを読む
2014年6月21日
STAP問題を受けて①:研究者コミュニティの課題
2014.06.21 トピックス

STAP問題は、理研の問題に留まらず、日本の科学研究そのものへの信頼を失わせかねない状況を生んでいる。理研内での適切な対応を求めることは当然であるが、これを教訓として、日本の研究者コミュニティにおける課題を改めて検討し、具体的な提言がなされないものだろうか。 我が国における研究不正防止・対応策、つまりはどのようにすればこのような研究不正が防げるのか、また研究不正発覚後はどのような対応をとることが適切なのかについて、改めてご議論いただきたい。 尚、本コメントには充分な裏付け調査がなされていない点が多々含まれているものと思われる。できるだけ早く議論を開始していただきたいからであることをご理解いただき、誤りはすべて率直にご指摘いただければと願う。 1.疑義に対する責任著者自身による説明機会の保障 研究論文は責任著者を設定して発表される。それは論文に対する説明責任を宣言するものであり、今回のNature論文2報ともにおいて責任著者を宣言したのは小保方氏であるにも関わらず、疑義が呈されて以降、小保方氏本人によって社会に対して説明責任が果たされたのは、記者会見による一度であり、弁護士が小保方氏の体調への配慮を強調し、質問件数を限定させるという踏み込んだ説明が求められない状況においてのみであった。 小保方氏は悪意のない単純ミスや不勉強を強調したが、若山氏や遠藤氏による解析結果や人事選考の際に提出した研究計画書における不適切な画像掲載の疑義など、ミスでは説明がつかない事柄があまりに多く、小保方氏しか知り得ない真実が語られないことには、STAP問題の真相は明らかにされない。 また、本来、論文への問い合わせに対しては責任著者が応じなければならないにも関わらず組織が代わりに応じるがために、真実の説明が遅れ、社会や研究者コミュニティの苛立ちや不信感を募らせている。某大学において今なお調査中とされる研究不正案件についても、責任著者による直接の説明が調査を除くいかなる場においてもなされておらず、こちらも真相が判然としない。今回のSTAP問題では特に、小保方氏個人とSTAP細胞の有無への社会の関心が非常に高かったが、理研が調査を理由に本人に説明させず、また理研広報や幹部が組織として回答することで、本来責任著者に帰する責任が組織の責任となったことが、問題を複雑にし、所属機関全体への信頼を失わせる結果を生んでいる。 通常、研究は個人あるいは研究室単位でなされる。そしてその個人や研究室の責任によって成果が論文にまとめられてジャーナル投稿がなされ、レフェリーの審判を経て発表の日を迎える。この個人単位の活動が研究を支える基本である原則を崩しては、自由な研究環境は維持できない。 研究者が所属する組織においても、各研究者においても、個人の責任のさらなる自覚が求められる。発表論文への疑義に対しては、責任著者の責任で説明がなされるべきであり、組織はそれを阻害してはならないばかりかその機会を積極的に提供しなくてはならないことを認識すべきである。また、研究者コミュニティは、社会や海外から関心の高い疑義等が発生した場合、自ら研究者による説明の場、討論の場を設定するなど、研究者コミュニティとして解決へのアクションをとることを検討されたい。 STAP問題は、当初の論文投稿のお作法における問題との見方から、成果そのもののねつ造疑惑に発展している。研究内容に踏み込んだ説明がなされるときに、報道関係者のみが出席する記者会見では不充分である。分野の専門家の同席を求める、あるいは研究者による公開質問への対応を要請するなど、責任著者による説明機会の保障とその質の向上が求められる。 2.研究活動の不正行為への対応のガイドラインの見直し 文部科学省は「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」を公表し、文部科学省、独立行政法人科学技術振興機構及び独立行政法人日本学術振興会を資金配分機関とする競争的資金における研究不正の対応について示している。同じ国費でも、基盤的経費は「機関を対象に措置されるものであり、その管理は大学・研究機関に委ねられている」として、ガイドラインの対象としていない。 STAP論文は競争的資金を含む経費を用いてなされた研究成果であり、研究不正は本ガイドラインに沿って、研究者の所属機関である理研が調査を行ったものと考えられるが、結果、理研が設置した調査委員会が中立性を保てるのかといった批判、あるいは改革委による「理研のトップ層において、研究不正行為の背景及びその原因の詳細な解明に及び腰ではないか」との指摘を受けるに至った。隠蔽行為の可能性や政治的な思惑から早い幕引きを計ろうとしているといった疑惑が常に組織に対して向けられた結果でもある。 これらのことが示すのは、研究者が所属する研究機関による調査の限界である。例え自らを律して誠実な対応をしていたとしても、その研究機関が当事者を雇用している組織であり、政治による影響を受けるものであり、特許等の権利が絡んでもくることなどから憶測を呼び、中立性に疑いの目が向けられる。 CDBによる再現性実験についても、改革委はプロトコルの見直しを提言している。これを受け実験を組み直すのであれば、4月から既に3ヶ月かけて進められた時間や経費が無駄になる可能性がある。当初から、第三者機関によって調査が主導されているのであれば、こういった事態は避けられたのではないだろうか。 STAP問題は、一研究者の問題、一組織に問題に留まらず、日本の科学研究そのものへの信頼を失わせかねない状況を生んでいる。特に社会的に関心の高い研究においては、科学そのものへの信頼を失わないよう、中立的な立場による調査・説明は不可欠のものとなるが、現時点の文科省のガイドラインは所属機関が主導して調査をすることを求めており、ガイドラインに即した調査委員会の設置そのものが、中立性を担保できないものとなっている。 こういった事態に対応するためには、政府にて調査機関を設置する以外、方策はない。中立性の担保に加え、調査・検証のやり直しといった事態を回避し、迅速な調査・検証結果の提示を可能とする。さらには、研究者の所属機関であれば調査・検証にかかる経費や謝礼金を用意すれば利益相反状態が発生するが、政府による調査機関であれば、そういった問題も解決できる。そして政府による調査対象は競争的資金に限るものではなく、社会の信頼が学術研究を支えるとの視点から、基盤的経費を含めた範囲での検討がなされるべきである。 3.大学院教育の見直し これまで明らかになった小保方氏の研究不正では、研究者としての基礎教育がなされてこなかった、あるいは、教育されていても身に付いてこなかったことを示している。ポスドク一万人計画や大学院重点化の政策は、それまで研究室の伝統のなかで受け継がれ守られて来た研究の作法、規範、研究者のあるべき姿の伝承を難しくしてきているのではないか。大学教員が研究に専念できる時間は減少してきており、共に研究を進めながら研究者を育成する条件を維持することも難しくなっている可能性もある。研究室での教育は重要であり、当然PIの責務であり続けるものであるが、基礎的な知識の習得と規範意識の醸成を企図したカリキュラムを全国の大学院生に課すことが必要な時代になってきているのではないか。実験ノートのとり方やデータ保管方法、論文投稿のお作法、研究者の倫理規範からプロフェッショナリズムまで、大学院正規課程で一律に基礎レベルをあげることで、研究室における教育を効率的にすることも可能とするであろう。また、研究不正の告発は近年SNS等を通じてなされることが増えてはいるものの、論文発表前にチェック機能を持たせようとするのであれば、大学院生等に不正を知ったときにどのような対応をとる必要があるのかについて、周知徹底を計ることも重要である。 4.研究者コミュニティでの相互監視のあり方 小保方氏によって真相が語られない現時点において予断すべきでないが、数々の疑惑は、これまでの性善説を前提とした研究者コミュニティのあり方そのものを問うものである。不正を許さない強い姿勢、批判精神に基づくディスカッションの重視、不正の告発窓口の設置といったこれまでの相互監視のあり方は充分なのであろうか。 例えば不正の告発については、これまでは発表論文における研究不正が告発の対象となってきた。しかし、今回のSTAP問題は論文発表後の不正発覚が科学界や社会に対していかに大きな影響を与えるかを示している。研究者コミュニティにて、論文発表前であっても不審な研究活動に対して何らかの措置がとれないか、制度を検討できないものであろうか。これまでの不正においても、「あそこの研究室は怪しい」といったことが周辺では囁かれているものの見過ごされ、大きな事態に至ったケースがあったと聞く。研究不正を火種の段階で発見する仕組みの設計が、急務である。 5.守秘義務を課した議論の場の構築 研究成果は、多くの場合、①個々の研究室内での討議、②大きな研究所では研究所内での討議、③学会等での討議、④論文投稿時のレフェリーとの討議、といった研究者コミュニティでの議論を経て公開のものとなり、広く社会に発表される。ところが、特許申請の妨げにならない守秘義務が徹底された議論の場は限られている。学会発表の内容がリークされてジャーナルのEmbargo policyを守ったメディアから抗議されるようなケースもあったと聞く。国際ミーティングでも、守秘義務を徹底しているものはまれである。個々の研究者においても、“守秘義務”といった言葉を使うことを躊躇う人もいるのではないだろうか。オープンな議論は必要ではあるものの、それと守秘義務は相反するものではない。特許等が絡んでいるとしても、研究者間で活発な議論がなされるような場の設計と構築が望まれる。 6.研究成果の社会への発信方法 STAP問題では、報道機関を通じた社会への発信方法・内容についても、検討すべき課題があることを示した。STAPの報道発表のような、根拠に乏しい説明資料の作成や研究内容に関係しない演出、成果の誇張があってはならないことは言うまでもない。しかし、疑義発覚後に生じた社会と理研との乖離は、社会が求める情報ははっきりした結論であるのに対し、アカデミィアは複数の仮説をめぐって議論を繰り返す世界であることを見せきれなかったことに大きな要因があるのではないか。紙面の字数や放送時間に制限があるマスコミは、短い言葉で結論が語られることを望む傾向がある。それに対して、研究者がいかなる言葉を持ちうるのか、難しい課題である。同時に、アカデミィアへの理解を求める活動は、ますます重要となるであろう。 目下、政府は国際共同論文数を増やすべく次々と予算をつけており、国内のみならず海外からも研究者を受け入れるケースは一層増えることが予測される。研究者をとりまく環境は時代とともに変化している。そのなかで、今回のような事態を二度と起こさないという意思と、具体的な提言の表明が研究者コミュニティからなされることを期待する。 匿名M
続きを読む
2014年6月21日
「ガチ議論」をふりかえって
2014.04.30 トピックス
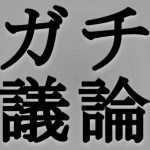
ガチ議論」企画を終えてのスタッフの感想をご紹介します。 . ガチ議論代表の近藤です。分生のガチ議論ライブからずいぶん時間が経ってしまいましたが、編集作業を終え、やっと当日の議論を公開することができ、大変うれしく思っています。この企画を思いついた当初は、お偉いさん方への“つて”はほぼ皆無であり、「ほんまにできるんかいな?」と自分でも全く先が読めなかったのですが、素晴らしい協力者にも恵まれ、終わってみれば期待以上のイベントになりました。当日のtwitterでの反応や、後日行った分子生物学会員へのアンケート結果も非常に好評で、多くの人が、このガチ議論を続けて欲しいと望んでいます。企画者としてはうれしい限りなのですが、では、我々がこの企画を分生の企画として続けると言うのは、ちょっと違うと感じます。科学者と政治、国民との問題は、生命科学分野に限るわけでは無く、また、一部の人だけが先鋭的になって引っ張っていくものでもありません。今回、我々が示すことができたのは、ガチ議論のように、政治の中枢にいる人たちと一般研究者との対話が、実は意外と簡単に実現する、という事です。我々と同じ問題意識をお持ちの方、是非ご連絡ください。企画に関するノウハウは喜んで全て提供させていただきます。理想的には、同様の企画が色々なところで自発的に立ちあがり、科学者コミュニティの意見の形成につながって欲しいと考えます。 近藤 滋(大阪大学大学院 教授, 年会大会長, ガチ議論代表) . ガチ議論企画が行われてから、あっという間に半年近くがたちました。 学会や会合などで出張すると 「ガチ議論、見ましたよ!」 とおっしゃっていただくことが頻繁にあり、この種のことに興味を持っている方々がたくさんいらっしゃるのは間違いないことを実感しました。 多くの方々が、「こう変わったほうがいいのに」と思うことがたくさん一方で、それらがほとんど変わることがないというのは、たいへん不思議なことではあります。しかし、意見を言うことが研究費獲得や人事などでマイナスに作用する可能性がある(と多くの研究者が思っている)現在の研究者コミュニティでは、これは驚くことではないのかもしれません。ネット上だけでもいいし、匿名でもいいです。一言だけのコメントでももちろんかまいません。勇気をだして自分の意見を公の場に出してみるのはどうでしょうか。「ガチ議論というのはちょっと」ということであれば、「プチ議論」ぐらいでも十分効果はあると思います。 また、この種の企画を分子生物学会だけでなく、様々な学会、グループでもぜひこの種の分野横断的なトピックについて議論をやっていただけるとうれしいです。ノウハウのようなものは提供できますし、なんからの協力もさせていただきます。 ネットでの一言や小さなグループでの議論が少しずつ積み重なって、ある種の共鳴のうねりのようなものがもしできれば、いろいろなことが良い方向に変わっていくのは間違いないと思います。 宮川 剛(藤田保健衛生大学 教授) . 分子生物学会年会でのガチ議論のまとめ作業をしていた2月中旬、例のSTAP論文の不自然な画像の重複の指摘がTwitter上で拡散しはじめました。それから2ヶ月近く経ち、うっかりミスでは到底済ます事の出来ない、様々な瑕疵があったことが明らかになりつつあります。大きな事故というのは、小さなミスが幾十にも重なって起きるというのは良く言われる事です。また、その小さなミスのどれか一つでも防げていれば、大きな事故にはつながらないというのもまた良く知られている事です。大学院教育の問題、ポスドク問題、研究費の分配の問題、業績の評価の問題、などなど。今回の事例では、単年度予算問題以外の、ガチ議論サイトで議論された科学技術にまつわる緒問題のほとんど全てが背景にあったような気がします。どのような研究者コミュニティーを目指してゆくのか。どうすればそれを実現できるのか。研究者の多くにとって、そういう話題は縁遠いものですし、できれば縁遠いままでいたいというのが正直なところです。しかしそれではいけない時代にさしかかっているということも、確かなような気がします。今の日本の研究環境が絶望的に悪いとは全く思いませんが、直すべきところ、正すべきところはたくさんあるはずです。ガチ議論で生まれた流れは、現在、カクタスさん主催のScienceTalksに引き継がれています。より多くの方々にこのような流れへの関心を持っていただくことで、今でもそう悪くは無い研究環境が、もっともっと良い方向に向かうのではないか。そう願っています。 中川 真一(理化学研究所 准主任研究員) . ガチ議論シンポジウムにご参加いただきました皆様、ありがとうございました。ガチ議論では今日の日本の科学研究における様々な問題がトピックとして取り上げられましたが、「ああ、これは自分が経験した・している問題だ」というものを多くの方、特に(私のように)キャリア形成の途上にある方は、おそらく複数、見つけられたのではないでしょうか。私の場合では、在外日本人研究者ネットワークの問題、ポスト問題、雑用問題などでした。本企画に関わる以前にも、そうした自分にかかわる問題について、ここはおかしいぞ、こうしたほうがいいのではないか、などと自分なりの思いやアイデアはありました。しかし、一研究者はそもそも非力で何も変えられない、ただ個人的な問題として受け入れるしかないと、どこかで諦めていたように思います。ガチ議論を通じて、一研究者の意見もそれが集まれば、大きな力を発揮する可能性があることに気づかされました。ガチ議論のコンセプトやフォーマットが共有・活用されて、研究者をとりまく環境をより良いものへとを変えていく役に立つのであれば、プロジェクトに関わった者としてこれ以上の喜びはありません。研究者が明るく研究に取り組んでいけるような世の中が実現されることを、末席に身を置く者として願っています。 小清水 久嗣 (藤田保健衛生大学 助教) . (これらの意見は筆者が所属する組織の意見を反映しているものではありません)
続きを読む
2014年4月30日
「ガチ議論」シンポ・テープ起こし (6/6)
2014.04.26 トピックス

前のページ – 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 宮野 結構お金の話になったけどね、やっぱり、その、tweetにもあったけど、研究環境。僕さっき、ちらって言ったけど、それやっぱり、お金取ったっていう、そのストーリーが、研究に専念できる環境につながっていない気がしてね。ダイレクトにさあ。お金、つまり…、「じゃあわかった生命科学バーンお金2倍です」って言って、それで、ヤッターって喜ぶ人いるわけでしょ。でも、それだけでなんか皆さんの研究環境よくなるのかなあっていうストーリーの部分が抜けてる気がするわけ。 近藤 そこまで、余っている研究室っていうのはない、ほとんどないと思いますけれどもね。 宮野 余っている? 近藤 ええ、結局お金が、そんなに余っている研究室っていうのは、ほぼ、ないと思いますけど。ただ、あるところはすごいあると思うんですけれども、ほとんどの人は常に足りない状態でやっていて、どうもなんかそこのところが強調しすぎだという気がしますよね。 宮野 ああ、そういうことか。 鈴木 あと、若干解説するとね、それは使う側の自治の問題です、っていうことがまず一つと。ただ、二つ目は、文科省が予算を増やしたいがために、いろんな新しい新規政策を出さざるを得ないんですよ。これは日本の予算システムの非常に問題で、本当は既存予算の増額っていう要求でつけば一番それがいいんです。だけど、それだと、ニュースの一面、要するに増額っていうのはニュースにならないんですね。新政策だとニュースになるんですね。というメディアの特性もあって、残念ながら、政治家は、あるいは財務省っていうのは世の中の、その政治家を通じて、世論センサーをものすごく働かせてて最後予算を決めるっていう。 宮野 それはどうよ、文科省。文科省のハンドリングの範疇なのか、財務省の範疇なのかという。どうなん? 鈴木 メディアの範疇だってことを言いたいんですよ。 宮野 そうそう。メディアの範疇って、どう? 川上 とにかく一元化するのをやめてほしいんですよね。議論を。一つの答えがあるわけじゃないんですよ。この議論のはじめの宮川さんの問題の提起の仕方でちょっとやっぱりものすごく不安を感じるのは、皆さん理系の世界に住んでいて、答えは1個ということになりすぎているような気がしてしょうがないんですよ。たとえば、学術会議の提言がなぜ採択されないのか?それは、答えは、学術会議から来たものだけが正解であるとは限らないからなんですよ。結局、政策っていうのは、1個の正解を出す作業ではなくて、何らかの選択をする作業です。その選択をするときに、我々選択の場に関わったりするわけですよ。決して官僚が勝手に選択しているわけでなくてそれはもう政治家、みんなで選択するわけですけどね。選択をするときには、やっぱり本当らしいこと、と、多くの人が考えること、それから、多くの人が言っていること、いろいろな判断基準のもとで選択をしていくわけです。そういうものなんだってことを、まず、理解をしていただきたい。それと同時に、選択であるからこそ、全員が満足するものではない。それこそ全員がイエスだ、っていうのはむしろ選択すべきじゃないと思うんですよね。そういうもんだ、っていうことを理解していただきたい。 山本 今、川上さんの言われたことは、実は学術会議もちゃんと分かっていることなんですね。学術会議は、あくまでサイエンスをベースに色々な正論を出しているという、そういう立場です。それで、科学者の行動規範にも書き込んでありますけれども、我々、科学者というのはやはりevidenceベースで物事を言う。しかしそれが政策に反映されるかどうかは、それはもう政治の判断であって、必ずしもサイエンスがこうだから、世の中はこう動かなければいけない、動いてくれとは言っていないのです。ただし、もし政治がそういうふうな、サイエンスによらない、サイエンスから見ればちょっとこれは取れないっていう判断をされるのだったら、その時はやはりそれなりの説明責任はあるんじゃないか、ということを述べています。だから、学術会議が言っていることが採択できないということは、当然それはあって構わないわけなんです。放射線のレベルがこれだったらこれぐらいの被害が出ますよ、って学術会議が言っているときでも、やはりそこに帰りたい人が多いのだったら、政治はそういうふうに判断するかもしれない。それはそれで良いわけですけれども、決定についての説明責任はあるでしょう、っていうことですね。それからもう一つ、ちょっと違う問題ですけれども、鈴木さんのいわれたことも非常に良く分かるのだけど、世の中で一般にいわれているのは、要するに教育とか科学技術っていうのは、票にならない、ってことですよね。だからいくら正論で分かっていただいても、最終的にはTPPに反対すれば何票かは絶対集まるとかですね、駅を作れば何票か集まるっていう話、そういう話と同列の議論になってきちゃうと、やはりこれは困るんじゃないかなと。 鈴木 なのでね、結局、政治家っていうのは別に利害、ステークホルダーのための利害だけやってて支持を受けるわけじゃないんですよ。だからメディアっていうのは非常に重要で、evidence-based policy makingとか正義に基づいた政策をやっている人たちが支持されるかどうかっていうのは、まさにメディアにかかっているんですよ。ええ。だけどメディアに対して基礎情報を出していますか、っていうことなんです。そこはやっぱりサポートしないと。それもadvocacyと。 宮野 大事だ。大事だ。 山本 ちょっと観点が違うかもしれないけど、我々、今、サイエンスの世界ではポスドク問題とか、いろいろ就職難があるわけです。それでさらにキャリアパスを広げなければいけないって時に、我々が議論しているのは、たとえば官僚の世界とかですね、それからマスコミの世界とか、そういうところがもっと間口を広げて、受け入れてくれればということです。さっき言われた、全然サイエンスを分からない方たちだけでサイエンスのポリシー作って、というのはやはりおかしいわけです。そのことを、さっきちょっと言われていましたけれども、もし本当にそうだったら、そういう間口を広げるっていうことを、実際に始めていただきたい。 宮野 ま、たしかによく大学も「そうや」って言うけど…。手短に。 川上 政治家の先生が関心を持つからどうだっていう点は、これが一つの解じゃない、one of factorsでしかないということですね。それは当然のことですよね。だから5人しか集まらない科学技術と、100人が集まる公共事業で、予算の伸びを見てみれば、こっち(公共事業)が下がっていて、科学技術はそれなりに上がっているわけですから。その、数だけではないです。だけど本当に現場でいて、行政の現場にいて、それは政治家の支持が有る無しっていうのは、もう支持していただいて、動いていただける人が、数が多ければ多いほど、仕事は前に進む。予算はいくらかでも伸びると思います。従って、政治家に対するadvocacyとか、政治家だけじゃないですよ、それこそメディア、もうぜひ、やっていただきたいなと思いますね。で、皆さんでやっていただきたいんです。各分野、みなさんでやっていただきたい。ある分野だけが熱心、という傾向がまたあります。そうなると、それだけで歪む可能性があるということを、申し上げたい。 宮野 よし。じゃあ、取ってつけたようですけれども、その、若手人材というかさあ…、あ、どうぞ。 安宅 いやあ、まさにそれをいいたかったんですけど、どうやって政治に影響を与えるかっていうのも大事なんですが、もともと、僕、先ほど言っているとおりどうあるべきかの議論を、ちゃんとやりたいんです。さっきからずっとTweetでもですね、若い人のことをちゃんとやってくれというのをずっと見ていて、そっちのHow論っていうのはここプロが集まっているのでそういう話になりがちなんですけれども、そっちのほうをちょっとやってみたいんです。さっきの僕のこの絵でいう、左側のですね、優れた人を集めて育てて維持するの側をしっかりやりたいと。先ほど、学術会議の先生もおっしゃったとおり、やっぱりポスドク問題とかっていうのはとんでもない問題で、凄まじい高学歴の人がですね、あぶれているわけですよね。相当数ですね。それどうすんだというようなことについて、ある程度、なんかここですくなくともここで意思決定、といわないまでも意思を揃えないと、この議論って一体なんだったっていう話になりかねないと、思っているんですけど、いかがでしょうか。ちゅうことを、ちょっと、投げ込みたいと。で、僕の考えだけをとりあえず突っ込んでおくと、ポスドク問題は何重もの間違いの結果起きていると思います。一つは、アメリカの大学院だけはよく知っていますけど、国外ではですね。terminal degreeでmaster’s degreeっていうnatural scienceのgraduate programはほとんど存在しないですね。アメリカには。基本的にはPhDプログラムのみが存在していて、drop outすると、1年とかでdrop outするともらうのがmaster。もしくは大学の4年間で頑張ったときに卒業と一緒にもらうのがmasterなんですよね。そうであるっていうのがアメリカの価値観なわけですけれども、日本の場合ですとほとんど同じようなスペックの人をですね、masterとして外に出してしまうんで、結局食い合いがおこって、若くて潰しがきくっていうことでmasterの人を雇えば済むっていうことで、もうそもそもPhDの人のニーズが市場に存在しないという、とんでもない問題が起きていてですね。大学院が食い合いのアウトプットを二つ出しているところを潰すっていうのがすごくあるというのが、背後にそもそもあると思うんです。それと関係なくですね、政策的に、大量にドクターを生み出すっていうことがかつて行われたためにですね、余っていると。ということで、二つの失敗をですね、反省して、まず、そもそもmasterなるものを潰すと、いうことと、私の提言としてはですね、doctor degreeを取るために入った人は途中で抜けるときに、「まあしょうがないね」っていって何もなくて出すとかわいそうだからあげるっていうならいいんですけども、そうじゃない訳の分かんない中途半端なものは潰すと、いうことと、途中で大量に排出してしまった部分というのは、国の失敗でしたと謝ってですね、何年か分の生活費かなんかあげて、いやいや、本当なんですよ、これは。あのね、皆さん多分ちょっとアカデミアにいらっしゃるんでちょっとあまりピンと来ないかもしれないですけれど、実際問題ですね、20数年前にバブルの後に大量に民間企業に行った人の多くは叩き出されたわけです。みんななんやかんやいって別の仕事やっているんです。全然関係のない仕事やってsurviveしているんです。同じなんですよ。受け皿がないところに大量にいたら出て行くしか方法はないんです。それは。そのことは事実として認めなくちゃいけなくて、ただそれは国なりアカデミアがやってしまった過ちなんで、そこはある程度面倒見てあげる必要がたぶんある、というふうに私としては、思うということを、2点、投げ込んで(おき)たいとおもいます。 鈴木 じゃあ、いいですか。一点目のことについては全く大賛成で、実はリーディング大学院という出島が始まっています。これがうまくいくのかいかないのか。さっきの共鳴の問題ですね。これもなんか、ぜひ、うまくいってほしいと思います、というのが一つ。それから、先ほどの山本先生の話にもつながるんですけれども、私のときは、産学人材育成円卓会議というのを作って、私だけでも、経団連の社長または会長に、20人に、直接、文系の修士、そして理系の博士を採ってくださいと。逆に言うと、採ってないことが、日本の競争力、特に日本というのは非連続なイノベーションに非常に弱いので、ここはやっぱり基礎基本、原理原則に立ち返った、そういうことを考え直す人材が少ないからだ、ということを説得をしました。それで、少なくともトップ20社についてはですね、CEOが人事担当専務に聞いてみて、それまではそもそも博士の採用っていうのは、研究所長がやっていたんですね。それをちゃんと、本体、っていいますか、headquarter本体の採用に変えてくれるっていう企業がかなり増えてきているということ、です。それから、リーディング大学院には各社がちゃんとどういうことをやっているのかっていうことの、ステークホルダーとして噛んでいく。そこにちゃんと口も出すし、そしてそこで口を出して育てた以上、就職先も出すと。という小さな出島が始まっているので、これをどういうふうに育てていくかっていうことです。で、ポスドクの話は本当におっしゃるとおりで、これは大きくいうと、一つは、まず大学のポストを増やす、っていうことですね。これは、なかなか厳しい中で上のポストを減らして若手のポストに振り替えるっていう、その資源配分をどうするかっていうこと。それから勿論、国公立の研究所のポストをどうやって増やすか、これ、同じ話ですね。それからやっぱり、ベンチャーだとかさっきもいった一般企業だとか、PhDを持った人を研究所でしか使うっていう発想じゃなくて、たとえば、いろんな海外のプロジェクト営業とかプロジェクト担当とか、こういうところで使っていくと。ただ、そういう要請をさっきの人たちはあんまりされていないので、そこのミスマッチというのが非常に問題なんで、ここは相当深刻な問題だっていうことは、理解しています。それから、もう一つですね、私はやっぱりポスドクの活躍先は、海外だと思っています。これは私2年前にですね、インドと、日印サミットというのをやって、その時の大学部門のディレクターを、日本側、任されたんですけれども、その時に、インドから、こういう提案をされました。今インドはですね、大学の進学率が10%なんですけれども、国策として、これ25%に引き上げていきたいと。そうするとですね、新規に1200の大学が必要になるんだそうです。すずかん、っていうか、日本に、200校作ってほしいと。まあ、ハードはできるんだと。インドで。しかし、人材、要するに教員と研究員と。そういう人材が全然足らないと。日本というのはいろいろ批判はあるかもしれないけれども、少なくとも研究者としてのPhDのクオリティーっていうのはインフレになっていないでちゃんと質が確保されているので、ぜひそこは協力をしてほしいという話があって、こういうところをどんどん…、ですから、私に言っていただければ、インドの大学の就職は探しますっていう、サポートしますっていう。これはわりと真面目で、たとえば東大のインド事務所を開設をしました。これは国立大学みんなで使えるようになっています。それから立命館大学もインド事務所を開設をして、そういうことを、体制をどんどんどんどん整えていくっていう、こと。こういうところはもちろん文科省もより積極的に応援していかなければいけないし、各…、ですから、200校ですから、掛ける500から1000ということなんで、えー、200掛ける1000は、20万?(と)いうことなので、ぜひ。HyderabadもNew Delhiもですね、Bangaloreもですね、空調はちゃんと利いておりますので。これ、真面目にね、僕は、日本の、日本に縁のあるサイエンスコミュニティーが、あんまり国粋主義みたいになっちゃうのもどうかと思うんですけれども、やっぱり働く場がないのは、事実だし、なかなか予算が厳しい中で国内でポストを確保するっていうのは難しいと。そういう意味で本当に海外にどんどんどんどん行ってですね、5年とか10年やってですね、 山本 シンガポールなんかへはもう出てます。 鈴木 出てますよね。そういうので、むしろ他の国の予算を使ってですね、我々がどんどんやりたい研究をどんどんやってくと。逆に言うと、研究しやすい国をこっちが逆に選ぶみたいなね、こと、ぐらい、戦略的にやっていくってことが、大事なんじゃないでしょうか、というふうに思います。 宮野 よし分かりました。それで?無理矢理でもいいのでまとめを?もうそれで終わりってことね。そしたらじゃあ。もう終わりですけれども、最後に、一言ずつ、言ってもろてね、最後、近藤先生にさくっとやってもらって。じゃあこれもできれば短い感じでお願いします。いきなり斉藤さんからですけれども。短い感じでね。 斉藤 むちゃ振りですね。またね。先ほどいろいろ私も参考になっていたんですけれども、まさに安宅さんおっしゃっていたその、戦略とかビジョンとかっていう話が重要なのかなと前からやっぱり思っていまして、このチャートを作ったときもそうだったんですけれども、やっぱりその全体を見ながら何をしたいのかというのが見えないのが問題で、何をしたいのか議論する場すらないのが問題なのかなということを思っていまして、なのでそこで少しずつでもそういう議論ができるような場を作っていきたいなということで、ネット上で色々やったりですとか、文科省の中でも活動を少しずつやって頑張っています。やっぱりそのさっき申し上げた行政というか政策を考える、っていま考えている人たちと、研究現場でまさに最前線でやっている方たちが直接の議論をしてですね、このガチ議論みたいに、直接コミュニケーションをとりながら相手の現状も分かった上で、両方動けるアクションプランみたいのを作る場がやっぱりどっかにないと、結局なんか浮ついた議論で終わっちゃうのかなという気がしていて、長期的な話と、なにをアクションプランとしてスイッチを入れなきゃいけないのかっていうのを、考えていかないとな、というのを改めて感じました、というのが感想です。 宮野 ありがとうございました。どうぞ。 安宅 唯一部外者の安宅です。元、部内者だったと。私の言いたいことは割と一貫していて、とにかくどうあるべきかをクリアーにした方が良いということです。それで、この二重サイクルを回すっていうのは変わらないと思うので、優れた人を集めて育てて維持する、っていうのと、圧倒的なvalueを出すっていう。優れた人を集めて育てて維持するところは大学院教育のところから、そもそも世界に伍しているとはとてもじゃないけど思えないので、ちゃんと、なんというんですかね、生活費も含めてちゃんとメンテしてほしいというのと、厳しく育てて、向いていない人はパッパと言ってあげて出してあげて下さいと、いうことですね。ポスドクの人も同じように、これで食っていけないと思う時は、ちゃんとフィードバックをするべきであって、それはあまりにも無責任ですよね。ダラダラと雇い続けるっていうのは。それはやめていただきたいと。それをしっかりやると。右側の圧倒的なvalueを出すっていうところについては、評価のところと、財源とのリンクに尽きるんですけれども、この評価のところがですね、先ほどの議論で口挟もうかどうか悩んで言わなかったんですけれども、若干短期的な話によりすぎているような気がしてまして、これだけはちょっと追加で言いますけれども、これ、戦略的な取り組みのイニシアティブをマッピングするポートフォリオなんですけれども、横軸が一体いつ頃刈り取るかで、縦軸がどのくらいその取り組みが、なんというかfamiliarか、なんですね。目先と、もう一つ先と、かなり先という。これ経営手法ですけれども、上側が今やっているfamiliarであって、次が誰かがやってで、一番下が誰もやったことのない未知と。で、左側になればなるほどですね、要は目先の刈り取りなんです。事業体がやっているんです。こんなものは、アカデミアがやる必要はないと。正直言って。だから産学協同の話を過度にやるとですね、左(短期的)になっていってですね、企業の手先になりますから、それはやめていただきたいと。何のために大学があるんだということを誇りに思ってやっていただかないと困ると。研究所も全く同じ。国立研究所なんてそのだけのために国費を投下しているんです。だからそこは絶対に這ってでも右(長期的)をやっていただかなくてはいけなくてですね、そのためにはですね、目先だけの評価システムを止めなければいけないと。よくcitation、citationと言いますけれども、citationみてんのは最低ですよ。本当に。何にも分かっていないと。あなたたちなら評価できるはずであってですね、本来、これが未来なんだとか、これが世界を変えるんだっていうものが一杯あるわけです。私もですね、相当激しいメンターについて鍛えられて来ましたけれども、例えば、私のthesis advisorの一人であったFred Sigworth、彼の25歳の研究でpatch clampが生まれてノーベル賞が出ているわけですね。彼は4人の、何千回と引用された論文、出していますけれども、それなんか、聞いたことのないようなわけ分かんないようなジャーナルに出ているわけですよ。それで数千回の引用が起きてですね、起きているわけですよね。それとか僕のいたneuroscienceで最も尊敬されている仕事の一つであるvisual cortexの研究っていうのがありますけれども、そのWieselたちの研究だってですね、すごい立派なjournalですけれどもJournal of Physiologyであってですね、別にNatureとかそういうものに載っているわけではないんです。でもそれが我々の脳についての理解を最も変えた論文なんですよ。実際問題としてですね。その前に出ている、neuroscienceで最も有名な論文の一つである、Hodgekin-Huxleyの研究も、Journal of Physiologyです。ですから、目先のcitationに捉われてそういうことでしか評価できないんだったら、それはアカデミアのreviewerやっている資格はないですし、そういうことはちゃんと見た上で、ぜひ評価していただきたいと。それをやった上で、もう一回この左に戻ってくるんですけれども、圧倒的なvalueを出すというサイクルをやっていただかないと、皆さんの誇りを持ったですね、せっかくのこのアカデミアにおける戦いっていうのが、無になってしまうと。これは是非ですね、左側はそういう戦いにしていただきたいですし、右側はちゃんと与えるものは与えてですね、評価するものは評価するという、当然の世の中の仕組みというものを回していただきたいと、いうことをやっていただけると、うれしいなあと思っており、なおかつ多分これが、このぐらいであればですね、45℃ではなくて42℃ぐらいのいい感じの温度感の社会になってですね、気持ちよくて、成長ももっとできると。今でもそんなに弱いわけではない日本のサイエンス、特にライフサイエンスすごく強いんで、本当にですね、アメリカに近寄れる、かなりいいところまでいけるんじゃないかと、思っています。以上です。 宮野 ありがとうございます。 川上 2000年に、ポスドク1万人計画というのが1万人にいきました。それで、そのときっていうのはまだ大学ではポスドクはそんなにいない時期ですけれども、そのときからですね、ポスドクが、ポスドク終わった人がアカデミアに入るっていうのは無理というのはもう、数の収支勘定で明らかだったので、2001年から何を言っていたかというと、キャリアパスの多様化。それから民間企業に対してポスドク経験者、ドクターを採る、採れ、ということをさんざん働きかけをしました。もう10年以上その歴史っていうのはある。だけどなかなかそれが前に進んでいかない。民間企業はそれでも採るようになったと思います。もう一つやっぱり考えてほしいのは、ポスドクになった人も、やっぱりキャリアパスはいろんなキャリアパスがあるんだ、ということを、本当に考えていただきたいと思うんですね。アカデミア志向が非常に高いというふうに、感じています。あの頃、経験したことでものすごく印象に残っていることを一つだけご紹介します。東大の物理のあたりだったと思うんですけれども、ポスドクの人が陳情にいらっしゃったんですね。どういうことを言ったかというと、私は運良くポスドクになりました。だけど私の隣にもう一人同級生がいるんだけど、こいつは自分と同じぐらいできるんだけれども、残念ながらポスドクになれませんでした。私の給料を半分にしてでもいいから、隣の友達と二人にして下さい、と。やめなさい、って私は言いました。やっぱり、中途半端な状況でポスドクを続ける、それが人生の選択の幅をどんどん狭めることになるので、私はポスドクはポスドク、しっかりやる、だけど、ポスドクになれなかった隣の君は、やっぱり、何か違う道を考えるべきだ、というふうに思いました。なかなか、そういうふうには現場はいかないと思いますけれども、人間の一生はやっぱり重要なことなので、引きずるんじゃなくって、ダメなときにはダメ、というふうにやっていただきたいな、というふうに思います。行政という、ともすると高いところにいてこんなことを言うのは無責任ですけれども、よろしくお願いします。 宮野 ありがとうございます。僕も1パネリストとして感想だけ。何も考えてませんけど、やっぱり鈴木先生おっしゃった、「個人の問題」って、やっぱ響きました。例えば安宅さんおっしゃったのも、僕もう論文書かないと決めれるわけなんでね。僕本当に最近実は政治科学というか学問論のところをやっていてね、科学ってなんて特別なんだろうって、こと思って、何でこんなに…、ぶっちゃけ、アンチ科学なんですよ。すっごく偉そうにしてさあ。鈴木先生おっしゃるように、人文の方ももっと強くなきゃいけないし、両方ともダメだなダメだなあと色々思っていて、自分たちすごく特別なんだって自覚をしてはじめて僕、やっぱり自分の研究を見つめ直したって経緯があってね。そういうこと思いました。皆さんの敵は、フェーズによって、皆さんのライバル、違うなと。例えば隣に座っている人であったり、フェーズによって、他分野であったり、国であったり、ただやっぱり、学問、って、そのなんちゅうかなあ、競争力上げるためでもないし、論文書くためでもないし、そういうところの価値っていうのは絶対持ち続けて、よく考えたら行動できること一杯あるなと思った。最後のまとめは近藤先生ですよ。すいませんね、ケツ拭かせて。はい。 原山 3時間という議論の中でまとめもへったくりもないんですけれども、共有できる部分で、個人、個の位置づけであってそれぞれ人によって背景が違うし、立ち位置も違うし、家族の話もあるんですけど、やはり、自分をどうするかっていうのは、最終的に自分が決めることであって、それをいかに周りの環境をうまく使いこなしていくかっていうところなんですね。それで、環境もいかに良くしていくかっていうのがある種の政府の役割であって、その中に私の仕事もあるっていうふうに。位置づけです。でもすべてが政府がなんとかっていう話では全然ないと思っていますし、限界があった上です。また、政府の中で意思決定するところもやはり人間ですから完全にパーフェクトにはいかない。ですので必要に応じてメッセージとしてこれはおかしいんじゃないか、というのは必要であって、その中で、対話って、すごく重要だと思っています。これも対話の場ですし、私はもう基本的には、呼ばれればどこにでも行って議論しますし、また、そこから、どちらかというと吸収するつもりで行っています。ですので、今日も吸収させていただきたい。で、一つconcreteな話ですけれども、やはり意見を持っている方達が、建設的な側面の意見をいかに反映させるかっていうのがやはり難しいところで、それに対するなんか一つの突破口みたいなものを作れればなあっていうのが私の個人的な意見です。 鈴木 まず、こういうね、ガチ議論をやっていただいたっていうことが素晴らしいと思いますし、このことがほかの学会にも広がってほしいし、分子生物学会がその先頭で、これをさらに続けていただきたいっていうのが、お願いです。私も「熟議」っていうことをずっと言っているので。それで、その時にですね、二つぐらいお願いしたくて、私は「人が大事」っていう話を書いて、…まぁこれ、川上さんにほとんどやってもらったんだけど…、「科学の甲子園」っていうのを立ち上げました。で、もちろん書いてできていないことも勿論一杯あるんだけど、書いてできていることも、実は一杯ある、っていうことで。これはadvocacy にもものすごく重要な話で、さっき言った5%っていう話はね、別にメディアや政治家だけじゃなくて、やっぱ次の世代に対するadvocacyっていう、それは非常に重要で、やっぱり科学の甲子園やったりあるいはオリンピック、サイエンスオリンピックやるときに、分子生物学会をはじめ色々な人が、本当にいろんな貢献をしていただいているというのは素晴らしいし、そういうことはとっても大事なことだっていうことを申し上げたいと思います。それから、やっぱり基礎科学の人に、これ熟議のテーマの一つにもしてほしいんですけれども、この研究は何の役にも立ちませんからっていう口癖はやめてほしいと思うんですね。やっぱりね、何に役に立つかっていうのは、やっぱり、ちゃんと考えて、言葉にしなきゃダメですよ。それは。それで、私昨日も一昨日も、修論の指導をしていたんですけれどもね、今私たちは、これ公共政策大学院で教育政策の修論ですけれども、高校の教員に、研究論文を書かすっていうmovementをやったり、あるいは高校生に卒論を書かすっていうことを、一生懸命やらそうとしています。ある種、研究の一番最初なんだけれども。別に、彼ら、全然、ほとんどの人が研究者になるわけじゃないし、あるいは高校の教員はずっと高校の教員です。その99%は。しかし、やっぱり研究をやることのcore valueっていうことを徹底的に議論してほしいんですね。これ実はスポーツ基本法を作るときに、スポーツのcore valueっていうことを徹底的に議論しました。で、スポーツなんて、もっと役に立たないんですよ。ええ。だってもう100メートル競走終わっちゃったら終わりなんで。まだね、特許が残ったり知的財産が残ったりするだけましなんですね。でも、やっぱりスポーツの人たちは、徹底的にcore valueは何かっていうことをちゃんと言語化しました。本当にその人その人のいろんな物語やいろんな、それは別に一つに終焉する必要まったくなくって、永遠に繰り返すべきだと思います。それで、高校生、あるいは高校の教員にも研究を、ということで、その答えの一つがね、これ、たまたま中央大学の文学部の浅川先生っていう人が1984年に、George Owellの研究者ですけれども、言っていて、decentに人間がなるためだ、って言っているんですよ。decentに。これも、研究をやることの大変大事なcore valueだと思うんですよ。その時にこれから少なくとも、これは一つの例だけれども、皆さんは自信を持ってですね、人間がdecentになるために、そのトップランナーに、人間の持っている可能性というものを振り絞って何かに、なんていうかな、向かっていくっていうことが人間を人間たらしめるんだぐらいのことはですね、やっぱ自信を持って言っていただきたいと、いうふうに思います。なんか最近ね、やっぱアカデミアの人が、なんか自信喪失になっているのが一番良くなくて、文科省も、政治家も、みんなよくわからないんですよ。分からない中で、やっぱり本当にさっき言ったね、みんながそれぞれ役割は違うけれども知恵を出し合って、なぜ基礎研究をやらなければいけないか、なぜサイエンスをやらないといけないかということを、本当にその同じ立場で、これから深めていこうということを始めていただければと思います。 宮川 「科学技術にまつわる議論の課題はこの日ここで完結する」、というキャッチフレーズは、見事に失敗に、終わったと。完結しませんでした。申し訳ないです、スタッフとしまして。ここでやっぱりでも申し上げたいのは、科学技術にまつわる議論、このいろいろ一般的なですね、科学技術全般にわたる議論というようなことを、学会matter、その分子生物学会だったらその分子生物学という、そこに議論を絞ってしまうんではなくて、学会matterを超えたことも、その学会でちゃんと議論するというようなことをやっていかないと始まらない、と思いますので、是非こういったことをですね、今後、ここの学会はそういうのはやらない?んですよね、いやちょっとよく分かんないですけれども、もしかしたらやるかもしれないんですけれども、こういった試みを他の学会でも、あるいは学会でない別の組織でも、何でもいいと思うんですけれども、ぜひ、やるという、文化みたいなものをですね、やっていかないと、どんどんこの自信が喪失した状態で行ってしまうと思いますので、これをぜひ、皆さんやりましょう。声をどんどん上げていく。 近藤 すいません。座っていると倒れそうなんで、アドレナリンを上げるために…。 宮野 もうそれ最後よ。それ終わったら、終わりましたーって言って。 近藤 一番印象的だったのは、一番研究者に明らかに厳しそうな安宅さんの応援が、我々の心に一番響いたっていうところは、非常に印象的でした。確かにその通りで、我々は自分でやっていることにもっと自信を持ってやんなきゃいけないなあと。いうふうに思います。 宮野 たしかに拍手してる、拍手したけどさあ、そういうアカデミア作っているのは僕らだからね。 近藤 [...]
続きを読む
2014年4月26日
「ガチ議論」シンポ・テープ起こし (5/6)
2014.04.26 トピックス

前のページ – 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 – 次のページ 宮川 日本学術会議の資料出していただけます?この資料の33なんですが。 宮野 20時回ってますね。どうしよう? 宮川 これ、9時まで取ってあります。 宮野 どう考えても、こっちも、こっちも…、ちょっとブレイクは入れる。もちろん、さあガチ議論なんで、さあまたやりましょうかなんてTweetもあったけど全くその通りで、我々もそういうつもりでここに座っているんですけれども、ただ、聞き漏らすまじ、とみんな思ってるんちゃうかなあと思って。聞き逃したくないなあとみんな思っているんじゃないかなあと思ってね。いったんbreak入れた方が良いなあと思ってね。2時間経ったし。5分ぐらい。きついね。 宮川 本当は10時まで取ってある…。 宮野 やろう、やろう。やろうぜ。大事なことだよ。 近藤 そのあとも皆さん今日、お泊まりだそうです。年会長権限で、皆さんの分は出せませんけれども、どっかで続きをやってくれても一応構わないってことに。私自身はもうちょっと2日ぐらいもう寝てないんで、限界なんですけれども…。一応そこはガチということでよろしくお願いします。 宮野 じゃあ5分?10分!15分から。 宮野 よっしゃー。じゃあまた始めますね。決して休憩中も我々集まって話したわけ全くなくって、普通にトイレに行ってパン食ってただけなんで。糖分ちょっともらっただけなんで。引き続きこういう雰囲気なままで、お送りできればと。で、どうやらUstも1200とかいって、1800?会場も400とかいて、2200とか見て、良いのかなあと思いつつ、なんか壇上で安宅さんも写真撮ってはるし。いい雰囲気になってきたなと思っています。別にまとめる気もないですけれども、また思ったこと、ばーっと吐き出せばいいなと。 宮川 さっきの続きの、声を上げる仕組みっていうのを…。 宮野 一気にぎゅっと戻したね。 宮川 日本学術会議の資料をちょっと出してもらっているんですけれども。「日本学術会議では各論ばかり議論?」というスライドを出してもらっているんですけれども、これ、どういうグラフかと言いますと、そっちに出ているやつですね。日本学術会議のホームページを見ますと提言みたいのがいっぱい出てるページが。ちょっと言葉で説明しますと、グラフがありまして、このグラフが何かというと、日本学術会議のホームページには提言がいっぱい出ているんですね。色んな提言が。その提言を我々でグラフ化してみたものなんですけれども、灰色の部分が個別の話ですね。100万人ゲノムとか、それぞれの業界のこういうプロジェクトをやりたいみたいな提言が、この灰色の部分であって、赤い部分が何かというと、科学技術政策一般みたいな、全ての科学技術の分野にまたがるようなお話に関する提言が赤いので記されているんですけれども、ほとんど、科学技術全般の施策に関する提言というのはないんですね。日本学術会議。僕は皆様とお話ししていて、こういう、なんか一般の研究者の声みたいのがあった時に、本当は日本学術会議って研究者のボトムアップの声を公式に国に提言するような、そういう場なんじゃないかと思うんですけれども、そういう機能が全然果たせていないんじゃないかと。そのような機能を日本学術会議でもいいし、総合科学技術会議でもいいし、新しいものでも何でも良いんですけれども、そういうものですね。お金をかける必要はないと思います。ネットとかでも良いと思うんですけれども、そういうルートみたいなのがあったほうが。lobbying活動っていうのも重要で、そういうルートがあったところで結局人に、重要な人物にお話ししに行かなきゃいけない、と、そういうことはあると思うんですけれども、そういう、分かりやすい、透明なルートがあるってことが、大事なんじゃないかなと。今日、そういうお話、ぜひ、なんとか、実現していただけないかなと、ちょっと思うんですけれども。 鈴木 いいですか。いや、僕は全く大賛成なんですよ。大賛成で、私自身も日本学術会議がこういう政策についての提言をもっとしてくれたらね、いいなと思っているんですが、一つやっぱり、原山先生みたいな先生の質と層がやっぱ日本はあまりにも薄いですよね。こういうことをちゃんとオーガナイズしていくっていうか。結局、教育議論でも研究の議論でも、自分の経験をすごく一般化する傾向っていうのが非常にあって、そこの危険性に陥らないためにはやっぱり科学技術政策の専門家集団、っていうかね、が、もっと分厚くなるってことが大事だと思うし、かつ、それは、今のご提案は僕は最大限応援したいとは思いますが、どこがボトルネックなんですか?大西さんはそんなに理解のない人じゃないと思うんだけれども。僕別に明日にでも電話してあげてもいいんだけど、ちょっと一回やってみたらどうですか。あるいは、明日分子生物学会で日本学術会議は今なに、1本とか4本とかっていっているものを、10本ぐらいに増やせとか、あるいはもう科研費の基金化の前面化については、もうやるって言って大会決議をしてですね、学術会議の、今日もおそらく幹部が見えていると思いますけれどもその紹介で持ってっちゃって、どこが引っかかってどうなるかっていうのを…。 宮川 学術会議の先生いらっしゃいますよね。この中で…、山本先生はいらっしゃらない?もしよろしければマイクを…。 山本 学術会議の第2部、生命科学の部長をしています山本です。まずこのグラフですけれども、学術会議の仕組みは、全体のことを決めている幹事会という組織がありまして、それから3つの部、人文社会科学、生命科学、理工学に分かれた3部構成です。さらに例えば第2部生命科学であれば、その中にまた9つの分野別の委員会があります。基礎生物学、統合生物学とか、基礎医学、臨床医学などの形で9つあります。さらにその分野別委員会の下に分科会がありまして、2部では全部で100以上の分科会があるのです。それぞれの分科会は例えば免疫学だとか林学だとか、それぞれの領域にspecificな問題を取り上げているわけです。あとですね、今期は大西会長のリーダーシップで設置されたものもありますけれども、課題別委員会という、学術会議全体で課題を取り上げるような委員会もあります。例えば日本の少子化のこの先はどうなるんだろうかとか、科学者の意思を社会にどうやって伝えるかとか、そういった、非常に一般的な、たぶん宮川さんがそこに書かれている科学技術全般の施策に関するような提言を出すような委員会が10ぐらいあるわけです。重要課題を取り上げるという意味で。そうすると、全体としては300ぐらい細かく分かれた分科会があって、それらそれぞれに提言を出す権限があるわけです。実際提言は出てきます。ですから統計的にご指摘の数になるのは当然なんです。むしろ今期なんかは課題別委員会の活動を強めています。現在論文不正の問題とか研究費不正使用の問題、これについては会長が委員長になって取り組んでいますし、それから今期は原子力発電の将来像とか非常に重い課題があって、こういったものも全体で議論しています。ですから、これ単に全部の分科会にですね、みんな科学論を議論しろというのは成り立たないことで、それぞれの分野にspecificな提言があってもいいことです。それからこれもまた分かりにくいのですけれども、学術会議からの意見表明は強い順でいうと、勧告、要望、声明、提言、それから報告という形になります。普通分科会など小さなグループで出すのはせいぜい提言どまりです。例えば今期「科学者の行動規範」の改訂版を出しましたけれども、これは声明です。ですから、勧告、要望、声明というところを見ていただければ、そこのレベルでは少なくとも科学界全体を見渡したものを出している、とそういうことになります。 宮野 なるほど。分かりました。分かった。 近藤 学術会議が声明なり提言を出した時に、文部科学省はどれぐらい正確にそれに従って動くんでしょうか。 山本 多分、文科省で考えておられるのにぴったり合うような提言が出てくると拾っていただける…。 近藤 でもそれでは提言にならないですよね。それだったら提言しなくとも良かったということに…。 山本 おっしゃる意味は分かります。それはだからその政府なりと我々とのすりあわせで…。 近藤 それで学術会議と文科省の考えが違っていたらどっちが強いんでしょう? 宮野 強制力っていう意味で? 近藤 ええ。 山本 それは分かりませんね。学術会議は鈴木さんが言われた通り、法律で定められた提言権というもの、権利は持っているわけですけれども、執行機関ではないということはもう何度も何度も言われていて、予算付けてくれと言っても執行に関する予算は一切つきません。ですから、現状は言いっぱなしです。 斉藤 提言の扱いについて一行政官視点なんですけれども、多分提言がまとめられると、会長から大臣とか局長とかに手渡されてっていう感じで正式にくるんだと思うんですけれども、その時点ではもう全く変更ができない状態でバチッと来ますし、しかもそれを見て担当の課とかに降りてくるわけですけれども、分かるところもあるけれども色々事情もあって、もっとここは踏み込んで議論しないといけないよねとか、ここはもうちょっとこういうふうにやるやり方もあるんじゃないのかなとか、言いたいことは一杯あるんですけれども、これで、というふうに来ちゃうので、なかなかそのすぐに動けないみたいな面があるのかなと思っているんですね。だからそのいきなり上から上っていうルートだけではなくて、そういうものを一緒に考えていくような仕組みが、行政も、中堅か若手で、多分、研究者、学術会員も含めて中堅若手の人たちが、本当にその現場も見えているような人たちが横につながって一緒に提言を作っていくような仕組み、で、そこでできたら両方の上に上げていくような、仕組みがいるのかなというのは常々思っているところです。 原山 国内じゃなくて英国の事例なんですけれども、英国にはRoyal Societyっていう、歴史ある由緒正しい学会の総本山みたいのがあるんですけれども、あそこでも一つのビジョンとして政策提言に関して議論してしっかりとしたエビデンスベースのpaperを出しているわけなんです。外部からみるとその提言した内容にかなり近いものが政府側の意思決定する時にreferしながらやっているのと、公の場でもって我が社の場合は、我が国の方針というときに、それとかなり似たような文脈の事が書かれているってことは、共鳴しているわけなんですね。それは、長い歴史の中で、また人によっても違うんですけれども、Royal Societyのヘッドをしている方がアメリカでもってバリバリやっていた方が戻ってきて新風を吹かせていると。強く制作側にも働きかけているし、新しい共鳴の関係ができている。やはりこれは作り込まなくてはいけない話であって、単純に制度でもって法律でこれがruleしているからできるものじゃなくて、やはりそれを引っ張る、コミットする人が中にいると行くし、そうじゃない場合やはり、ふらっとなってしまうという現状だと思うんですね。今の大西先生っていうのは総合科学技術会の充て職としてメンバーになったわけなんです。で、基本的に総合科学技術会議っていうのは、基本計画作ったりとか科学技術政策に本質的なところを決めるところなんだけれども、その中に必ず学術会議のトップの方が入っていると。今制度上は情報が入るようになっているし、学会、いわゆる学術会議っていうのは一応複数の主たる学会の総本山であるから、個々の学会の方達が言えば、その形でもうすっと上がっていく、そのルートはできているんですね。でもそれをどのように活用していくのかっていうのはpracticeなんです。それはやはりしていかなくてはいけないし、その方針として色んな大事なコアとなるとこをまとめているんですけれども、やはりお互い持ちつ持たれつで、総合科学(技術会議)でできないことは学術会議で出していただいて、それを使うものは使っていく。そういうやり方っていうものをやはり試行錯誤ですけれどもやっていかなくちゃいけないと思います。 宮野 それやっぱちょっと問題意識があって、この前とある御大の講演を作る時に調べたんですけれども、3.11以降、提言の数、調べたんですよ。グラフで。どわー(っと)、増えてるんですよ。もうやっぱり明らかに何というかな、その提言にかかるエフォートってすごいエフォートかかるんですよ。でもそれ安宅さんの言うね、戦略と違うんですよね。ねえ。だから、しかも敢えて言うと政策のための政策というか、言葉は悪いけども、総科である提言に書いてあるから文科省やりますっていう、ひとつのエビデンスになっていますよね。それがなんか元々そうは違わないですよね。まず。近藤さん、おっしゃった質問に絡むけど。そうは違わないんですよ。燃料電池?大事だ!そりゃ大事だ!みたいな。だから、エビデンスに使っていて、それが、その、それこそ原山先生がおっしゃる、その、ビデオとかにあったけど、末端…、ってここ指してすいません、現場の研究者にいくまでにどんどん丸め込まれてね。やっぱ全然効果発揮していないという現実はあるような気がするんですがどうでしょうか。って、まただれかにむちゃ振りしているという…。 原山 じゃあ皆さん考える間ちょっと、余興じゃないですけれども、先ほど鈴木さんがおっしゃったように科学技術の政策のための科学っていう柱は建てていただいたんですけれども、ちょっと大風呂敷というか、中身が伴わないという斉藤さんの指摘があって、そこは、どこに、何がネックになっているかっていうと、そういう文脈でもって研究する人の研究者層がすっごく弱いんですね。ほぼいない。私がなんで総科なんかに入っているかっていうと、たまたまそういうことを研究対象としていて、たまたま女性であって、たまたま海外にいたからっていう、色々な条件が揃って私がこの立場にいるんですけれども、やはりこれを、層を厚めに作っていかないと、いつまでたっても、大きな声の人がこれが重要だから、だからそれが政策になるっていうなりかたになってしまう。それも、声の大きい人たちは、自分たちの研究者としての積み上げがあって、感性っていうのがあって、鼻が利く人がいるわけなんですよね。その、(鼻が)利くのもすごく重要なんだけれども、それが、その匂いがちょっと弱くなった時に、その人に判断を任せていいかっていうと、必ずしもそうじゃないので、バランスを取る意味でそういう人とプラスにもうちょっと全体像をscientificに見渡せる人が必要だっていうのが私の現状認識です。 宮野 分かった。ここでちょっと議論を整理したいんですよ。割と混同していると思うんですよ。いろんなところでね。何を言いたいかといいますと、政策提言ってそもそも何か、っていう話ですよ。領域決めるってことですか?研究者自由な発想でやるって言っておいて、この領域やって、っていうのはなんかおかしい。つまり何を言いたいかというと、内閣府が総科なんで、やっぱりそれはメシの種だと思うんですよ。ちがうの?メシの種、産業、競争力になるっていうことを目的として領域設定するっていう事ですか?総科の提言っていうのは。アカデミアの領域を、ぼうっと強化するんじゃなくて。 原山 「メシの種」ってどういうふうに理解すれば良いんです? 宮野 ま、技術につながるというかね。産業を生むとか…。 宮川 いやそのメシの種だったらメシの種で良いと思うんですけれども、領域設定というか、要するにどういう分野にどれくらいの、重点的に配分するかっていうそういう問題があるっていうことですよね。 宮野 それは何を目的として? 宮川 予算は限られているわけなので、どういう分野にどういうふうに配分していくかと、いうことを、総合科学技術会議でされるわけですよね。重点的に大型プロジェクトとかを選別するとか。そういう話…。 原山 私、今、日本に2年いなかった頃の話なんですけれども、基本的に科学技術基本計画っていうのを5年ごとに作っているっていうのがベースですよね。96年以降。それが、大方針を示して、それを踏まえた形で関連省庁、その中で最も大きなactorっていうのは文科省なんですけれども、が、政策を立てる時にその方針にあった形でもって立てていって、予算化してっていうそういう一連の流れっていうのは一応皆さんがアクセプトしている状況な訳です。その中で第3期まではどちらかというと今おっしゃったような特定分野、これが重要だ、日本の将来のためにこれが重要だという分野を4つから8つ立ち上げて、それに重点的に投資するという、ま、流れをしたわけであって、と言いつつもわりと幅の広い領域だから、こじつければ全ての人たちの、私のプロジェクトっていうのはここに入れるって、それは作文的にできることであって、それをいかに目地切りするかっていうのが各省庁の難しいところなんですよ。そういう方針があったんですね。それに対して今第4期の真ん中なんですけれども、ここで舵切りをしたのはそういう、その、分野をピックアップするっていうか、日本が解決すべき社会的大きな課題っていうものを大きくいくつか取り上げて、それに対する解決策というか、それを乗り越えるための科学技術イノベーションていうふうに打ち出したわけなんですよ。それは前の方達が作ったからそれをgivenなものとして、私、今、ハンドリングしていると。そういう流れっていうのは日本だけじゃなくて、G8の国、ほぼ全部シフトしているのが昨今の流れで、課題解決型の科学技術政策ていうのが今流れになって。別にアメリカがやるから後追いする必要もないし、日本がやるからダメなんじゃないけれども、同じ方向に向いていることは確かなんですね。しかもその中で、そのための、役に立つ技術、役に立つ科学っていう発想っていうのがその根底にあって、それが強く流れているっていうのはやはり財政危機があって、なんか役に立つものでないとっていう、そういう色んな背景があるわけです。その中で今の政策があって、で、と同時に、その、いわゆる競争力っていう、さっきもおっしゃったような、安部政権になってなおかつそれが強くなってきたわけなんですけれども、それだけで十分かっていうと、完全に、表面的なことしかないわけですよ。今日、明日の話で、閉じるんならそれで良いかもしれないけれども、やはり、人がいて、それから研究者層っていうのは一、二年で作れるもんじゃないし、今のうちにinvestしていなかったら将来目が出るところに人がいかなくなったら困るわけですよね。だから基盤的なところも手当てしなくちゃいけない。そのバランスが重要であって、バランスをどういうふうに取っていくかっていうのが、政府の舵取りだと思うんですよ。その、基盤的なとこっていうのはさっきおっしゃっていたみたいに、すぐに目に見えないから、お金つけない、でもそれも担保することがいわゆる国の役割でっていう、アメリカもうかなり言い切っているわけですよ。目的思考と同時に、肝心なのは人であって、それに対するinvestmentはしっかりすると。基礎研究もあってって。大体皆さん、両刀使い、しているわけです。どこに線引きするかっていうのは国によって違っている。 鈴木 と、書いてあるわけですよ。ポイントはね、どういうことかっていうと、原文読んでいただければ、私も科学技術振興計画の方には関わりました。課題型とか、あるいは特に人材っていうコンセプトを相当出したのは、その通りですね。まず、原山さんのさっきのお話で、本当に層が薄いので、ぜひ、僕は今日リクルートに来て、5%ぐらいの人が原山門下生になってくださいっていうか、そういうそのトータルの戦略を。今ね、power-based policy makingなんです。これをなんとかevidence-based policy makingにしたいので、で、例えばその総科の問題にしても学術会議の問題にしても実はメンバーの問題っていうよりも事務局の問題なんですね。事務局の数と質と多様性の問題です。私、もともと国家公務員でそのあと学者になりましたけれども、法律を書くとか予算書にするとかものすごく得意なんです。そこは。だけど、必ずしも別に科学技術のいろいろな現状を分析し、それを戦略に引き上げるっていうのはそういう訓練とかそういう評価をしてきた人ではないので、村上さんとか斉藤さんを前に、もちろんそういうことを、一生懸命努力はしているけれども、全部役人だけで事務局やるっていうのはなかなかもう限界があるよね、っていう議論をしてきて、何で科学技術政策のための科学をやったかっていうと、5年ごとか10年後にはいわゆる今のお役人みたいな人が事務局の3割から4割いてもらって、残りの3割ぐらいは原山先生の門下生みたいな人たち、もちろん反逆してもいいんですけれども、この周辺、この分野の人たち。それから残りの3割ぐらいはそれぞれのフィールドにおいて非常に強い人。こういう事務局体制ができたらいいよねというもとに。すぐには解決はできないと思います。少なくともPhDがでて、そういった人たちが現場でいろいろトレーニングを積んで、そして一生ずーっと事務局にいたらそんな人は使い物にならない訳であって、研究の現場を歩き、そしていろんな具体的にラボのadministrationとかmanagementもやり、そして、15年ぐらいたったところで、10年ぐらいたったところで、そういう事務局に来てっていうローテーションを2回ぐらいまわすっていうような人材イメージを考えていましたと。そういう、もちろん博士から入ってくれる人もいてもいいし、2周目ぐらいからですね、入っていただく方もいてもよくて、そこに僕は一緒にリクルートに来ましたので、5%ぐらいの人はですね、そちらに転向するのもよし、それから35歳ぐらいになったらそっち側にちょっと加勢してくださいという、そういう話が一つと。それから今の文章はまあまあそこそこそれなりに文章としては、計画としてはきれいなものになっていますが、やっぱり弱いのはそれに至るエビデンスとか、立論とか、その部分がもうちょっとあってもいいかもしれない、というが今の反省点。ただ、最大の問題は、じゃあ計画通り予算がついているのかと。そこなんですよ。要するに。 宮野 そうよね。その提言がちゃんと活かされているかというかね。 鈴木 そういうこと。だから提言もいい提言出しているし、総科のpaperもですね、もちろん100点とはいえないけど、なかなかいいできです。それでちゃんと基礎研究にも配慮しているし、いろんなバランスも見ているし、何かを切り捨てるっていう文章になっていません。しかし、しかし、そのことと、仕上がりの予算は全然、まあ全然とはいわないけれど、違うものになっていますと。で、僕は今日ずっと申し上げているのは、これは、文科官僚の責任は3割ぐらいなんですよ。それは財務省を説得しきれないという責任と、それから国民の支持を皆さんの代弁者として獲得しきっていないという責任はあるかもしれないけど、しかしそれはですね、国交省も、経済産業省も、総務省も、みんな頑張っているわけですよ。その中のプライオリティと、ある種の広い意味での政治力の勝負になっていると。予算をとるって言った瞬間からはね、もうきれいごとでないってことを言いたいわけ。さらに言えば、文科省はすごくよく頑張っていて、なぜならばですね、科学技術の分野を応援しようって言う政治家は5人ぐらいいたのがいまや3人ぐらいに減っているわけですよね。国交省には応援団が何人ついているかっていうと400人とか500人いるわけですよ。720分のですよ。その割にはパフォーマンスは極めて高いっていうのは、まず、だからこういうのは要するに役人と、現場の関係者と、それを束ねるいわゆるコミュニティーの、これは学術会議になるんかもしれないし分子生物学会になるのかもしれないけど、それのトータルの政治力っていうかね、要するにもっと言うと国民の支持を獲得するチームとしてこの分野が、公共事業に対して弱いという話なんです。私はコンクリートから人へと言って、研究費を増やし、科研費を増やしたけど、結局、いまや議員でなくなってきているわけで、その話を言いにきたわけじゃないんだけど、だけど、そらそうですよ。研究強化法とかの話だって、超党派の部会をやったってですね、もう一桁しか来ないんです。国会議員は。だけど一方でTPP反対のですね、農業問題だったらですね、直ちに議員会館が満員になると。やっぱこの状況をまずちゃんと直視しないと、提言は、少なくとも予算のことについては生かされません。それから労働者契約法については今回研究開発強化法で僕の置き土産ですけれども、なんとか議員立法で改正すると思います。10年、5年を10年に。だけど、これだってですね、結局いわゆる研究者の働き方の特殊性について、やっぱ社会がそれはnegligible、smallだよね、っていう議論になっちゃったってことなんですよ。 宮野 宮川先生。 宮川 よろしいですか。今すずかんさんがおっしゃったことって、本当に日本の研究者コミュニティーにものすごく足りないと思うんですね。いわゆるそのちゃんとその政治家の方々とかにどれだけ基礎研究が重要なのかとか、そういうのをしっかり、なんというんですかね、advocacyっていうんですかね、advocacy。それをやるっていうことを、全然しないですね。研究者コミュニティーで。その政治家の方々となんかお話ししているのはちょっとdirtyな感じの研究者だみたいな。 宮野 でもまたそれも研究者にじゃあドーンとやれ、ってこと?研究以外の…。 鈴木 やらなかったら、来ないっていうこと。 宮川 全員はやんなくていいんですよ。全員はやらなくてよくて、研究者コミュニティーとして、代表を出せばよくて、アメリカの神経科学のSociety for Neuroscienceは、advocacyに関することすごくやっていて、毎回、いつもNewsletterにadvocacyのこと書いています。政治家のコングレスに行ってこういう説明をしましたとか。そういう、それ関係のは必ず書いていますよ。 宮野 [...]
続きを読む
2014年4月26日
論文のオープンアクセス化を推進すべき7つの理由と5つの提案
2014.04.14 トピックス

概要スピードやコスト、情報価値の重み付けなどは、科学技術研究に関する情報交換を行う上で重要な要素でしょう。これらにおいて、電子媒体は紙媒体に対し多くの面で圧倒的なアドバンテージを有しており、オープンアクセス化(OA化)は必然の流れとなると考えられます。しかし未だに、科学技術研究に関する情報交換、研究者間のコミュニケーションにおいて、紙媒体を持つ科学雑誌への論文発表という方法が主流です。そこでは多くの場合、課金の壁(Pay Wall)が存在し、誰もが自由に論文を読むことはできません。これはいったいなぜでしょう?何か特に明確な抵抗勢力が存在するというわけでもなさそうであり、我々研究者や行政がOA化のメリットを明示的に認識していないということが大きな原因の一つであるように思われます。古い仕組みを変えるにはある程度のエネルギーを要しますが、おそらくその源となる根拠がはっきりと意識されていないのです。そこで、本稿では、OA化のメリットについて「OA化を推進すべき7つの理由」として改めて整理してみました。さらに、OA化を押し進めるための方策についても既存の枠組みにとらわれず検討し「5つの提案」としてまとめてみました。議論の呼び水となるよう、少し変わった提案も入れています。ぜひ皆様、忌憚のない御意見をお寄せください。また、ユニークなご提案も歓迎いたします。 I. OA化を推進すべき7つの理由 1. 部数が増えてもコストは増えない 2. しかるべき数・分量の論文を出版できる 3. 公表までのスピードが上がる 4. スライドや教科書、一般書籍などで再利用しやすい 5. 情報価値の重み付けがしやすい 6. 不平等な格差の縮小にプラス 7. イノベーションを促進 II. 5つの提案 1. 公的研究費による論文のオープンアクセスの義務化を! 2. 公費による紙媒体の科学雑誌の購読の制限を! 3. 出版後評価の積極的仕組みを! 4. 日本発の論文をアピールする仕組みを! 5. 報道時に論文URLの表示の義務化を! OA化についてのアンケートも行っておりますので、ぜひご協力ください。 著者らによる第91回日本生理学会大会での同テーマでのプレゼン「オープンアクセスを推進すべき7つの理由と5つの提案」の資料(スライド)もあわせてご参照ください。以下からダウンロードいただけます(外部サイト[包括脳プラットフォーム - XooNIps for CBSN]に移行します)。 ・Powerpoint スライド(20 MB)ダウンロード Sciencetalks でのタイアップ記事「日本はジャーナルのオープンアクセス化推進を戦略とすべし!」より、本記事の著者の一人、宮川と、科学技術・学術政策研究所(NISTEP)科学技術動向研究センターの林 和弘 上席研究官との対談の動画を転載します。Sciencetalksの記事もあわせてご覧下さい。 本文新しい科学技術上の発見・情報が素早く効率的に世界で共有され、それが新たな発見を促す。様々な発見が繋がって予期されなかったようなイノベーションを産み、それが人類の健康・福祉・幸福に貢献する。その貢献によって得られた利益がさらなる科学技術研究に投資され、そのサイクルが回っていく。 このサイクルの中で、科学技術研究に関する情報交換、研究者どうしのコミュニケーションの方法が最適化されることは極めて重要なことでしょう。このコミュニケーションの主要な手段として用いられてきたのが、紙媒体を持つ科学雑誌への論文発表という方法です。インターネットと電子媒体の普及によって、この状況は徐々にかわりつつあります。 スピード、コスト、情報量、再利用可能性、情報価値の重み付け。これらは、科学技術研究に関する情報交換が行われる上で決定的に重要な要素であるように思われます。紙媒体との比較において、電子媒体はこれらのどの要素においても圧倒的なアドバンテージを持っているはずです。また、電子媒体中心の論文出版においては、論文1コピーのコストが限りなくゼロに近く、出版までの初期コストしかかからないためオープンアクセス化が必然の流れとなるはずです。 しかしながら、意外にもこの変化のスピードはとてもゆっくりしたものであるように感じられます。この大きな原因の一つは、我々研究者や行政がOA化のメリットを明示的に認識していないということではないでしょうか。本ブログでは、研究者としての視点から「オープンアクセス化を推進すべき7つの理由」として電子化・OA化のアドバンテージを整理し、これを推進するための具体的な方策についていくつかの提案をします。さらOA化のマイナス面として指摘されがちな点についてQ&Aを設けてみました。ぜひ皆さまの忌憚のないご意見をお寄せいただけますと有難いです。なお、OAに関する世界の最新の動向や、より専門的な分析については、当該分野の研究者による論文や発表資料等をご参照ください[1, 2, 3])。 I. オープンアクセス化を推進すべき7つの理由 オープンアクセス化のメリットについて、改めて整理してみました。欠けている視点のご指摘など皆様からのご意見を歓迎いたします。 1. 部数が増えてもコストは増えない 電子媒体では、紙媒体の場合と違って、発行される論文の部数に比例してコストが増加する、ということはありません。それぞれの論文が出版されるまでの初期コストがほとんどを占め、PDF論文が10万回ダウンロードされた場合でも10回しかダウンロードされなかった場合でもかかるコストはほとんど変わりません。「科学技術の知見を世界中の人々にできるだけ広く速く安価に伝えること」を科学出版の目的として考えてみましょう。電子媒体による出版ではいったん論文を出版したらそれ以上はコストがかからないわけです。研究者にはたくさんの部数の論文を販売してそこから金銭的利益を得ようというモチベーションは基本的にはありませんし、現在の仕組みもそうはなっていません(部数が出て利益を得るのは著作権を有する出版社のみです;学会が利益を得る場合も海外ではありますが日本ではほとんどありません)。しかし研究者には成果をできるだけ広く普及させるというモチベーションはあり、成果の普及をどの程度達成するかが、研究費などが採択や人事に影響を与える、というのがビジネスモデルです。この研究者のモチベーションを考えると、論文出版までの実費的コストさえなんとかした暁には、あとはオープンアクセス化してしまうのが目的を達成するために最適な方法であるのは間違いないでしょう。電子論文の閲覧・ダウンロードを無料化すること、つまりオープンアクセス化するのはあまりにも当然のことであり、しない理由を考えつくほうが困難なのです。 しかし、実際にはそこに高い壁があり、現実にはいまだにオープンアクセスではない論文が総論文の半分以上を占めています[4]。なぜでしょう?紙媒体の雑誌が悪玉であると筆者らは考えます。 論文の電子版閲覧・ダウンロードに課金する雑誌のほとんどは紙媒体での出版も同時に維持する雑誌でしょう(そうでないオンラインジャーナルはNature Communicationsなどの一部の例外的な高インパクト雑誌くらいか?)。紙媒体がある雑誌では、なぜコストのかからない論文の電子版にペイウォールを設けてダウンロードに課金しなければいけないのでしょうか?それは、そうしないと紙媒体のものが大学図書館などで売れなくなってしまい、「紙媒体部門」の採算が採れなくなってしまう、あるいは、利益が上がらなくなってしまう、というのが最も大きな理由に違いありません。つまりほとんどの研究者が必要としていない「紙媒体部門」の延命のため本来はコストのかからない電子媒体に課金されてしまっているわけです。言い換えれば、ごく僅かな数の雑誌を手にとってパラパラ読みをしたいという研究者の贅沢な趣味のために、大多数の研究者と研究の原資を出している納税者の負担が強いられているという状況とも言えるでしょう。 2. しかるべき数・分量の論文を出版できる 紙媒体では「紙面の制約」という非常に困ったしばりがあります。 論文がリジェクトされる、という現在の科学出版の仕組みにおいて我々研究者が苦労させられる問題の多くの部分は、この「紙面の制約」に起因していますし、多くのリジェクトのメールでは「紙面の制約」が明示的に書いてあります。 語数制限で論文を短くさせられてしまう、ページチャージ・カラーチャージを取られる、などもこの「紙面の制約」が引き起こしている問題です。それぞれの研究でなされている実験・データの量は、千差万別であり、これらに一律のしばりがあるのはナンセンスなのですが、「紙面の制約」と言われるとそれは仕方がないと納得せざるを得ません。このことから、紙媒体を持つ雑誌では電子版がある場合でも紙面の制約にしばられてしまう、というよく考えるとおかしなことが生じているわけです。 紙面の制約によって、論文の採択率は低く抑えられることになります。さらに出版社も、ジャーナルのインパクトファクターを維持したり上昇させるために、掲載論文数を抑制的にコントロールしたいというモチベーションを持っています(インパクトファクターと論文の評価についてはI-5参照)。論文の採択率の低さは、投稿者に対するエディター・レフリーの優位性を圧倒的にしている大きな要因でしょう。査読の透明性は低く、投稿者はどんなに理不尽なことをされてもほとんどの場合、泣き寝入りするしかないのです。 電子ジャーナルでは「紙面の制約」がありません。電子媒体のみジャーナルとなることにより、論文を受理するか否かの決定は、純粋に科学的、技術的な観点からのクオリティによって判断されるようになるでしょう。少なくとも「紙面の制約」などという言い訳はきかなくなります。電子ジャーナルでは掲載する論文の数、論文の分量は、必要・十分で最適だと考えられる分量をジャーナルと著者がかなり自由に設定することができます。 そもそも「紙面の制約」がないのですから、論文のリジェクトをする理由は科学的、技術的な観点から最低限のルールを満たしているかどうか(統計の標準的な使い方がなされているか、主張がデータから導かられるものになっており言い過ぎでないかどうか、論文としての体裁がきちんと整っているかどうか、オリジナルの研究であるかどうか、動物実験や人を対象とする実験の倫理的問題はクリアしているかどうか、盗用やデータの不適切な加工などの不正がなされていないか、など)、という部分に限定されることになるのが当然でしょう。最低限のルールが満たされていないような場合は、それを満たすようにするためのリバイズのアドバイスを行うだけでいいはずです。出版費用の初期コストさえまかなうことができ、かつ情報の重要度を示す何らかの指標さえあれば、情報は世に出れば出るだけ良いので、リバイズのアドバイスはあるとしてもリジェクトする必要はほとんどの場合ないのです。 電子ジャーナルでもインパクト・ファクターを高くしたい場合があり、その場合は採択率を低くすることがあるではないか、というご指摘があるかもしれません。それは事実なのですが、同時に採択率を高く保つような工夫も可能です。上位ジャーナルでリジェクトされた論文について、別のジャーナルにエディター・レフリーと査読結果を丸ごと簡便に移行する方法があり、これはそのような工夫の一例です。著者の一人の宮川がセクションエディターを務めるBioMed CentralのMolecular Brain(Impact Factor: 4.20)という電子ジャーナルでは、最近、同じくBioMed Centralが発行するBMC Neuroscience(Impact Factor: 3.00)とBMC Research Note(Impact Factor: 1.39)との間で「ジャーナルカスケードシステム」の試験的運用を始めました。このシステムでは、上位のジャーナルでリジェクトされた論文について、下位のジャーナルがその基準を満たしていると判断すれば、(実質的に)新たな査読なしにアクセプトされます。Molecular Brainでは、掲載には、概念的な新しさやインパクトの強さが求められます。一方、BMC Neuroscienceでは、概念的な新しさやインパクトが必ずしもないと判断される場合でも、実験結果そのものが明快で新しければ受け入れられます。また、BMC Research Noteは実験や解析方法に問題がなければ単なる追試の報告でも掲載されます。Molecular Brainにリジェクトされた論文も、ジャーナルカスケードシステムによりBMC NeuroscienceかBMC Research Noteにおいて、Molecular Brainでの査読の内容や状況を踏まえた上で査読が行われて掲載が決定されます。 紙媒体の雑誌は、物理的なスペースも必要とする、ということも軽視できない問題です。図書館や研究室のスペースは有限であり、古いものは廃棄せざるを得ない場合があります。一方、電子媒体であればスペースの問題は全く存在しないと言えます。保存・通信できるデータ量も10年ほど前に比べると飛躍的に増え、ムービーや実験・調査のローデータも論文に加えることが可能になってきています。いわゆるビッグデータ解析や、論文横断的なデータの再解析の重要性も増してきています。ローデータや詳細プロトコルの公開は不正防止という観点でも強力な力を発揮するでしょう(STAP論文で調査が難航している大きな理由の一つはこれらがなかなか出てこないことです)。これらの意味でも紙媒体の論文というのがナンセンスになってきているように思われます。 大量の情報が出版されてしまうと情報が溢れすぎて何が重要かわからなくなる、という危険性もよく指摘されることです。しかし、その論文の重要性や価値については出版後でも前でもいいので別途表示すればいいだけでしょう(I-5参照)。「紙面の制約」という時代遅れの取るに足らない理由で、ジャーナルのエディターやレフリーが情報の重要性や価値の判断を拙速に進め、情報が世に出るのを遅らせてしまう現行の仕組みは明らかに世界の科学の進展を妨げています。 3. 公表までのスピードが上がる 電子媒体で物理的な印刷とその物理的送付の必要がないことが成果公表のスピードを速めることは言うまでもありません。ここでさらに指摘しておきたいのは、出版の敷居が圧倒的に低いため出版前の査読に必要とされていた時間を圧倒的に短縮できる可能性を秘めているという点です。現状の雑誌、特に高インパクト雑誌では、論文の全体的な質を高く保つため、必ずしも本質的でない補助的実験・解析を要求することが多々あります。これによって、研究の成果が世に出るまで1年や2年、場合によっては5年というような長い時間が余分にかかってしまうのは稀なことでは決してありません。 また、紙媒体であれば、一旦出版してしまうと、訂正を行うのが非常に困難で面倒です。ErrataやCorrigendaは可能ですが、敷居が非常に高く、多少のタイポやミスであればそのまま放置する、というのがほとんどではないでしょうか。 一方、電子媒体であれば、本質的な部分をまずできるだけ早く世に出してしまい、きめ細かい改訂作業は出版後に行えばいいという方法も成り立つでしょう。そもそもほとんどの場合、単一の研究発表の中でのエッセンス・本質的なデータというものはそれほど多いわけではありません。その僅かな部分を発表する場合でも、それの裏付けとなるコントロールデータ、補助的データはもとより、その研究が出てきた歴史的背景、研究のモチベーションの説明、得られた結果の解釈の可能性、今後の展開、応用の可能性などなど、必ずしも必要とはいえないような情報を付け加える必要があります。英文の文章もある程度の水準が要求され、英語を母国語としない日本人はこの点で不利でありハンデを背負っていると言えます。科学の世界では、スピードは非常に重要な要素です。2013年に刊行されたOAジャーナル、F1000 Researchでは、論文が投稿された時点で原稿をそのまま掲載し、レビューをレフリーの名前と共に公開で行うというシステムが採用されました。 Cell pressやPNASが採用しているCrossMarkのように最新改訂バージョンのトラックを簡便にできるような方法も既に考案されています。CrossMarkを適用すると、pdf版の論文およびジャーナルサイトのhtml版の論文に専用のリンクボタンが埋め込まれます。これをクリックするとその論文の更新状況の情報にダイレクトにアクセスすることができます[5]。このような手法を活用して、まず成果のキモとなるような本質的なデータを中心にざっくりと出版・公表してしまい、後で補助的データなどは付け足し、考察・イントロなどの文章を追加・推敲したバージョンアップをするというような方法も将来的にはありうるのではないでしょうか。そのような仕組みにより、研究成果の本質的な部分が世に出るまでの時間が圧倒的に短くなることは間違いないところだと思われます。また、この種の仕組みが普及すれば、ある論文の最新バージョンは、紙媒体では掲載されないわけですので、紙媒体の論文の存在意義はさらに低下すると考えられます。 4. スライドや教科書、一般書籍などで再利用しやすい 原著論文でのオリジナルなデータやオリジナルなアイデアというのは、科学上のコミュニケーションをする上での最も基本的なものであり、科学における通貨、科学における米(コメ)のような位置付けではないかと思います。公的な研究費を用いて生み出されたオリジナルなデータ・アイデアはスライドや教科書、各種書籍、Wikipediaを始めとする各種ウェブサイトなどで引用という形式をとりさえすれば自由に活用できるようになるのが望ましいでしょう。Creative Commonsのような形でのオープンアクセスが標準になることにより、科学的知見の普及が飛躍的になされやすくなるのは間違いありません。従来型の紙媒体の雑誌の多くではしかし、全ての著作権が出版社や雑誌の発行母体(学会)にあるという状況があります。論文に掲載されている内容を上記のような用途で再利用するためには、多くの場合、出版社から許諾をとる必要がある場合があります(しかるべき引用の方法さえ踏襲すれば許諾なしで利用できるという考え方もありますが)。論文のPDFファイルを自分のウェブサイトからダウンロードできるようにすることはもちろん、メールで他者に送付するだけでも、この著作権の侵害に当たる可能性すらあるというたいへん不思議なことになっています。きれいに整形された最終版ではなく、未整形の最終的な原稿であれば、機関リポジトリや各種ウェブサイトに掲載しても良い、ということになっている場合が多いわけですが、おかしな話ではあります。わざわざきれいなバージョンを労力と公的資金をかけてつくっているのですから。多少、追加の費用がかかっても、最終版のきれいに整形された論文を自由に配布できる、というのが正常なあり方でしょう。 また、購読型の学会誌では、学会が著作権を保持しているものもあります。あるOA出版社の方からお聞きした話では、こうした雑誌の中には、オープンアクセスによって著作権を著者が保持することに学会が抵抗感を示すという場合が少なからずあるそうです。学会誌は学会のものであるからそこに掲載される内容も学会に属するものだという考えがあるほか、転載料や図表等の使用料から収益を得たいというのがその理由であるようです。その種の収入の額の小ささや世界的なオープンアクセスのトレンドを考えると、こうした収益が今後拡大していくとは思えません。 そもそも、ある研究論文が誕生する際には、誰がどのように貢献しているでしょうか?そして、それによって生まれる権利は誰に帰属されるべきでしょうか?本来は研究を行い論文を執筆した研究者がその発見に最も貢献し権利の帰属がなされるべき対象でしょう。その範囲をもし広げるとしても、せいぜいその研究者の所属機関、研究に出資した人・機関くらいまでではないでしょうか。出版社はその成果を広めることにそれなりの貢献しているとはいえ、それはあくまでも補助的な役割にすぎず、全著作権を所有する、というのは現代の価値観から見るとほとんどあり得ないことではないでしょうか。著作権の出版社への譲渡というのは、科学雑誌の歴史のなかで受け継がれている古いしきたりのようなものかもしれません。科学の黎明期には、印刷・出版は容易ではないことであり、一方、科学的成果の重みは相対的にそれほどのものではなかったのかもしれません。当時は印刷・出版を実現させることに大きな価値があり、その代償として著作権の出版社への譲渡があったのでしょう。情報の公開・普及方法が高度に発達し、極めて安価で容易に実現される現在ではこの古いしきたりは全く意味を失っているだけでなく、科学の進歩を阻害している要因であるといえるでしょう。 5. 情報価値の重み付けがしやすい 電子媒体の普及によって出版の敷居が下がると、当然、世の中に出る論文の数・量が増加します。膨大な情報の海の中からどのようにして自分にとって価値の高い有用な情報を選別して取り入れるか、というのはすでに現状でも既に大きな問題となりつつあります。従来型の仕組みでは、2〜4名程度のごく少数のレフリーとエディターが論文の価値を判定し、世に出すか否かの判断を行うことが論文の情報価値の基本データになるものと多くの研究者に理解されています。つまりレフリーとエディターは雑誌の「格」のようなものやインパクトファクターを漠然と想定し、その雑誌に見合うだけの価値がその論文にあるかどうかを主観的に判断し、その判断がそれぞれの論文の情報の価値や重要度を示すものとして実際上、かなり用いられていることになります。私たちは、ごく少数の専門家の価値判断を受け入れて情報の選別・受け入れを行っているわけです。NatureやScienceの論文は価値が高いと一般的に考えられており、そのような論文を発表していれば、研究費も採択されやすいし人事でも有利なこともあきらかです。 一方、掲載雑誌のインパクトファクターや、「ごく少数のレフリーとエディターの判断」が個々の論文の価値を決めるものでないことは明らかです。高インパクト雑誌に掲載されていても再現性のとれない論文、引用がほとんどなされない論文はたくさんありますし、インパクトがそれほど高くない雑誌に掲載されている論文でも頻繁に引用されたり、果てはノーベル賞受賞の理由になったりすることすらあるわけです。科学論文の価値は多くの研究者による再現性の検証や利用などを経て長い時間をかけて定まってくるという側面が強いはずです。現在最もポピュラーな情報の重み付け方法(雑誌インパクトに頼る方法)は最適なものとは言えません。もっとも、インパクトファクターはジャーナルそのものを評価する指標としては有用です。また、論文の被引用数がピークを迎えるのは発表から2年目前後の期間で、発表直後はあまり引用されないので[6]、論文発表直後の評価の間接的指標としても雑誌インパクトファクターは有効でしょう。 電子論文ですと閲覧数、ダウンロード数などの定量化が行いやすい、ということがあります。Social Mediaでの注目度を指標としたAltmetricsのような今までなかった指標もできてきています[7]。Altmetricsは、WEB上での反応を指標としているため、論文のインパクト(影響度)をほぼリアルタイムで測ることが可能です。また、多くの場合、電子論文では、雑誌のウェブサイト上やPubMed上(PubMed [...]
続きを読む
2014年4月14日
「ガチ議論」シンポ・テープ起こし (4/6)
2014.04.08 トピックス

前のページ – 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 – 次のページ 宮野 よっし、分かりました。ありがとうございます。なるほど。そしたらいったん仕切り直しますけれども、おそらく…、またここでだらだらしゃべりません。一つは、理念の不在という問題が一つ。つまり、僕らどっち向くの、っていう話ね。あ、ごめんね。宮川先生、しゃべろうとしていた? 宮川 Tweetを読み、一部…。 宮野 流し読み、僕これ言った後流して読むよ。まず一つは理念の不在。方向性っていうことね。僕らどうしたいのって話。もう一つは方法論の話がなされました。で、割と高所、高いとこからの話だなとか、上ついているなつかあったけど、僕はやっぱこれ、すごい大事だと思うんですよ。密接に関係していますからね。それと。やっぱりこれまでむしろ個別論しかしてこなかった結果が、今あるとも思っています。だからいいなと思っています。後もう一つは、安宅さんがいうような健全なバトルフィールドって思うんですよ。そのバトルフィールドの関係を、原山さん、おっしゃっていたような問題。ただね、ここで皆さんと、皆さんのtweetとも接続するんですけれども、研究で評価されていない。そこがやっぱ一つボトルネックかなと思った。研究者が研究で評価されていないような気がする。たとえば雑用が多いとかさあ。その、競争的資金とかね。ピュアに健全なバトルフィールドって書いたけど。で、つまりこのマップの上の議論っていうのが、いまなされたのかなあ、と思いました。なんとなくね。位置づけ的に。そういった、なんとなく言った後にtweetだーっと見ますけれども、確かに、そうですねえ、どう言ったらいいやろ。この、思った以上に内容も拡散しているんでねえ。皆さん「もっといろいろ」とか言わはるけど結構難しいですよ。どうしましょう?流し読みすら戸惑うぐらいの量なんですけれども。そうでしょう。どうする?たとえば、あえてまだ議論、ここで話してないというという視点でトピックを上げるとするならばその人材育成の話ですかね。あと、具体論も話して、っていうはなしもありましたけれどもね。なんですかね、あと?皆さんも見られているんですよね。コミュニティーのことを考えている人ってどれぐらいいるのかなあとか、そういう話? 鈴木 いい、口はさんで?研究者が研究で評価されていないって、本当にそうですかねえ。雑用が多いのは、予算が足らないので、リサーチアシスタントだとか、administration stuffが雇えないだけの話であって、研究は研究で評価されていると思いますよ。僕は。比較的。でね、これはちゃんと確認しておきたいんだけど、今の現状の特に、その生物学とかですね、理系の数字はどうなのかと。これは一つの物差しではあるけれども、論文のcitationで言えばですね、東大のPhysicsは2番だし、生化学も4番だし、京都のChemistryは4位だし、東北のMaterialsは5位だし、ということで、全然、competitiveなんですよ。我々は。 安宅 そう思います。 鈴木 ダメなのは文科系で、東大の社会科学は283位ですよ。ええ。だから、まずそこは今はオッケーだと。ただ、ほっとくと、後5年10年しちゃうと安宅さんが言うようにプレーヤーが誰もいなくなった、という、だからそこをどう維持しますか、というふうなことにしておかないと、 安宅 すずかんさんのおっしゃる通りで、最初に少し言ったんですけれども、そもそも悪くないんですね。この国の研究レベルって。だから、これでいいんじゃないかっていうですね。この38、9℃でやりましょうと。という僕のさっきの話というのも、答え、っちゃあ答えなんですよ。なぜかっていうとアウトプットが出ているんで。それだけのことですね。だから、どうなんですか、ということを聞きたいと。私はむしろ。皆さんとして。そんな悪くないじゃないですか。かなり誇らしい国ですよ。この状態って。僕、別にアメリカ行っていて恥ずかしい思いしたことないですし…。 宮川 それが違うという話が出てきていて、「あまりにも異常な論文数のカーブ」っていう資料(鈴鹿医療科学大学学長 豊田長康氏 資料)あります?この手元の資料の29番なんですけれども。あの30番(「人口あたりの高注目度論文数は先進国で最低!!」, 鈴鹿医療科学大学学長 豊田長康氏 資料)、そちら(サブスクリーン)に出せます?日本だけ論文数がどんどん減っていて、かつ、高注目度論文数も、減ってるんですね。研究費は、総額はどうも伸びてるようなんだけれども、生産性のアウトプットは減っているということがあって、これは、僕の実感としても、すごいあるというか、研究費は意外に結構あってもですね、それがちゃんと活かせるような仕組みになってなくて、なんかやたらと雑用が多くて忙しいし、研究費は年度末までに使い切らなければいけないし、ちゃんと増えている研究費を活用できない仕組みになっちゃっていると思うんですよね。 鈴木 ちょっと今かなり誤解があると思うんだけれども、物事にはインプットとアウトプット、そのratioがパフォーマンスなんですよ。で、アウトプットは減っている、その理由は、最大の理由はインプットが増えてないからですよ。それ絶対misleading。で、日本のパフォーマンスは世界一良い。インプット分のアウトプットで言うと。アメリカはアウトプットが良いのは、アメリカはパフォーマンス、決して良くない。なぜならばインプットが膨大にあるからあのアウトプットが出ている、んですよ。そこは。だから日本はね、こんなに安い研究費でこんなにスタッフつけてくれないにも関わらず、世界3番とか4番のアウトプットを出しているから、極めてパフォーマンスは良い。燃費はすごく良いんですよね。だからそこは良いんだけど、インプットが、ガソリンがゼロになっちゃったら走らないでしょ、っていう話で、だから、こんだけ燃費が良いんだから、ガソリン少なくとも維持してよねと。できれば、この良い燃費のところにあとガソリン2倍にすれば、アウトプット2倍出しますよ、ということなんですよ。だから日本だけですからこの20年間科学研究費増やしていないのは。もう中国とかなんとか4倍も増やしているし、アメリカだって2倍にしているんだから、そこの問題にフォーカスしなくちゃいけなくて、その、中の使い方なんて、概ねうまくいっている。いろいろあるかもしれないけれども。それは社会の理解とサポートを得られていないのでインプットが増えないんです、っていうことにちゃんとまず我々が正確な問題提起をしないと、だめなんじゃないでしょうか。 宮川 いや、そこのところは全くおっしゃる通りで、いやもう本当にインプットを倍にぜひしていただきたいし、本当に我々もしたいんですけれども、どうすればそうなるのかっていうのが…、インプットが倍だったら雑用の問題とかも…。 鈴木 解決しますよ。 宮川 するかもしれないですね。いろいろ解決しますね。はい。 原山 インプットと、経済学でいえば、大きくいうとcapitalとlaborなんです。それにtechnologyが入るわけなんで、今予算の話にフォーカスされていますけれども、それだけか。この、研究開発っていうのはlabor intensiveであって、しかも質の高いものが入れば入るほど効果が高くなるという話です。そこでさっきのアメリカとの比較、もちろん金銭的なウェイトとかいうものはかなり日本と比較にならないんですけれども、もう一つ、研究者層の質というものを考えると、量だけじゃなくてね、人数だけじゃなくて。先ほどおっしゃっていたdiversityの話がかなり効いてくるわけで、もちろんそのdiversity、いろんな人をまとめれば良いっていう話じゃなくて、もともと自分の確固たる物を持っている人を、分野が違っている人も集めながら、っていう色んな最前線にいけばいくほど、面白い組み合わせでもってチャレンジングなことをやっているって、それが背景にあるが故に、高くなっているし、それともうアメリカだって相当危機感持ってやっているわけですよ。アメリカの政府の人に聞くと、もう自分の今の状況じゃあ全く不十分だって言っているわけですね。政府の人たちが言っていると。何かっていうと、他の国も追いかけてきていてその中でこれまで自分の強みだったとこが完全に強みとしてキープできるかっていうその不安感があるわけ。逆に日本のことを考えれば、尚更のこと、質っていうものをどのように担保したら良いか。その色んな今の悪循環ってありましたよね、こん中で。逆にリバースして良い方の循環にまだどっかで進むそのスイッチ入れなくちゃいけないし、どっからスイッチを入れれば一番効果的か。その大学と企業体との違いっていうのは企業っていうのはある種の一つのindicatorでまとめられる目標を設定できるんだけれども、大学の場合multipleなんですよ。そのvectorで考えなくてはいけない。アウトプットが。研究成果であり人材育成でありその他諸々のファクターっていうのを背負いながらやっているわけですから、非常に苦しい、難しい、経営しなくちゃいけないわけ。それを理解した上でもって、大学に対してプレッシャーかけなくちゃいけないし、であるがゆえに、大学のトップの方はそれだけの思い、企業のトップより逆に難しい経営しなくちゃいけない状況にあって、なおその中にいて、大学の教授上がりの人がなるから、申し訳ないけどプロフェッショナルなマネージメントができない、できていないっていうのが現状なんですね。いかにそういう人を育てていくか、っていうかやはり若い人材が、研究者であり、同時にマネジメントも少しコミットする、それはその自分の大学に対する社会貢献ですね。それも少しずつやりながら、ま、そんなこと言うとまた尚更時間がなくなるんじゃないかって言われるんですけれども、もう一つは、私スイスに長いこと行ったんですけれども、あそこはイノベーションの、色んな指標からいくと、いつもトップの国なんですよ。人口もまあそんなに多くないし、多様性って意味ではもう必然的に多様なんだけれども、勤務時間考えると、大体朝早く来るけれども、大体夕方にはみんな帰っているわけですね。研究者。うちの主人なんか、土日に大学行って、お前何してるんだ、って馬鹿にされてたわけですよ。効率が悪いから土日にするんじゃないか、と言われて。そういうふうな形をしながらもcompetitiveであれる。研究環境があるわけですね。それはもちろん自分で全部やらなくていいからで、役割分担があって、プロフェッショナルなテクニシャンがいて、そういう事務のプロフェッショナルがいるわけですよ。それは一人一人の個人についているのではなくて、色々な、研究科とか、レベルでついてる。いわゆる効率化っていうのが良い意味で効率化なされている。でもそれしないと、単純に、どこにしわ寄せがくるかっていうと、若手の研究者に行っている。 宮野 よし、分かった。おっしゃる通り。で、ネットでも…。 宮川 そうそう。ネットで、「効率がいいのは業界全体がブラック体質だから」とか。 宮野 そう、そうなんですよ。そこに共感するのいっぱいあるけども、例えば今、やっぱ配分の問題って大事ですね。文科省からも是非言ってほしい。苦い顔してるけど。大学も削れるとこいっぱい削れるでしょ、とか。それこそ原山さんおっしゃったような大学の経営の問題とかね。これもあったよ。今増えても、やっぱり雑用増えるだけちゃう、みたいな。それこそやっぱり、単に、もちろん皆さん考えておられるように、単に何かをなんかしたらなんか変わるっていう問題じゃないから、ちゃんと一斉に考えないといけない。はい、どうぞ。たとえば…、審議官。 川上 だからですね、一番最初から言っているんですけれども、2倍にしてくれって、実現しないですよ。だって財政がこれだけ厳しい状況にある。だからさっきから言っているように、11足したいんだったら10引くっていう議論をやってかないと実現しないんです。だから、宮川さんの研究費を2倍にする、ことはできます。だけど、別の人の研究費をゼロにすることになる。そういうことだったらできるわけですね。皆さん方の研究費全部を倍にしてくれと、それは叶わないことなんですよね。現実的な議論をすべきなんです。 宮川 僕の研究費を2倍にしていただくのは良くて、で、その後なんですけど、異常にいっぱいありすぎて、もう使い切れないってとこから、引いていただきたい。他の誰かのをゼロにして僕にくれるっていうのは、ちょっと…。 宮野 配分の問題ね。 宮川 すごいもう使い切れなくて、みたいなの。年度末に使い切るってとこから持ってくるっていうのが良いのでは…。 宮野 そう。その通りだ。だから単発にこうポンってやっても、解決しないよね、ってそういう話ね。 川上 まずその、年度末問題っていうのはまたちょっと別の問題だから。置いといた方が良いと思うんですね。もし年度末問題をやるんだったらまたそれはそれで良いんですけれどもね。今、もう年度末に使い切らなきゃいけないなんてことを求めているつもりは全然ないんですよ。それは使い切ってゼロにした方が会計はやりやすいから、現場でそういうことを求める人はいるかもしれませんけれども、そんなことに従う必要はないです。本当に研究の進度に合わせてお金を使ってくれればいいです。それでそれは残してもらえばちゃんと来年度使えるようになっているし、成果が上がれば、科研費の場合は違うかもしれませんけれどもね、私はJSTに3年間いて理事やっていましたんで、JSTのCRESTとかそういうものでいけば、成果があったらちゃんと増やすし、成果が上がらなければ減らすと。いうことをちゃんとやりますから、思い切って使えるものを使うべき時に使っていただければ良いと思います。そういうものだと思っています。 宮野 そんときに、例えばすっごい儲かっている人、儲かっているというか取っている人から分配する時に、それこそ安宅さんのおっしゃる理念がいるんです。どういう研究がいいの、っていう話です。それはやっぱり僕らどうなりたいの、っていうのが定まっていないと、当然評価できませんよね。誰が良いとかどうかって。しかも難しいのは研究なんてなかなか評価できないってとこですよ。やっぱし。よし。静かになったからいったんここで、休憩します?(休憩はもう良いような気がします)あ、やっぱり。海外、日本人の話を、っていうことなんですけれども。海外日本人ってなんだ。海外で研究している日本人の研究者の話。人材育成っていうのは教育って意味なのかなあ、それとも研究者のっていみなのかなあ。人材育成って。多少ぶつっと切られた感がありますけどどうしよう。 宮野 はい、じゃあちょっとお願いします。 佐々木 ありがとうございます。今ちょうど話題になった、その、留学においての、我々のパフォーマンスを、いかに高めていくのか。ちょっとお時間頂いて、お話しさせていただきたいと思います。我々は、海外日本人研究者ネットワークUJAを立ち上げました。これは、日本、そして全世界の日本人研究者がさらにお互いを高め合う、史上初のネットワーキング、世界を結ぶ、プラットフォームです。私は、アメリカの大学でプロフェッサーシップを取り、自分自身の研究室を主催しています。現在、アメリカのポジション一つに対し、約300名から500名のアプリカント、応募者がいます。ジョブハントは激戦です。私の所属しているボストン「いざよい(の夕べ勉強)会」は100名のコミュニティーですが、数多くのメンバーがアメリカで独立し、活躍しています。このような、アメリカで成功した先輩方と知り合い、その経験談や情報を共有させていただくことにより私の道は大きく開きました。海外では強いネットワークを持つこと自身、それが我々自身の大きな力となります。こうしたネットワークを世界規模で広げ、そして、個々人の留学のパフォーマンスを高め、日本のサイエンスを加速し、日本が世界のサイエンスを牽引していく未来へ貢献したい。そうした思いから海外日本人研究者ネットワークは生まれました。世界各地には日本人研究者が集まるコミュニティーがたくさん存在しています。現在、次々に、コミュニティーの方々が参加していただいています。そして大事なのはこのコミュニティーを結ぶ、というのは、コミュニティー同士ではなくて、我々個々人と世界を結ぶことです。我々、そのために、システム作りに取り組んでいます。UJAには、全世界どこにいても、今この瞬間も参加することができます。ぜひ、我々のホームページを訪ねてみてください。そしてUJAを立ち上げるにあたって、我々はまず、日本人研究者がどれくらいの数海外に出ているのか。そして、どのような思いを持っているのか。知りたいと思いました。そして大規模アンケートを実施しました。多くの意見では、まず留学して、そのあとどうすれば良いかわからない。また、留学にあたって、どのように生活をセットアップして良いのか分からない。電話はどうやって引くんだ?子供の学校はどこが良いのか?家を決めること。まずライフラインから、我々の留学生活の第一日目は始まります。そして多くの方々は、海外日本人とのつながりを求めています。我々はこの問題に取り組み、解決します。そうすることで、まず、留学する際の不安と負担を軽減し、より多くの方々がすぐに留学していける。そして、キャリアパスを整備することによって、日本への、優秀な方々がより多くの方が帰り、また世界の舞台へ打って出るようなシステムを作り、この結果、研究留学の最大の効果、そして国内外の研究者の交流を高めたい。そして、日本の国際的なプレゼンスとイニシアチブを強化したいと考えています。以上です。ありがとうございます。 宮野 ありがとうございます。 分かった。インプットとアウトプットの話のところで、Tweetであと拾いたいなと思っていたのは、やっぱりインプットを増やして、cで掲載されるような論文を出すことが価値なのか、企業の競争力を高めるタネを出すのが価値なのか、それをやっぱり決めないと話できないよね、っていうまさにこれ、理念の話ですよね。僕らはどっち行くのか。これ、1パネラーとして言うとするならば、大事なところで、現在の大学論というか傾向でいうと、それこそ文科省の答申であったように個性輝く大学とかいったように、各大学で考えてくださいみたいな方向になっていますよね…、というフリで誰かに頼むという…。 鈴木 各大学っていうか各個人で考えてくださいっていうことでしょう。そんなものを国がね、じゃあ企業でいきますとかね、Nature、Scienceですと、Nature、Scienceにすら載らない学術研究だって大事なものはいっぱいあるわけで、それがまさにポートフォリオなんですよ。その、どっちですか、その理念が決まらなければ次の議論にいけませんといっている限り、この議論は100年経っても200年経っても終わりませんから、次の議論にいきません。それは、両方大事ですよね、っていう議論しかなくて、それぞれの、大事だと思っている人が、社会から、もう同じことしか言わないけれど、どれだけソーシャルリソース、社会の応援を、応援っていうのはいろんな応援がありますよ、っていうことを取ってくるかという話です。だから僕が今日ずっと言いたかったことはね、今の、海外留学生ネットワーク、こういう具体的なプロジェクトをどんどんどんどんやりましょうっていうことなんですよ。うん。その方がよっぽど有益だと。で、もちろんやりながらね、ここが足らない、あそこが足らないっていったら、応援すると。 宮川 こういう具体的プロジェクトが、下からこう上がってくると思うんですね。海外の方から。こういうのが上がってきた時にどこに持って行ったら良いかよく分からないんです。文科省に持って行けば良いのか学会に持って行けば良いのか、大学に持って行けば良いのか、そういうのが全然分からないわけなんですね。で、こちらでご発表して、なんでここでこんな発表が出るんだみたいなことになっちゃうと思うんです。 鈴木 それは簡単です。まずコミュニティーの中でできることは全部やっておられますよね。まず、近いところに聞いてですね、なおできないことはその先なんです。文部省に頼むことは、予算に関わることと法律に関わること、この二つです。政府がやらなければいけないことは。それ以外のことは自分たちでやってください。 川上 全くその通り。どこに持って行ったら良いかって、何が必要なのかって思ったんですよね。今のコミュニティー作ったんだけれども、予算、お金がいるんだと、だったらそれは言ってきてくれれば、 宮川 それは文科省にお願いすれば良いんですか? 川上 だからその、うちなのか、うちでできなければ外務省なのか、それは分かりませんけれどもね。それは考えますよ。ですけど、ほんとおっしゃる通り。お墨付き、例えば文科省のお墨付きがなければ動けないというようなことは全然ないですから、まさにインターネット空間でこういうことを展開しておられるんだとおもうんですよね。 宮川 たぶんこういうのを下からどんどん出していく。この種のことですね。色々。単年度予算のことにせよ、いろいろな今日お示しした意見、色々あるのを、あの種のことをですね、ネットとかで盛り上げて、それを施策みたいなものに結びつけるルートみたいなものが欲しいんですよね、ルート的なものが。どこに持って行けば良いか分からないので、窓口なり、仕組みなり、そういったものがないのかなと。 鈴木 少なくともですね、研究担当理事っていうのは各大学に全ているはずです。その人は、所属している教授の絶対あの…、っていうかだから学部長に聞けば誰がその人であるかっていうことは分かるわけだし、そしてそういう人たちは常日頃毎日のように川上さんのところに行って、あれしろとかこれしろとか言っているわけなんで、このチャネルにつなぐだけの話なんですよ。あるいはね、文部科学省の審議会の委員、見てください。かならずここにいる大学の先生が入っていますから。そこにメール一発してください。 宮川 多分その流れが今の流れだと思うんですね。偉い先生方ですね。大学の学長先生とか学部長先生とか審議会の先生方がいらっしゃって、そういうところを通じて文科省なりどこなりに持って行くっていう、この流れがいいのかという部分があると…。 鈴木 使えるものは全部使うんですよそんなもん。で、ダイレクトに川上さんと名刺交換すれば良いわけだし。 宮川 単年度予算のときにどうしたかと、事業仕分けの時に、単年度予算制度が非常にまずくて、非常にお金がむだになっているということを、我々ネット、神経科学者SNSっていうのでネットでそういう意見をまとめて、どこに持って行けば良いんだろうかということで困って、一応日本学術会議と、総合科学技術会議、のほうに提言を出したんですね。両方宛に。日本学術会議の方では、一応その我々の原稿をですね、日本学術会議の当時の会長の先生にご覧頂いて、一応文面とかも直してですね、なんとかしようとしたんだけれどもなんか、結局、取り上げられなかった。総合科学技術会議の方は、それをサポートしてくださる先生がいて、この場にも実はその先生がいらっしゃるんですけれども、その方が、その先生が総合科学技術会議に持って行っていただいて、そこでプレゼンをさせていただいて、それで当時の文部科学大臣の川端さんとか、当時の副大臣のすずかんさんとかに、それでちょっと、ちょっと実現したと。 鈴木 それはね、事実としてあんまり正確じゃない。それももちろん大事なルートだったけど、要するに僕らはメール見ていましたから。私自身も、研究者仲間から、毎日、しょっちゅう。私自身も年度末問題については悩んでいたこともあるし、僕らの友達はそんなこと毎日言っているわけですよ。そんな仰々しいルートでものが動いていると思っていたら大間違いで、あの時ね、なかなか科研費増やすの難しいなと。あの時は運営費交付金のV字回復をやろうとしていたから、それじゃあ予算制度改革療法っていうのを要するにやろうという話を私がしたんですよ。それで、このテーマでなんか面白いことをやっている人知らないかと言ったら、文部科学省の人はみんないっぱい知っていましたよ。こういうサイトがあります、こういうサイトがあります、こういうサイトでこういう議論をしています。その中で最も良い議論をしているのは宮川先生です、とこういうふうになって、だから文科省の役人は全然馬鹿じゃないので、ネットでどういう議論をしているのかなんていうのは全部チェックしています。まあ、全部とはいわないけど、検索エンジンの使い方はみんな知っているので。 斉藤 まさにその情報を鈴木副大臣にご紹介した立場だった者なんですけれども、誰に相談するかというのはとても重要だと思っていまして、さっき宮川さんがおっしゃっていたような、先ほどの取り組みのように、広く視野を持って、それこそビジョンがあって、前に進める素晴らしいものが上がってきて、幅広い視野を持った人にいってうまくいった場合は良いと思うんですけれども、さっきまさにご批判されていた、自分のところに使い切れないほどお金がくるみたいなそういうのもたぶん全く同じルートでつながって、実現しちゃっているというのもそうだと思うんですよね。そうならないようにするためにはもちろん持っていただく方の中身も、ちゃんと俯瞰的に見た、良いビジョンの詰まったものである必要があるし、受け取る側の人も、我々役所の方も、人によって、ポジションによって、いろいろ違いがあるので、そこがうまくつながった時にうまくいくのかなという感じもしています。まさにさっきご紹介いただいた、若手研究者と会っていろいろ進めたいっていう時も、ちょうどそういう問題意識を持った時にご相談できましたし、そういうものを進めて頂ける方が上にいたんでうまく進んだという。ちょうどその時に宮川さんや、宮野さんや、そういう活動されている方とちょうどうまくつながったっていうのもあるのかなと思います。 宮野 それやっぱ一つポイントだと思うんですよ。今、要は、少なくとも既存のシステムでどう変わったかの話ですよね。で、もっと言うと、今そんだけ情報あったのに、なぜ他のことは変わらないのっていう問いも生まれますよね。 原山 今のそのいろんなやり取りっていうのは、現場の方達の思っていること、意見っていうのをどういうふうな形でもって施策決定するところに意見を上げていくかっていう議論だと思うんですが、色んなチャンネルがあるっていうことは事実であって、でも、個別に知っている人を頼っていくチャンネルっていうのは、まあ、正面切っての話じゃなくて、ある種のlobbying的な話。また、その頼られた人は、ある種のパワーゲームの中で優位的なところに立つわけだから、あまり健全、健全じゃあないわけなんですね。そういうルートとかもありながらも、もっとダイレクトに出せる、誰でもが出せる場っていうのが欲しいなあっていうのが、たぶんここでの議論だと思うし、それはできると思うんですよ。そんな難しいことじゃない。もう一つこういう議論するっていうのは私の世代であれば、インターネットがない、通常こんなふうに使っていない時代であれば非常に大事だし、だからそれもフォーマルに作るのと、今本当に、今の議論もそうですけれどもTwitterなりなんでも出すことができるし、さきほど鈴木さんがおっしゃったように、こっちだって見ることもできるわけなんですね。正面切ってじゃないけれども。そういうチャンネルが増えてくると一つプラスな効果だけども、もう一つダイレクトのが欲しいのが一つあると思う。それからさきほどの海外の話、ひとつ戻させていただくんですが、また、スイスのケースで恐縮なんですけれども、スイスも、外からも人来るけれども、スイスからもどんどんどんどん人が出ているんですね。出た時にやはりちょっと不安になるところがやはり日本とスイス人近いところがあって、どうやったら戻れるのか。まあ、Destinationとしてはやはりアメリカなんですけれども、優秀な人がアメリカに行って、残る人もいれば、戻るってことも一つのオプションとして思いたい時に、やはり情報がアメリカに行っちゃうと欠けると。どういうオファーがあるのかなかなか掴めないっていうんで、その研究者達のリクエストをベースにして、スイスの一つの役に立った人なんですけれども非常に方便してあちこち歩き回ってお金を集めて、アメリカのボストンにスイスハウスっていうのを作ったんですよ。それは公的な方がやったんですけれども、インセンティブ取ったんだけれども、fundingはプライベートなところから持ってきたと。それが情報を共有するところ。そこに行けばスイスの国内でのオファーのリストもあるし、紹介もしてくれると。逆にそこの場っていうのはスイスのショーケースみたいな形でもってスイスの研究を省アップするところをボストンの中に作った。それが数年もうたって非常にうまくいっているんですけれども、今の所長の人に話を聞くと、100%自力で回していると。というやり方なんですね。ですからビジネスモデルっていうのはやはりそれぞれ考えなくちゃいけないし、sustainableに持っていくためには、相当知恵を絞らなくちゃいけない、という話です。そしてやり方色々あると思うんですけれども、必ずしも政府がかまないとうまくいかないというロジックじゃないと思います。 鈴木 あのね、lobbyingは不健全だっていう認識は間違えた方が良い、絶対間違えた方が良い。それはね、アメリカだってlobbyingの嵐だし、もっと、日本学術会議が取り上げてくれなかったら、なんでもっとちゃんとlobbyingをやらないんですか、っていうことなんですよ。それからフォーマルってどういう意味で使っているかっていうことなんだけど、僕はフォーマルに作るのはもうenoughだと思います。たとえば、分子生物学会が、自主的に、そういう年次提言をまとめていく、あるいはそれをいろんな物理学会、あるいは数学会、あるいは化学会と組んで、そういうのをどんどんどんどんあげていくというのをフォーマルと言っているのであればそれはそれで賛成なんだけど、それは政策の側からすれば別にフォーマルでなくて学会の自治の話なんですね。それをまたやれって法律で決めるのは僕は絶対反対。それは学会の自治でどんどんやってください。そういうことについて僕は全面的に、一学者の端くれとして、めちゃくちゃ応援します。だけど、元文部科学副大臣としては応援しません。それは、気持ちが悪いから。だけどそういうことをやって、且つね、今度、なんで学術会議が、学術会議は完全にシステムの話ですね。学術会議っていうのは法律上、提言、提案権ていうものを持っていて、そのことは非常に重く受け止められるっていう話があります。それから、もう一つは、分子生物学会がですね、年次の大会で、ある提案をまとめて、その分子生物学会長が斉藤さんなり川上さんにアポイントを取ったら絶対に会えますよ。それは。分子生物学会規模のものになれば。だって現に今日、東京からわざわざ来てるわけだし、言えば良いわけで。僕はなぜそういうこと言っているかっていうと、結局システムを置く畳句を重ねれば重ねるほど、ある目的にとってはそのことは良いことなんだけど、別の目的にとってはそれは足かせになるんです。システムは複雑になればなるほどそのための学習コストと、その運用コストが上がるので、そこはやっぱりシステムっていうのは、ほどほどに整備をとどめておかなければならなくて、むしろそれを運用する人材、あるいはそのネットワーク、ヒューマンネットワークを健全に作る。あるいは健全に育成する。そしてそういう能力のある人を分子生物学会長に選ぶのか、あるいは学術会議の会長に選ぶのか、という、そういう人事の話というのは実は大事だっていうことを申し上げたい。 前のページ – [...]
続きを読む
2014年4月8日