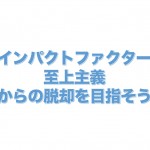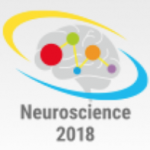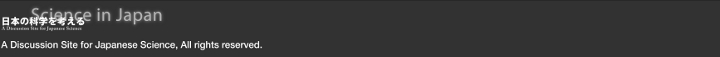トピックス
【報告】雇止め問題と博士人材の課題について、盛山正仁文部科学大臣との意見交換を行いました
2024.10.21 HOME

2024年9月25日、盛山正仁文部科学大臣を訪問し、大学・研究機関での雇止め問題と、博士人材活躍に向けた課題と提案について、研究者の意見を直接お伝えする機会を得ました。今の博士をめぐる研究現場のリアルな現状について、研究関係者へのアンケートに基づいた情報を共有し、日本の社会で博士が安心して研究関連活動に集中し、活躍できるようにするための意見交換を行いました。 会合の参加者は、日本神経科学学会・前会長、日本学術会議・神経科学分科会・委員長の柚﨑通介教授(慶應義塾大学)、日本脳科学関連学会連合・代表の高橋良輔教授(京都大学)、SciREX事業で博士の安定性と流動性を両立したキャリアパスの仕組みを提案する宮川剛教授(藤田医科大学)、自らが博士課程の大学院生である三田剛嗣氏(慶應義塾大学・博士課程/生化学若手の会有志)と盛山宗太郎氏(慶應義塾大学病院 精神・神経科学教室)の5名でした。 草の根アンケートが映し出す博士人材の課題 まず最初に三田氏より生化学若手の会有志が実施した、「博士人材活躍プラン」に関連する研究者草の根アンケートの結果を大臣にご報告しました。アンケートには博士課程進学者への支援の拡充を求める声や、博士号取得後の企業就職やアカデミアのポスト不足への不安を訴える声などを紹介し、産業界へのキャリアの出口戦略に加え、アカデミアでのキャリアパスの整備の重要性をお伝えしました。 アンケートの詳細はこちらから。 「越境研究員制度」の提案 続いて宮川教授が、SciREX事業の一環で取り組んでいる「越境研究員制度」についてご説明しました。宮川教授らが提唱するこの制度では、博士号取得者を大学コンソーシアムや企業、資金配分機関等で終身雇用し、大学・研究機関・企業等が競争的資金や自己資金などの多様な予算を人件費として活用して研究関係者を受け入れることで職の安定性と流動性を同時に高めることを目指しています。博士人材の多様なキャリアパスを支援し、研究者がアカデミアと産業界の間で柔軟にキャリアを選択できる環境を提供することで、社会全体に貢献できる新しい制度と博士像を提案しました。 越境研究員制度の内容はこちらの記事から。 雇い止め問題と労働環境の課題 最後に、柚﨑教授と高橋教授が「大学・研究機関での雇い止め問題」に関する研究者関係者へのアンケートの結果をご報告しました。この調査は任期付きの研究関係者の5年あるいは10年雇い止め問題に関する大学・研究機関のリアルな現場と当事者の声を浮き彫りにしたものです。結果からは、改正労働契約法が研究者の雇用に「悪い影響を与えた」と回答した人が57%に達しており、クーリング期間をおいた再雇用の事例が多数報告されるなど、研究関係者たちが経済的・精神的に厳しい環境に置かれ、若手の博士課程離れや我が国の研究力の低下を招いている現状をお伝えしました。 アンケートの結果はこちらから。 大臣との意見交換 盛山文科大臣は、文部科学省が取り組みを開始した博士活躍プランに触れ、多くの博士人材を抱える海外企業との競争においては、日本の企業が博士人材を積極的に採用していく必要があること、そして、ただ博士採用を増やすだけではなく、高度人材にふさわしい職務や条件を準備していく必要があることを語りました。また、博士が企業に就職しづらい現状を変えるため、大臣自らが経団連など産業界に働きかけて経営者と直接の議論を重ねていることを紹介されました。また、大学の学長などの経営層との対話を行うことなども含め、アカデミア内で議論を行った上で政策提案をまとめて提示すると良いのではないか、というような期待を示されました。 今後の展望 今回の訪問は、博士人材の育成と雇用環境の改善に向け、大臣と研究関係者と博士の窮状と現場の課題を直接情報を共有し、意見交換をさせていただく貴重な機会となりました。政府、産業界、研究コミュニティの間の対話を活性化し、博士号取得者が、その特長を活かすことのできるキャリアを選択し、安心して活躍できる環境を整えることで、日本の科学技術力が飛躍的に上がり、日本、ひいては世界の人々のウェルビーイングの向上に貢献することができるはずです。この議論をきっかけに、博士人材の活躍を可能とする持続可能な仕組みとはどういったものかについてさらに議論を重ね、具体的な施策の実現へと進めていきたいと考えています。 訪問参加者 高橋 良輔:京都大学・教授、日本脳科学関連学会連合・代表 柚﨑 通介:慶應義塾大学・教授、日本神経科学学会・前会長、日本学術会議・神経科学分科会・委員長 宮川 剛:藤田医科大学・教授、日本神経科学学会・将来計画委員会・委員長 三田 剛嗣:慶應義塾大学大学院 医学研究科・D2/Keio-Spring 盛山宗太郎:慶應義塾大学病院 精神・神経科学教室
続きを読む
2024年10月21日
「大学・研究機関でのいわゆる「雇い止め問題」についてのアンケート」の結果
2024.10.16 pickup

「大学・研究機関でのいわゆる「雇い止め問題」についてのアンケート」の結果を掲載します。 2013年4月施行の改正労働契約法によって契約期間が通算5年(大学教員・研究者の場合は特例で10年)を越えると無期契約に転換できると定められました。そのため、10年を越えて無期転換権が発生する前に雇い止めが起きることが懸念されていました。そこで、施行から10年目となる2023年4月に文科省が全国の大学・研究機関を対象に調査を行い、令和5年9月に公表した「研究者・教員等の雇用状況に関する調査」(令和5年度)の調査結果では、「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等のうち、無期転換申込権発生までの期間(原則5年)を10年とする労働契約法の特例(以下、「10年特例」という。)の対象者」(特例対象者)のうち、約80%が無期労働契約を締結した又は締結する権利を得たとされましら。この結果を受けて、文科省の人材委員会のワーキンググループの論点整理(案)としては「現段階においては本制度が概ね適切に運用され、研究者・教員等の雇用の安定性の確保に一定の役割を果たしていると評価することができ、直ちに本制度を見直す必要はない」との方向での議論が進められています。 昨年4月に行われたアンケートは、文科省が主に大学・研究機関に対して行ったものであり、研究者関係者の声や実態はよく分かりません。例えば、研究費等を財源として雇用されている研究者・技官(特殊技能者)が、10年目を迎えた際に、研究費を財源として続けて雇用したくとも、無期転換権の発生を恐れる大学・研究機関のために実質的な雇い止めをされているという声も研究関係者の中では聞こえています。また、いったん退職して、他大学・研究所等で6ヶ月間のクーリングオフをした後に再雇用するような例もあるとも聞ききます。そこで、研究者サイドからの生の声を聞くことによって実態を把握することを企画しました。この調査結果を通じて、関係諸機関に研究環境の実態の理解を深めていただき、研究力強化に繋がる施策に反映していただくことを目指しました。 結果の概要をまとめたものと自由記述も含めた全回答をこちらからダウンロードできるようにいたしました。被雇用者側の研究関係者の悲痛な声のみならず、雇用をする側である研究室主催者などによる研究人材育成の困難さや研究力低下への影響についての懸念も多数示されており、多くの大学・研究機関においてこの問題が解決しているわけではないことがわかります。 今後、より詳細な分析と考察を行い、問題の解決とサステイナブルな仕組みの構築へ向けての提言も合わせて改めて公表することを予定しています。このアンケート結果などについての皆さまのご意見やご感想をこのページの下方にありますコメント欄にて受け付けますので、よろしくお願いします。 大学・研究機関でのいわゆる「雇い止め問題」についてのアンケート結果 [公開版 v1.04] 資料1 アンケートのフォーム 資料2 自由記述全回答(6番の質問) 資料3 雇い止め研究機関名リスト 資料4 自由記述全回答(10番の質問) 資料5 自由記述全回答(11番の質問) 研究関係者の雇用状況に関するアンケート(全データ) 企画: 日本神経科学学会・将来計画委員会 日本学術会議・基礎医学委員会・神経科学分科会 SciREX「安定性と流動性を両立したキャリアパスの仕組みについての定量・定性的研究」プロジェクト アンケート実施協力: 日本脳科学関連学会連合 生物科学学会連合 日本地球惑星科学連合 日本気象学会 日本エアロゾル学会 日本科学振興協会(JAAS)・研究環境改善ワーキンググループ
続きを読む
2024年10月16日
NEURO2024 ランチョン大討論会 〜 私達が望む神経科学の研究環境―よりよき現在と未来へ向けて
2024.09.06 pickup

2024年7月に福岡で開催されたNeuro2024にて「ランチョン大討論会 〜私達が望む神経科学の研究環境―よりよき現在と未来へ向けて」を開催しました。内閣府の総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)が策定する「第7期科学技術・イノベーション基本計画」に向けて、研究費や博士のキャリアパス、学会連合として連携することの意義と可能性について討論を行いました。 この記事では、大討論の内容をまるごとお届けします。 前回の記事はこちらから 【ご注意】記事内の各イメージをクリックしますと、高解像度の拡大したイメージをご覧いただけます。なお、記事内イメージのQRコードはご利用いただけません。 趣旨説明 私たちが望む神経科学の研究環境〜よりよき現在と未来に向けて 柚﨑通介 (慶應義塾大学・教授、日本神経科学学会・前会長、日本学術会議・神経科学分科会・委員長) 皆さんこんにちは最終日まで残っていただきましてありがとうございます。それでは恒例になりましたけども、ランチョン討論会を開始したいと思います。本日は「私達が望む神経科学の研究環境、よりよき現在と未来へ向けて」というテーマでディスカッションしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。私は司会をさせていただきます慶應義塾大学の柚﨑です。本討論会の主催は日本神経科学学会将来計画委員会ということで、(SciREXのプロジェクトと)共催のような形で行います。今日の流れですけども、まず最初に趣旨とその背景を私の方から簡単に説明させていただきます。それから、引き続いて最近皆さんもご存知と思いますけども、最近、生物科学学会連合(生科連)が主導して進めていただきました「科研費署名運動」について、これは後藤先生の方からご紹介いただくということですね。 その後で宮川先生の方からSciREXでの活動についてお話していただきます。できる限りこの3つは短めに30分以内に収めて、4番目の総合討論に時間を使いたいと思っております。全体で2時間です。申し訳ないんですけども、今回会場にはマイクはありませんので、LiveQのほうに質問やご意見を挙げていただけましたら、議論で取り上げさせていただきます。 では最初に今日の趣旨とその背景についてお話します。いうまでもないことですが、昨今、日本の科学力科学技術力が低下しているということ、あるいは次世代を担うべき研究者数が、相対的に低下していることはいろいろなところで議論になって、その問題の原因の分析も行われてきています。これまでに国の主導で 様々な対策も行われてきているところではあります。 ただ、肝心なことは、研究を行うのは我々です。それから、その研究を支えるのは基本的には国民からの税金です。ということで、研究者や国民からの働きかけが必須になっています。そのようなことでこの神経科学学会でも過去5、6回ランチョン討論会を通じて、様々な討論を行ってきました。 それから今日ご出席いただいている、生物科学学会連合や、あるいは脳科学関連学会連合などの学会連合でも、様々な活動をしています。ただ、問題なのは、せっかく議論してこの討論会も5、6回やってるんですけども、その後どうやって政策に反映し、どうやって実現していくのか、ここが非常に問題だろうと思います。今いろんなチャンネルがあっていいと思うんですけども、そのうちの一つのチャンネルとして、本来ならば日本学術会議が役割を果たさなくちゃいけないということで、今回、私が実はこの司会させていただいていますのは、この日本学術会議の基礎医学委員会の神経科学分科会の委員長となってますので、ぜひそれをチャンネルの一つとして、我々の声を何とか政策に反映したいという気持ちからであります。 昨今、いろいろ話題になってますけれども、日本 学術会議は、内閣総理大臣所轄のもとで、 職務を行うことになっています。1部(人文・社会科学)、2部(生命科学)、3部(理学・工学)とあり、会員210名で、我々は2部に属しています。 この学術会議の非常に重要なミッションは、政府に対して、勧告・答申・意見など、科学技術に関する意見を発表することができることです。今日何をしたいかというと、学術会議などで話し合われることの中では、分野をまたぐ重要な共通した問題、例えば、どうやって大学院生を増やしていったらいいかとか、そういうことは話し合われるんですけども、生命科学系、特に神経科学の分野に特徴的な課題というものが多くの場合、あんまりはっきりしてこないということがありますので、そこを明確にしたいと考えています。 それから、研究費、キャリアパス、我々の研究環境について、現場の若手も含むいろいろな年齢・ダイバーシティを含んだ研究者の意見を集約していきたい。そして最終的には国レベルでの政策フィードバックしていきたい、そんな狙いで本日の討論会を行います。 それでどうやって実現していくかについてですが、先ほど言いましたように、私は現在委員長を勤めている学術会議の神経科学分科会、高橋先生が委員長を務める脳とこころ分科会などに、多くの神経科学系の研究者が参加していますので、そこでさらに今日の議論をまとめていきたいと思っています。そして、今日ご出席していただいている林先生が委員長をされている科学者委員会 学術体制分科会というところからの提言として、次の2026年からスタートする第7期科学技術イノベーション基本計画に少しでも意見を反映していくことを現実的な出口として今回考えています。 この科学技術イノベーション基本計画は結構重要で、昨今のいろんな政策のもとになってるのは、最終的にはここですので、何とか意見をインプットしていければと考えています。 といっても、なかなか議論がまとまらないと思いますので、議論のたたき台として4点、論点を用意しました。一つ目が、キャリアパスの問題。それからもう一つは、研究費の問題、特に基盤的研究費の問題。それから分野横断的な対話・議論ができる場をどのようにして作っていくか。そして最後の4番目として、社会との対話の活性化について。この4点についてディスカッションしていきたいと考えています。 私からの説明は終わります。大体予定時間通りですね。できるだけ本音の討論をしたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。 話題提供 科研費増額要望書提出・署名活動開始の背景について 後藤 由季子 (東京大学・教授、生物科学学会連合・副代表) 一応、生物科学学会連合の副代表という立場でこちらにおりますが、代表は東原先生でいらっしゃいまして、東原先生がいろいろな学会連合に働きかける形で、今や理系だけではなく、文系の学会連合にもご賛同を次々といただき、大変広い活動となってきております。この活動の背景につきまして、ご説明させていただきます。 日本のこのTop 10%論文数が世界で13位まで落ちたというニュース、皆さんもご覧なってるかもしれません。しかしながら、インパクトのある論文が少ないというだけではなくて、日本の研究が遅れているという残念な現実がございます。 これは浅見先生らが出された論文で、このデータは研究テーマの相関を網羅的に調べたものですけれども、例えば、アメリカで2010年に扱われた研究テーマが中国の論文でいつ扱われているかというと、約1年遅れているんです。 残念ながら日本もそうでして、このようにアメリカで扱われているテーマが、1年ぐらい遅れて扱われてしまっている。これに対して他の西欧諸国ではほぼピークが一緒になってます。日本はこの縦軸のこの被論文引用率という点、横軸の、先ほどお話したその研究トピックの先進性という点、両方において、この西洋諸国から大きく遅れてしまっています。 これは、産業的にもまずい状況です。これは豊田先生の解析ですが、この論文引用数が高い論文の方が特許に引用されてイノベーションにより貢献しているという図になります。つまり先進的でインパクトの高い論文が少ないということは、イノベーションへの貢献が少ないというふうにも言えます。 ではどうやったら費用対効果高く、効果的にインパクトの高い論文を生み出せるのでしょうか? このe-CSTIの分析結果を見ますと 同じ研究費の額に対して、「科研費がメインの研究者」の論文の被引用率が4から6なのに対して、「科研費以外の競争的資金がメインの研究者」の論文の被引用率は、1から2と、かなり差がついています。これは科研費が非常に効率よく、論文被引用率の高い、インパクトの高い論文を産んでいることを示しています。 科研費には、新しく芽を作る、すなわち新しいトレンドを作り出すという重要な役割があります。一方、この戦略目標に沿った競争的資金というのはこちらも非常に大事です。あえて強調しますが、後者が駄目だと言ってるわけではなくて、こちらはこちらで非常に重要な役割をしていて、注目分野や既にある芽を選択と集中によって育てていくという、役割がございます。どちらも非常に重要であり、バランスよく支援する必要があると言えます。 ところが、この科学技術関係の予算の中で科研費の割合というのは実はたった5%に過ぎません。しかも全体の予算が徐々に増えている中で、実は科研費は全く増えていません。 増えてないばかりか、実質、皆さん体感されていると思いますけれども、大幅に減ったと思われています。減った理由はいくつかあるんですけれども、デュアルサポートのシステム崩壊というのが非常に大きな原因だと思われています。 基盤的な研究というのは従来、運営費交付金や私学助成などの経常的な資金と科研費、この二つでサポートされていました。しかし、この大学法人化以降、経常的資金というのがどんどん減ってしまったために、その肩代わりとして、これまで競争的資金、科研費に応募していなかった方々が、もうやってられないということで科研費に応募するという方が増えました。その結果、申請数が非常に増えてそれによって採択件数が大幅に増えました。科研費総額は同じということで、つまり1件当たりの配分額が減ったということになります。実際その結果非常に激戦になっていて、この基盤(A)、(B)などでは本当に世界的にレベルの高い研究者がちゃんとレベルの高い研究提案をしていても不採択になっているという状況です。 そして、その激戦を勝ち抜いても基盤Bは年間600万円です。これですと、人ひとり雇用できないということにもな ります。この危機感というのは分野を超えて多くの研究者の間で共通です。例えば、文科省の研究費部会でも、日本でアクティビティの高い研究者が、基盤 (S)(A)(B)に申請しても、7割以上は不採択になってしまい、その年の科研費がゼロになってしまうことを非常にもったいないと述べています。 なので、科研費予算の規模を抜本的に増大すべきという意見が繰り返し出されています。これは一例ですけれども、オートファジーの発見でノーベル賞を取られた大隅先生は、科研費を主体として、初期、非常にオリジナルな研究をされていましたが、時には科研費で不採択になったこともありました。しかしその頃は運営費交付金がございましたので、科研費に落ちても研究を細々と続けられてオリジナルの研究を継続できました。ですから、研究の芽を作り育てるには、科研費と経常的経費の補助の両輪が大事だということを強調したいです。 またカタリン・カリコ博士もおっしゃってるように、研究の成果の予測というのは難しいです。だからこそ、研究者の自由な発想に基づく研究を幅広く支援することが重要だと思われます。特に脳神経科学という領域は複合領域でありまして、幅広い分野からの多様な芽が出る環境というのを整えることは、特に重要であるというふうに考えられます。 しかしながら、国のトップである統合イノベーション戦略推進会議では、先ほど 柚﨑先生がおっしゃった通り、今でもこのアイディアが理解されていません。むしろもっと選択と集中の方向を進める方針が続いています。これでは日本の研究の遅れがさらに悪化してしまうと思われます。 もう一つ、この科研費が額面上は一定に見えて実質大きく目減りしたという理由としてコストの拡大もあります。物価高騰と円安を考慮しますと、科研費の実質の平均配分額はこの10年で約半分になっています。 しかし、例えばアメリカの研究費であるNHI RO1では、この物価高によるコストの増加を考慮して配分額をこの20年余りで2倍以上に増やしている。一方、日本はそのような補填をせず、そこにさらに円安が加わっています。我々の研究材料は輸入品に多くを頼っておりますので円安の影響を受けやすい。また、もちろん皆様も体感されているように、ジャーナル掲載料・購読料の高騰も追い討ちをかけています。 年々増やしていただいている科学技術関係予算の一部を科研費にあてるだけで、どんなにたくさんの研究の芽が育つだろうか、どんなにたくさんの若手の方の新しい発想が活かせるだろうか、と思うのです。 そこで、多くの皆さんが本当に同じことを思ってらっしゃったと思いますので、そのご意見を反映し、日本の未来のためにということで、この科研費の増額を求めましょうという運動を始めました。 とりあえず2倍を目標にお声かけをしているところですが、これまでに非常にたくさんの学会連合や学協会に次々とご賛同いただきまして、本当に幅広い運動になっています。メディアでも取り上げていただいてます。 今、若手の人材が本当に減ってるので、それに対してもこういった基盤的な経費がとても大事だということを最後に申し上げて、ぜひ皆様にご支援いただきたいと思っております。 話題提供 安定性と流動性を両立したキャリアパスの仕組みについての定量・定性的研究 宮川剛 (藤田医科大学・教授、日本神経科学学会・将来計画委員会・委員長) 藤田医科大学の宮川です、よろしくお願いいたします。博士のキャリアパスにつきまして、SciREX事業 共進化実現プログラム「安定性と流動性を両立したキャリアパスの仕組みについての定量・定性的研究」というプロジェクトを行っております。これは文科省の人材政策課の官僚の方々と、日本科学振興協会の有志数名で共同で行っているプロジェクトで、私はこのプロジェクトの共同代表を務めております。これについて簡単に紹介させていただきます。 このプロジェクトを始めた経緯なんですけれども、皆様ご存知のように多くの先進国では博士号取得者がどんどん増えているのに対し、日本では(相対的に)減少傾向、あるいは低いレベルで横ばいであり、若手の科学技術分野への参入が減ってしまっているという、大変由々しき事態です。 今後、このままでは科学技術立国としての日本がまずい、というか、もう既に「だいぶまずい」状態になっている。なぜこんなことになってしまってるのでしょうか?おそらくその最大の原因は、ポスト、研究者・博士のポストが不安定だからであろうと考えられます。 大学で研究者の半数近くが任期付でありまして、しかも最近は、10年雇い止めの問題というような深刻な問題も起きてしまっているわけです。これは世界的にもそうだとは思うんですが、アンケートをとりますと、知識生産活動で重要だと思う要因に「経済的安定」を挙げる人がほとんど、9割方の人であることがわかっています。 また、これは以前この討論会でとったアンケートですが、終身雇用の主観的価値は日本ではとても高く、年間100万円から300万円程度にも上るというふうに考える人が多いわけであります。ポストが不安定で苦しんでいる先輩たちを見て、若手が博士課程に進学することを躊躇するようになってしまっているのです。 ならば、なぜ大学教員に任期付き雇用が導入されたのかというと、そもそもの目的は研究者の流動性を高めるためでありました。平成9年に「大学の教員等の任期に関する法律」というのができ、それまで終身雇用が原則であった大学教員で、任期付き雇用ができるように改正されたのですが、この経緯を調べると明確に「研究者の流動性を高めること」が目的と書かれています。 もう一つ、任期付が増えた大きな要因は、運営費交付金から競争的資金に基金がシフトしてきて、競争的資金が増えて、それで雇用される研究者が増えたことです。競争的資金は3年から5年の期限付きであるため、その資金で雇用される人も必然的に任期付になってしまうのです。 このような背景を踏まえて、私たちは、流動性を確保しつつ、競争資金を元手に研究者の終身雇用ポストを増やすことはできないか、と考え、提案をしているところです。 この案は、一言で言えば、「競争的資金・自己資金で無期雇用され、大学や企業など、分野・職種の壁を越えて研究を行う博士の人材プール制度」です。博士を大学コンソーシアムやJSPS、AMEDなどの資金配分機関、あるいは企業が終身雇用し、それらを派遣元として、博士が派遣先の大学や企業で研究関連業務を行うという仕組みです。ポイントは、派遣先が競争的資金や企業の自己資金で人件費を負担し、派遣元に支払うという点にあります。 この仕組みであれば、大きな予算の追加負担なしに終身雇用ポストを創出できるのではないかということです。ただの派遣ではなく、職階は派遣先で特任准教授、シニア・エンジニア、といった社会的な体裁の良い名称を付与していただくことをイメージしています。 現在アカデミアでは博士人材は事実上、研究室主宰者、いわゆるPIとしてのコースを目指すしかないような状況で、競争に勝ち残ってPIコースに残るか負けてしまうか、どちらかになってるのが実情です。しかし、PIだけが研究を行っているわけではなく、ポスドク、技術支援、アドミニストレーター、それから教育中心の方など、多様な研究者としてのキャリアパスがあった方が良いのではないかと思います。 そして、その人のモチベーションや特徴、得意なこと、ライフステージに合わせて、フレキシブルに適材適所の人事異動が行われるような流動性を確保したいということです。我々の提案では、人事異動を奨励するだけではなく、大学の正規の終身雇用教員に対しても、そのような人事異動をできるだけ促進していただくと良いのではないかと考えています。これを「次世代型選択集中」と呼んでいまして、実験、解析技術、アドミニストレータなど、その人の得意なことに選択を集中してもらうということで、分業体制が充実し、研究関係者が研究に集中できる時間を確保しやすくなるというメリットがあると思っています。 この提案のもう一つのポイントは、企業です。企業に博士がどんどん 輩出されなければいけないということがありますが、企業に派遣された場合に、博士と企業のマッチングがうまくいかないような場合がありえますが 、気軽な お試し雇用が促進できるということです。 このプロジェクトは、現在、調査研究をしておりまして、本日は皆様からのご意見を伺って案に反映し、実現したいと考えております。ぜひ忌憚のないご意見をお願いできればと思います。 パネルディスカッション 柚﨑 まず最初に、ご講演をされていないパネリストの皆様は、自己紹介をお願いできますでしょうか?山中先生からお願いします。 山中 名古屋大学の山中です。立場としては本学会の理事長も務めさせてもらっています。また大学の方でも研究の方向をデザインするような立場も兼務してますので、一緒に議論できればと思っております。 山中 宏二:名古屋大学・教授/副総長、日本神経科学学会・理事長 久保 理化学研究所の久保と申します。私は神経科学学会の将来計画委員会の委員をさせていただいています。日本学術会議のメンバーもさせていただいており、特に若手アカデミーという若手の研究者で作っている学術会議の中にある組織で活動をしております。今回は中堅の枠で議論に参加できればと思っております。よろしくお願いします。 久保 郁:理化学研究所・チームリーダー、日本神経科学学会・将来計画委員会・委員 加藤 初めまして。マウントサイナイ医科大学の加藤郁佳です。私はまだ博士号を取得して1年半ぐらいで、このような場で意見できることがたくさんあるかわからないんですけど、日本神経科学学会の将来計画委員会の方で若手委員をしておりますので、若手というか、新しくこの分野でこれからやっていきたいなと思っている立場として、何か意見ができたらなと思っています。よろしくお願いいたします。 加藤 郁佳:マウントサイナイ医科大学・ポスドク、日本神経科学学会・将来計画委員会・委員 金井 株式会社アラヤの金井と申します。僕は元々10年ぐらい前まではイギリスのサセックス大学っていうところでアカデミアで認知神経科学分野の研究をしてました。このアラヤっていう会社は自分で立ち上げた会社なんですけど、脳科学に関係あるような分野の事業化を目指してやってます。脳とAIの両方を扱っているのですけど、そういう意味で研究者のキャリアパスとかを考えるときに、面白い観点があるんじゃないかなと思います。 あとは、今国のムーンショットっていうプロジェクトのプロジェクトマネージャーをやっていて、そこでは神経科学全般の人たちに参加していただいて、主にブレイン・マシーン・インターフェースの開発をやっています。よろしくお願いします。 金井 良太:(株)アラヤ・代表取締役 林 林と申します。本務は文部科学省科学技術・学術政策研究所のデータ解析政策研究室長をやっております。文科省の人間ということで念のため申し上げますが、私は [...]
続きを読む
2024年9月6日
日本の科学力の向上へむけて
2024.07.01 HOME

2024年7月に福岡で開かれるNeuro2024にて「ランチョン大討論会 〜私達が望む神経科学の研究環境―よりよき現在と未来へ向けて」を開催します。本稿は同企画における議論のたたき台となるものです。 近年、日本の科学力の相対的な低下が顕著となり、これに対するさまざまな対策が行われつつあります。1990年代から始まった大学院重点化、2004年の国立大学法人化、近年では地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージや国際卓越大学など、さまざまな大学改革が政府主導で行われています。また、総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)においては、第7期科学技術・イノベーション基本計画が策定中です。 でも、肝心の研究の担い手は私たちです。日本学術会議やさまざまな学協会においてもさまざまな議論が行われていますが、人文社会科学系や数物系、理工学系と、生命科学系ではかなり置かれている状況が異なります。神経科学はこれら幅広い分野からの研究者が参加する融合的/分野横断的な研究を特徴としており、それぞれの研究者が置かれる状況も多様です。本討論会では、この多様性を踏まえつつ、研究費やキャリアパス等の研究環境について、現場の研究者の意見を集約します。その結果を国レベルでの政策にフィードバックすることを通じて、よりよい研究環境を創っていきましょう。 研究の原動力は何かを知りたいという好奇心や、何かを実現したいという情熱です。しかし、好奇心と情熱に基づく研究は、すぐに成果が得られ社会の「役に立つ」とは限らないため、これらを長期的にサポートする環境と十分な資金、社会的な理解が必要です。では、どのようにすれば、研究者が安心してじっくりと研究に打ち込み、成果を挙げていくことができる研究環境を整備できるのか?そのために必要な資金と社会的理解をどのようにして得るのか?様々なステイクホルダーが協働して議論を進める必要があると考えますが、そのたたき台として以下の原則を提案します。これらについて、皆さまからのご忌憚のないご意見を歓迎いたします! 1. 研究関係者のキャリアパスを長期的に俯瞰できるものに! ・研究室主催者を目指す研究者のトラックのみならず、アドミニストレーション、技術支援、教育中心などのトラックを用意することにより研究者の多様なキャリアパスを実現し、各人の個性を活かした分業体制を充実させること。 ・研究関係者のキャリアパスを、現代の日本社会の標準的な正規雇用のあり方にできるだけ合わせつつ、各人の適性とライフステージに合わせた適材適所の流動性を確保すること。 ・博士号取得者が広く社会に受容されるための各種基盤を整備すること。 2. 安定した基盤的研究費の充実を! ・基盤的な科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金;いわゆる科研費)の充実(増額と申請・評価疲れ低減のための大括り化など)と安定化(評価による増減ありのリニューアル可能なものにするなど)を実現すること。 ・政策的なトップダウン研究費と基盤的なボトムアップ研究費(科研費)の効果的・有機的な連携システムを構築すること。 ・基金化などによる年度繰り越しの容易化をすべての研究費に普及させること。 3. 分野横断的な対話・議論ができる場を! ・学協会レベルでの各年齢層にわたる意見を、国の政策に活かしていくための双方向コミュニケーションの場を充実すること。 ・分野横断的な問題については学会の連合体や、日本学術会議と連動して協議できる場を立ち上げること。 4. 社会との対話の活性化を! 研究から得られた成果が学術的・社会的なイノベーションを生みやすくするために、オープンサイエンスを推進し、一般国民、企業関係者、政治家、官僚などと双方向性のコミュニケーションや連携を行うことのできる場や仕組みを設けていくこと。 Text by 日本神経科学学会・ランチョン大討論会・企画者一同 参考: ・「わが国の研究力向上に向けた日本学術会議の取り組み−審議の経過と将来展望−」 日本学術会議我が国の学術の発展・研究力強化にする検討委員会・委員長 山口周 [PDF] ・「2040 年の科学・学術と社会を見据えて いま取り組むべき10の課題」日本学術会議若手アカデミー [PDF] ・盛山正仁文部科学大臣によるJAAS年次大会2023開会式でのビデオメッセージ(書き起こし):https://meetings.jaas.science/blog/20231007-4484/ ・JAAS研究環境完全WGによる“科学の生態系”にエネルギーを!「10兆円規模の大学ファンド」等についての提言:https://jaas.science/2022/04/20/10_trillion_fund/ ・JAAS「会いに行ける科学者フェス」の紹介文:https://meetings.jaas.science/overview/ ・神経科学者SNSの「これからの科学・技術研究 についての提言」 [PDF]
続きを読む
2024年7月1日
私達が望む神経科学の研究環境―よりよき現在と未来へ向けて Neuro2024ランチョン大討論会開催!
2024.06.06 pickup

2024年7月に福岡で開かれるNeuro2024にて「ランチョン大討論会 〜私達が望む神経科学の研究環境―よりよき現在と未来へ向けて」を開催します! 政府は「科学技術・イノベーション基本計画」を策定し、長期的視野に立って体系的かつ一貫した科学技術政策を実行することとなっています。具体的には内閣総理大臣からの諮問を受けて、総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)において、基本計画が策定されます。基本計画は、これまでにImPact、SIP、ムーンショット、国際卓越研究大学等の政策に大きな影響を与えてきています。現在進行中の「第7期科学技術・イノベーション基本計画」に向かって、神経科学分野の特徴も踏まえつつ、研究費やキャリアパス等について、現場の研究者、特に若手の皆さまからの意見を集約して計画にフィードバックすることを通じ、よりよい研究環境を創っていきましょう! Webinar ご視聴はこちらから! https://zoom.us/webinar/register/WN_hy2dWMimRtC1VyscKqZP9Q LiveQ ご質問を受け付けます! https://liveq.page/ja/NqmQtTUKuLHEJw8W3fCS 議論のたたき台となるテキスト「日本の科学力の向上へむけて」を公開しました! 前回同様、X(旧Twitter)にてハッシュタグ #大ラン討 にてご意見も募集します! 当日会場では豪華ランチを提供予定です! 日時:2024年7月27日(土)12:15~14:15 場所:Neuro2024(第47回日本神経科学大会・第67回日本神経化学会大会・第46回日本生物学的精神医学会年会・第8回アジアオセアニア神経科学連合コングレス;福岡国際会議場第3会場) パネリスト(五十音順) – 加藤 郁佳:マウントサイナイ医科大学・ポスドク、日本神経科学学会・将来計画委員会・委員 – 金井 良太:(株)アラヤ・代表取締役 – 久保 郁:理化学研究所・チームリーダー、日本神経科学学会・将来計画委員会・委員 – 後藤 由季子:東京大学・教授、生物科学学会連合・副代表 – 高橋 良輔:京都大学・教授、日本脳科学関連学会連合・代表 – 東原 和成:東京大学・教授、生物科学学会連合・代表 – 林 和弘:文部科学省科学技術・学術政策研究所・データ解析政策研究室長、日本学術会議・ 学術体制分科会・委員長 – 宮川 剛:藤田医科大学・教授、日本神経科学学会・将来計画委員会・委員長 – 山中 宏二:名古屋大学・教授/副総長、日本神経科学学会・理事長 – 柚﨑 通介:慶應義塾大学・教授、日本神経科学学会・前会長、日本学術会議・神経科学分科会・委員長 主催: 日本神経科学学会・将来計画委員会 共催: SciREX「安定性と流動性を両立したキャリアパスの仕組みについての定量・定性的研究」プロジェクト 後援:日本脳科学関連学会連合、生物科学学会連合、日本科学振興協会(JAAS)、日本学術会議 協力:小清水 久嗣(藤田医科大学・URA室長/教授)、サイエンストークス
続きを読む
2024年6月6日
インパクトファクター至上主義からの脱却を目指そう
2024.03.01 pickup
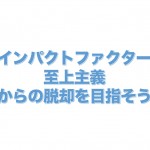
インパクトファクター至上主義からの脱却を目指そう 藤田医科大学・宮川剛 私は、個人としてDORAに署名し、また日本神経科学学会の将来計画委員会・委員長として学会のDORA署名にもたずさわりました。私が所属している団体としては、他にも日本分子生物学会、日本生物科学連合が署名をしており、日本科学振興協会(JAAS)による署名は私が関係するものとしては少なくとも5つめの署名ということになるかと思います。 DORAの宣言の中で指摘されているようにジャーナル・インパクトファクター(JIF)偏重が数多の深刻な弊害を科学コミュニティにもたらしていることは疑いようがありません。しかし、DORAが発出されてから11年以上が経過しDORAへの日本からの署名も増えているにもかかわらず、正直、日本でのジャーナル・インパクトファクター至上主義は、未だほとんど改善されていないと断言して差し支えないでしょう。DORAへの署名はJIF至上主義から脱出するための重要な一歩ではありますが、現在でもはびこるJIF偏重を見れば、それだけでは全然十分でなく、そのための具体的な策を研究コミュニティが立案し実行していくためのロードマップが必要であることを示しているように思います。ここでは、JIF偏重がなぜ生じ、なぜダメなのか、その欠点を改めて復習し、それを解消するための私なりの策をいくつか提案させていただきます。 要点 JIFが、論文や研究者の質の評価指標として不適切に使われている。 JIFの欠点には、1) 再現性と有用性の評価の欠如、2) 不適切な競争の助長とムダの生産、3) 研究不正の助長、4) 出版バイアスの助長、5) 盛りすぎ広報の助長、などがあり、JIF至上主義は科学の進歩を遅らせる科学の敵といって過言ではない。 JIF至上主義を克服するために、A) 出版後評価の拡大、B) 即時ゴールドOA義務化と高IF誌の出版コストの可視化、C)サウンドネス基準のジャーナルを増やす、D) 論文の価値評価を行う総説誌を立ち上げる、などを提案する。 1. JIFの社会的機能 JIFの弊害が叫ばれる中、これを偏重する文化はなぜ無くならないのでしょうか?それは、JIFにはある種の社会的機能があるからであり、この機能があまりに便利すぎ、必要不可欠な存在となるまでにアカデミアに深く組み込まれてしまっており、事実上、手放すことが困難だからです。 その社会的機能と一言で表現すれば、研究評価と広報の機能になるでしょう。各ジャーナルでは、投稿されてきた論文の原稿の技術的・科学的健全性、独創性・新奇性、学術的・社会的インパクトなどが、担当のエディターと2~4名程度の査読者によって評価されます。この査読による評価は、一般的にJIFが高いジャーナルほど厳しく、そのジャーナルから出版される平均的な論文の「質」がJIFに代表されているとぼんやりと考えられています。これは、「ぼんやりと考えられている」だけなのであって、実際にはそのようなことは必ずしもないことも一方で理解されており、DORAでも「研究評価ツールとしてのインパクトファクターの欠点について数多くの指摘がなされている」と記載されていますが、これは裏を返せば、インパクトファクターが研究評価ツールとして実際には用いられているということです。 アカデミアでは、研究費の審査や人事、学会賞などの審査において、当該の人が出版した学術論文を評価する必要があります。この評価は、その人が得る研究費、ポスト、研究者としての社会的名声などの基盤になり、研究を継続することができるか否かも決めますので極めて重要であり、ある程度の実績とポジションを有する研究者にとっては、他の研究者を評価する業務が日常的な作業の少なからぬ部分を占めています。しかしながら、これらの他者を評価するような立場の研究者(多くの場合、准教授や教授などのいわゆる研究室主催者)は、様々な業務であまりに多忙で、個々の論文を評価する時間を取ることが事実上、ほぼ不可能なのです。自分自身の研究に費やす時間すら十分に取れていない一方で、JSPS、JST、AMEDや各種財団の研究費など、機関向け競争的資金の種目数は膨大で、賞の選考、人事なども多数あります。これらの評価・選考に関わる人材は限られていて数が足りておらず、しかもどの選考でも応募者の数が膨大な数となることが多く、個々の論文をしっかり読み込んで評価を行うための時間が圧倒的に欠如しているのです。いくら真摯に評価をしようと考えている審査員でも100人もの応募者の論文すべてを読むことができるわけがないですね。このような状況の中で、評価者/審査員が自分自身でオリジナルな評価・審査をせずとも使える極めて便利な数値的評価指標がJIF、ということになるかと思います。JIFは論文評価の代理指標、サロゲートマーカーであるわけです。 私も各種の審査をする機会をかなりいただきますが、複数の賞や研究費の選考で、ある種の実験を行ったことがあります。申請者の論文実績について各論文のJIFと被引用数を調べ、それぞれ足し合わせるということをアシスタントに行ってもらいました。それだけをもとに仮の評点を機械的につける、ということをしてみました。これらの選考では、他の審査員の評点がわかるようになっていたのですが、機械的に計算した評点と他の審査員全員の平均評点の相関をみてみますとこれが極めて高い。とある選考おいて、それぞれの審査員の評点と、その審査委員以外の審査委員全員の評点の相関を、それぞれの審査委員ごとにだしてみると、なんと機械的に計算した評点の相関がトップにきた、ということがありました(その際の審査員の人数は通常のものよりも多い審査でした)。つまり、JIFをサロゲートマーカーにして審査をしていれば、大きくは外すことはないのであり、逆にいえば、多くの審査員はJIFの計算を(おそらく)頭の中でわりと雑に行い、その他もろもろで多少の調整をしているだけな場合が多いのではないか、と推測されます。これが事実であるとすれば、私たち評価者が行っていることは機械による計算にまかせてしまったほうがよいのではないか、ということになります。 これは、別の見方をしますと、研究コミュニティは、各論文ひいては研究費の申請や研究者そのものの評価をジャーナルのエディターと査読者に丸投げしてしまっている状況に近いといえます。誰がどのような研究費/人事/賞の審査をしようとも、このようなJIFに依存した評価では同じような結果になってしまい、高IFジャーナルのエディターと査読者が莫大な力を持ってしまうことになるのです。日本には高IFジャーナルはほとんどありませんので、日本の科学技術は高IF誌に研究の方向性のイニシアチブを取られて過小評価をされることにもなってしまっているのではないでしょうか。 JIFには、加えて、このような論文の評価機能から派生した広報機能があります。世の中には、日々、膨大な論文が出版されており、個々の研究者が専門とする狭い分野ですら、そのすべてをフォローして読み込んでいくことは不可能です。しかし、多くの研究者は、先端を切り開くような論文について常にアップデートされた状態であることを望みますので、それをサポートするような何かが必要となります。JIFの高いジャーナルの目次をざっと見るということは、分野の最先端にキャッチアップするための有効な手段であり、著者側から見れば、そのようなジャーナルに掲載されることは大きな広報効果を持つことになるわけです。高いJIFのジャーナルは、ジャーナル独自の広報・プレスリリースを行うこともありますし、そのようなジャーナルに掲載された論文は、著者やその所属機関がプレスリリースを行う場合もあり、その広報効果にはされにレバレッジがかけられることになります。 2. JIF偏重はなぜダメなのか? 研究評価と広報の機能を担い、「研究評価ツール」として活用されてしまっているJIFですが、DORAの主張するように「数多くの欠点」があります。その欠点を簡単に整理してみます。 欠点1: 再現性と有用性の評価の欠如 現状、JIFは、論文の評価ツール、研究の質のサロゲートマーカーとして使われてしまっているわけですが、研究の評価の上で極めて重要な2つの観点が決定的に欠落しています。それは、その論文で報告する結果やアイデアの再現性と有用性です。 科学技術がアートや宗教などと大きく異なる点の一つは再現性です。論文で記載された方法に従って実験・調査を行えば、原則的には同様な結果の再現性が得られるはず、ということ、科学はそのような意味で普遍性がある、ということです。ただ、実際には再現性が得られないことは多々あり、論文の半分から50~70%もが再現性が得られないという報告(1,2)もありますので、報告した現象が再現できるか否か、再現性が高いか低いかというのは、その論文の評価の重要な指標となるべきです。研究がきちんと行われている限りは結果の再現性が得られない論文の価値がゼロというわけでは必ずしもないのですが、再現性の高低が論文の価値の重要な指標の一つであることに意義を唱える人は少ないでしょう。 また、出版後、ある程度の時間がたったあとに、その論文で報告したものが有用であったか、広い意味で役にたったか、というのも重要な評価指標です。有用である、役にたつ、というのは、広く社会に実装され利用されるという意味ももちろんありますし、純粋に学術的な仮説や理論の構築の上で後続の研究の役にたったのか、世界の知識基盤の総体を拡大することにどの程度役にたったのか、というような視点ももちろん含まれます。 科学の本質とも言える再現性と有用性は、ある程度の時間の経過がないと評価ができません。したがって、本来、論文の本当の価値は出版後の中・長期的な評価で決まると断言して差し支えありません。高IFのジャーナルの査読では、”Conceptual advance”や、”Broad interest”が評価の視点の重要な部分を占めますが、出版後に再現性のないことがわかった結果に依拠した”Conceptual advance”は「概念の進歩」とはなっていなかったことになりますし、出版後に(社会実装でも学術的にも)「使えない」とわかった論文は当初”Broad interest”があったとしても、世の中からの関心はなくなっていくはずです。独創性・新奇性がいくら高くても、再現性と有用性がゼロであるような研究はその価値もほとんどないといっていいでしょう。再現性も有用性も、中長期的な時間の流れの中で、研究コミュニティや社会が徐々に決めていくものであり、エディターや査読者が出版前に決めることができるものではありません。科学技術の本質である再現性と有用性の観点の欠如は、研究評価ツールとしてのJIFの決定的な欠点と言えるでしょう。 欠点2: 不適切な競争の助長とムダの生産 JIFを高くするためのジャーナル間の競争は、著者らの不適切な競争を招き、多大なムダを生産してしまっています。ジャーナルがJIFを高くするためには、「質の高い」と推定される少数の論文のみを採択することが重要です。このため、科学的・技術的に健全であっても多くの原稿がリジェクトされてしまいます。リジェクトされた原稿は、他のジャーナルに再投稿されるわけですが、投稿のための労力(フォーマットの変更や、各種投稿手続き)や査読のための時間(2週間から2ヶ月程度)が浪費されます。リジェクトによる心理的ストレスとそのストレスからくる生産性の低下も、おそらく膨大なものでしょう(どなたかに推定してみていただきたいところ)。 採択に至る論文であっても、「質を上げる」ための実験・調査の追加などの改訂を要求され、出版が遅れることが多々あり、論文の初投稿から、高いIFのジャーナルを狙ったがゆえに出版まで2年かかってしまった、というようなことも稀ではありません。論文が世に出るのが遅れるわけですから、これは科学コミュニティと社会の損失となっているはずです。 激しい競争から、高IFジャーナルのエディターと査読者は過大な権力を持ってしまうことになり、これに伴う不適切行為も多々生じています。査読は普通クローズドで行われますが、これに伴い密室でのハラスメントが行われることがあります。分野の大御所はそのような点で権力をもっていて、査読の際に自己の仮説について過剰にバイアスがかかった査読を行ったり、自己の論文の引用を強要したりすることがあります。さらには、自分が査読者であることを暗に(ときには明示的に)示したりすることにより、著者やその所属機関などから接待を受けることなどがあります。世界的にも、多額の資金を使って、高IF誌のエディターや査読者(になりそうな研究者)を招いてセミナーや研究会などを行い、観光や食事などの接待を行うこと、そしてそのような接待の資金をもつ研究者や研究機関の論文が優先的に掲載されるようなことは普通であるといってよいでしょう。このような接待によるコミュニケーションには、科学的な交流を通じて情報交換・議論を行うというポジティブな意義ももちろんあるわけですが、これが閉鎖的なコネや研究者ギルドのようなものの形成を促してしまい、査読時のバイアスを強め、他の研究者の排除につながりかねないなど、公平・公正な科学の進歩を妨げる側面がある面は指摘しておく必要があると思われます。 欠点3: 研究不正の助長 高IFジャーナルの狭き門をくぐって掲載されるための不適切な競争から生じている極めて毒性の強い副産物として、questionable research practice (QRP;不適切な研究行為)と不正があると考えられます。再現性と有用性は上述したように科学の本質ですが、QRPと捏造・改ざんなどの不正は当然のことながら、これらを低減させる方向に働き、科学と社会にとっては本来、百害あって一利なしの行為です。しかしながら、査読の時点では(ある程度の予想をすることはできても)実際の再現性と有用性は原理的には評価することが不可能です。高IFジャーナルに出版した研究者が研究費・人事・賞などのレースのすべてで勝ちを独占しがちである現状のもと、再現性・有用性は出版に至る競争では評価されないわけです。p-hacking、HARKINGなどのQRPや、データの改変や捏造などの不正を行っても、それが見つからない限りは、論文の出版まで漕ぎ着きさえすれば「勝ち」がほぼ決まりになってしまいます。オランダで7000人弱の研究者に行われた調査では、捏造・改ざんなどの不正に関わったことのある研究者が4%、QRPを頻繁に行っている研究者はなんと50%以上おり、QRPを助長する最大の要因としてPublication pressure (論文出版へのプレッシャー)が抽出されています(3)。私は、Molecular BrainとNeuropsychopharmacology Reportsという2つの国際学術誌の編集長をしておりますが、以前、ある種の社会実験を行ったことがあります。データが”too beautiful to be true”に見えた41の原稿について、生データを著者に提出するようにお願いしたところ、半分以上の原稿は生データを提出することなく取り下げになり、データが提出された原稿でもその9割以上で真っ当な生データが提出されなかった(生データと結果が全く一致しないとか、生データのごく一部しか提出されない等)のです(4)。現状、生データの公開は義務化されていない場合がほとんどであり、捏造・改ざんなどの不正が見つかり認定されるようなケースは少ないですので必然的にQRPや不正を後押ししてしまっていることになっていると考えられます。適切な実験計画・データ管理には時間・労力がかかりますし、現実の実験・調査でエディターや査読者の要求を満足させるような「きれいな」インパクトのあるデータが出るとは限りません。JIF至上主義の弊害で、「正直者が馬鹿を見る」世界に残念ながらなってしまっているといえるでしょう。信頼できるデータで構築された「巨人の肩に乗る」ことが科学の本質なはずですが、この弊害で、データの山は砂上の楼閣となりがちなわけです。 欠点4: 出版バイアスの助長 高IF至上主義の裏返しとして、「ネガティブデータの論文」、「仮説が支持されなかった場合の論文」、「再現性が確認されなかったという論文」などが出版されにくいという現象が生じます。これらの論文は多くの場合、高IF誌では採択されにくいからです。実際、効果量がJIFが高いほど過大に推定されがち、というようなことも報告されています(5,6)。論文はネガティヴデータ、仮説が支持されなかったり再現性が確認できなかったような研究、さらに言えば失敗の実験ですら出版されることが望ましいです。世界の他の誰かが、同じ失敗を繰り返すことを未然に防ぐことができるかもしれませんし、公的研究費が用いられた研究なわけですから何らかの報告がオープンになされるべきです。再現性の危機が認識され、Systematic Reviewのような文献を系統的に検索・収集し、類似する内容の研究を一定の基準で選択・評価を行う研究が重要視されるようになってきていますが、そのような研究を行う上では、結果がネガティブであった場合も正直にその結果が出版される必要があります。実際には、当初の仮説を支持するポジティブデータばかりが出版されることが多々あり、偏った仮説が支持され続けることがあるからです。ポジティブ、ネガティブのいかんに関わらず結果が出版されることにより、より信頼性の高い結論が総体として得られることになります。このような意味でも、高IF至上主義は、健全な科学の進歩を阻害する要因になっていると言えるでしょう。 欠点5: 論文のハリボテ巨大化 高IF誌が論文のアクセプトの門を狭めるための弊害として、査読者が実験追加を過度に要求することにより、論文が大きくなりすぎてしまいがちであるになっています。メインのFigureに加え、論文本体に掲載しないsupplemental materialのFigureやTableが10〜20にものぼるようなケースは全く珍しくありません。論文の査読をきちんと行うためには、査読者が自分の専門に近い部分を批判的に評価することが必要なのですが、論文内の各アイテムの研究領域が様々な分野にまたがりすぎていて、少数の査読者では適切な評価ができない場合が多々あります。また、査読者は多忙なので、すべての補足的なマテリアルまでしっかりと評価する時間・労力を割くことが困難となり、査読者による評価が薄くなりがち、ということもあります。このため、高IFジャーナルに掲載される論文が、信頼性の弱いデータの寄せ集めとなり、肥大化したハリボテのような状態のものになってしまっていることが増加しているように思われます。 欠点6: 盛りすぎの広報 これは一見関連性が薄い用に見えますが、広報が過剰になりがちなこともJIF偏重の弊害の一つだと思っています。高IFジャーナルに掲載された論文は、あたかも信頼性や有用性が高いと思われがちなのですが、上述したように、再現性と有用性についての保証はないことがほとんどなわけです。所属機関やマスメディアからの広報は、論文発表直後に行われることが普通で、高IFジャーナルに掲載された論文が広報される場合が多いこともあり、再現性・有用性に関する認識と現実のギャップが、当該の論文に不相応で過剰な広報、盛りすぎの広報を生み出しがちになっていると思われます。 以上のような欠点を踏まえつつ、では、これからどうすればよいのか、について次、考えてみます。 3. JIF至上主義から脱却するために行うべきこと 上述したJIF至上主義の欠点を踏まえ、これらの欠点を克服できるような具体案を以下に提案させていただきます。 A) 出版後評価の拡大 JIF市場主義から脱却するために、研究コミュニティがまずは行うべきことは、論文と研究者の評価に再現性と有用性の観点を明確に導入すること、つまり、出版後評価を拡大することであると考えます。 そのための第一歩として、研究費、人事、賞などの申請書には、自分の論文の再現性、有用性の自己申告の欄を設けることが有益だと思われます。その欄には、自分(たち)のこれまでの論文の再現性、有用性(学術的、産業・社会や政策での応用の側面)を文献や記事などのエビデンスを示しながら記載することにします。それらが、他の論文でどれくらい再現されているか、ポジティブに評価されているか、どの程度、学術的に、あるいは社会実装に活用されているかなどです。研究計画で記載することの多い未来の有用性の可能性というのは、いくらでも法螺を吹くことができてしまい、あてになりませんし、大きすぎる法螺を吹いても心が傷まないような研究者を利することにもなります。論文発表後に、実際に再現されたか、有用であったかがエビデンスをもって示されるかどうかが重要です。 次に重要なのは、十分な時間をかけて評価者・審査員がJIFに頼らないまっとうなピア・レビュー、論文の科学的内容を定性的に精査した上での一次評価を行う環境を整備することです。まともな研究者であれば、できるだけそのように努力するはずですが、日本では、そういう研究者でもこれが事実上、物理的に不可能な状況となっており、これを改善する必要があります。詳細は省きますが、時間・労力が割けないというのが最大の問題ですので、これを解消するためには、分業の促進による時間の確保、研究費/賞などの種目数の削減(「大くくり化」)、再現性・有用性を重視し金額的に必要十分な額を措置する基盤的研究費の導入などが効果的と思われます。JIFに過度に頼ることなく、適切な評価が行われるようにするには、十分な定性的評価を行うことのできる時間と余裕を創出し、出版後の評価の比重を高めることが重要でしょう。 また、DORAでは、様々な論文レベルでの数量的指標(article level metrics)を利用可能にすることが推奨されています。最近では、JIFのようなジャーナルレベルの数量的指標だけでなく、個々の論文の被引用数、被引用数を分野調整した指標(ScopusのFWCIのようなもの)、Altmetricなどが極めて容易に入手できるようになっています。JIFはジャーナルの評価指標にすぎず、その値は、少数の多数回引用される論文によって大きく影響を受けていますので、論文ごとの指標が入手できる現在ではその意味が薄くなってきているはずです。これらの論文レベルでの数量的指標が重視されるようになると、高IF誌に出版するための費用対効果が相対的に弱くなり、状況は改善されることが期待されます。 ところで、一部、研究評価の数値化は必ずハッキングされるものなので、数値化自体がよくないとする意見もあるようです。しかし、論文レベルでの指標は基本的に出版後評価であり、JIFと比較すると本質的なところで優れているといえ、DORAでも活用が推奨されていることに注意しておく必要があります。また、論文の科学的内容を骨太のピアレビューにより定性的に評価して何をするかというと、最終的には数値化するわけです。そのピアレビューにより決定される研究費の額、ポジションとその報酬、賞の受賞の有無なども、ある種、数値化です。数値指標のほぼなかった昔の日本のアカデミアでは、基本的には指導教官の力、学閥、学会でのヒエラルキーと役割などを主な基盤として人事が行われていました。それらはそれらでメリットがないわけではないのですが、公平な競争を行うべきことがコンセンサスになっている現代では、その時代に戻ることは流石に不可能でしょう。メトリクスを全否定するということではなく、コミュニティとして、目的に応じた多様な数値指標や、よりハッキングされにくいような数値指標、不正なハッキングを検出する方法などを検討していくことにより、より公正・公平な指標を採用していくことが重要だと考えます。 B) 即時ゴールドOA義務化と高IF誌の出版コストの可視化 EUにおいて即時オープンアクセス化が義務付けの方針が”Plan S”で示されたことを皮切りに、米国でも同様な方針が示され、先日、日本でもようやく即時オープンアクセス化を義務付ける基本方針が示されました。これらを主なきっかけとし、Nature、Science、Cellやその姉妹誌などで、論文をOA化する場合のArticle Processing Charge(APC)が公表され、その高額さが話題になりました。100万円以上にもなるAPCは高額すぎる、というのが主な世論でしたが、私は個人的には、これは全然高くないどころかむしろ安い、と感じました。というのは、ジャーナルのサブスクリプションを通じてこれらの出版社が得る収益は莫大なもので、もしこれらの論文がすべてOA化された場合、この程度のAPCではおそらくそれに匹敵する収益は得られないはずだからです。即時OA義務化のメリットの一つで見逃されがちなのが、この高額なAPCにより、高IFジャーナルでの出版コストの可視化が進んだことです。大学や研究機関でのこれらのジャーナルの購読費用は莫大なものになっているのですが、研究者は自分のふところは傷まないので、これらのコストについては無関心な傾向が強いです。しかし、APCとなるとコストが自分ごととして意識化・可視化されるわけです。研究者にとって高IFジャーナルに掲載するメリットは、自分の論文がジャーナルの権威とともに広く広報されることによって、研究コミュニティや社会から認知され、引用が多くなされる傾向があることだと思われますが、これは見方をかえると、高IFジャーナルに掲載するための各種のコストは権威付けと広報のための負担であると考えることができます。ところが、オープンサイエンス時代に入りつつある現在、権威ある研究者がSNSで高い評価をするなどして話題になったり、OA誌の総説、論文などで高い評価がなされるなどすれば、権威も広報もそれで足りる場合が増えてきているのです。高IF誌に必ずしも掲載されていなくとも、プレプリントですら、権威付けや広報がしっかりなされる場合がある。一方、高IF誌であっても、その論文を事前にしっかりと評価するのは、エディターと査読者を含め、たかだか3〜5人程度にすぎません。SNSや後続の論文などによって何十人何百人という多くの研究者によって実際の再現性・有用性も含む評価がなされるわけですから、出版前評価と出版後評価の重みは後者が圧倒的に重要視されるべきものであることは明らかです。そういうことであれば、わざわざ100万円以上の高額なAPCを支払ってまで高IFジャーナルに掲載する必要がない、と考える研究者も増えてくるはずです。実際、私の研究室から出版された論文のいくつかは、標準的なOA誌に地味に出版された論文であっても、NatureやCellなどの高IF誌に掲載された論文よりも多数回引用されているものがかなりあります。高額なAPCのみならず、査読にかかる長い時間、理不尽に要求される追加実験、追加実験要求が助長する不正、リジェクト時の心理的ストレス、リジェクト後の他誌への投稿の手間、エディターや査読者候補への接待費用などは、高IF誌に掲載するための大きなコストです。研究コミュニティが負担しているこのコストの総和は莫大なものになって科学の進歩のマイナスとなっています。 現状、アクセプト時の原稿のリポジトリへの掲載で良しとするグリーンOAを許容する方針がEU、アメリカ、日本などでとられていますが、私は、ゴールドOAの義務化を進め、一刻も早く科学技術研究の原著論文の発表におけるサブスクリプションの息の根を止めるべきと考えています。これによって、多くの高IF誌の高コスト体質が浮き彫りにされ、費用対効果に見合わないことに多くの研究者が気づき、出版前評価から出版後評価へと評価の軸足のシフトがなされることを期待します。サブスクリプションの削減と廃止は、ペイウォールで可視化されにくく社会での研究活用の壁となり、科学情報へのアクセスの格差が生じている現状の改善という大きなメリットもあります。公的資金でなされた研究の成果は、サブスクリプションができない小さな大学・企業の所属の研究者からシティズンサイエンティストまで含めた一般市民まで広くアクセスできるべきです。日本の政府が、ジャーナルの購読料は原則、税金を原資とする公共の資金からは支払わないことにすることを明示し、この点での国際協調を先導するくらいのことを行ってもよいのではないでしょうか。 C) サウンドネス基準ジャーナルを増やす 科学的・技術的に健全でありさえすれば出版する「サウンドネス基準」を採用するジャーナルを増やすことも重要です。研究計画がしっかりしていて、適切にデータが取得され解析されているのであれば、「ネガティブデータの論文」、「仮説が支持されなかった場合の論文」、「再現性が確認されなかったという論文」なども出版する、ということによって、「欠点4」で指摘した出版バイアスを減らすことができます。現在、AIの著しい進化と普及が進んでいるわけですが、高IF誌偏重が出版バイアスを助長していることは間違いなく、AIが正しく学習していく上で高IF至上主義は害悪です。世の中のAIが適切に学習していくためにも、研究によって得られたデータが、研究者の人間的な思い込み・バイアスの影響をできるだけ受けず粛々と出版されていくことが欠かせないでしょう。この意味では、研究課題や研究方法が査読を通過すれば結果のいかんに関わらず論文の掲載を原則保証する ”Registered Report” の普及も進めたいところです。” Registered Report” をある種の研究費の審査と連動させるというアイデアもあります。システマティックなデータの取得を目的とするファクトリータイプの研究プロジェクト(例えば、ヒューマンゲノムプロジェクトというのはこれにあたります)というのも存在するわけですが、そのような性質の研究にはこのアイデアは有効なのではないでしょうか。高IF誌への論文掲載ではなく、信頼できる結果を得て報告する、という真っ当なことに研究者のモチベーションがシフトすることにプラスになると思います。 私は Neuropsychopharmacology Reportsという3つの学会が合同で運営する国際誌の編集長をしておりますが、このジャーナルでは、サウンドネス基準を採用することを最大の運営方針の一つとしています。また、このジャーナルでは被引用数やAltmetricなどのメトリクスを参考にした論文賞を多数出すこととし、出版後評価を行う文化の普及を目指しています。各種の評価において、論文ごとの被引用数その他の出版後評価を重視してほしい旨を、ジャーナルとして随時、学会員へお願いしていますが、投稿数は右肩上がりで増加中です。この種の試みを通じて、サウンドネス基準を採用するジャーナルを増やし、高IF誌偏重の文化を克服していくことが大切であると思われます。 D) 論文の価値評価を行う総説誌を立ち上げる 原著論文がサウンドネス基準のジャーナルに掲載されることが普通になった場合、では、「山のように出版される多数の論文の中から、今、読むべき論文をどう探せばよいのか?」という問題が生じます。現在、論文の価値の評価と広報の機能は、高IFジャーナルが担っている部分が大きい状況なわけですが、原著論文の健全性の評価と価値・インパクトの評価の機能は技術的に分けることができるし、そのための仕組みを作って峻別していくべきであると考えます。前者はサウンドネス基準のジャーナルの査読が主に担い、後者は総説(出版直後ではNews and Views的な速報的総説、再現性・有用性なども含めた中・長期的な価値は通常の総説)、SNSやAltmetric、機関からのプレスリリースとメディアによる報道などが主に担うようになることが望ましいでしょう。現在、高IF誌では専任で雇用されるエディターがいて、彼らは論文の健全性ではなく価値・インパクトの評価を主に行っています。この機能をしっかり分離し、そのような専任エディターをしている人材は、今後、出版後の論文やプレプリントなどから目ぼしいものを掘り起こして、News and Views的な速報的総説や再現性・有用性なども含めた中・長期的な価値評価を行う総説などを執筆するようにすればよいわけです。これらの専任エディターによる評価は、公的研究費によって担われているわけではありませんので、それらを掲載するジャーナルやサイトでは、オープン化を義務付ける必要はありません。新聞やネットメディアのサイトと同列の扱いでよいし、サブスクリプションもあって全然よいでしょう。そういうニーズは間違いなくありますので、現在、高IF誌のエディターをしている方々には、出版前の評価という顕著な弊害を有する仕事に従事することから、出版後評価の仕事、数多ある出版後の論文(プレプリントを含む)の中から注目すべき論文を掘り起こす仕事へと業務内容をシフトさせていっていただくことを期待します。 また、そのような流れを日本がリーダーシップをとって創っていくことも不可能ではないはずです。それぞれの学協会がサウンドネス基準のジャーナルを運営し、学会連合のような大きな組織が、News and [...]
続きを読む
2024年3月1日
Neuro2019で ランチョン大討論会 開催!
2019.06.10 トピックス

近年、遺伝子編集技術、光遺伝学、ブレインマッピング、単一細胞シークエンシング、ディープラーニングなど、さまざまな新しい技術が開発され、 神経科学研究が大きく進展しています。また個々の研究者を取り巻く研究環境も大きく変貌しつつあります。そこで様々な問題について、専門分野や年齢・研究環境を越えた建設的な議論を深めるために、日本神経科学学会では大会の最終日に不定期に「ランチョン大討論会」を行っています。 2018年第41回大会でのランチョン大討論会「脳科学は次の10~20年に何をどう目指すべきか?」での 討論の内容はこちら → テープ起こし版(PDF) オンラインでの議論はこちら → ガチ議論トピック 7月に新潟で開催されるNeuro2019でも以下の要領でランチョン大討論会を実施します。 「次の20年にどうやって脳科学にブレークスルーを生むか?」 日時:7月28日(日)12:00-14:00 ※お弁当付き 会場 : 朱鷺メッセ (新潟コンベンションセンター) 第1会場(国際会議室) 内容:脳科学分野を含む日本の国際競争力が低下していることが近年顕在化しています。前回の大会(神戸)では、「来る10-20年のタイムスパンで日本の脳科学を発展させていくには何を、どう目指せばよいのか」というテーマで、各分野の有志に持論を発表していただき討論を展開しました。今回の新潟大会では、ダイバーシティ企画・若手PI企画とタイアップし、「何を」のみでなく、「どうやって」に重点を置いて討論を行います。来る20年にブレークスルーを生みだしていくには、私たちはどうすれば良いのでしょうか?ご意見を募集します! 本ページ下部に書き込みいただくか、Twitter ハッシュタグ #大ラン討でツイートください。 参加:事前にWeb登録されていない方でも参加できますので、奮ってご参加ください。Web登録および大会会場先着200名様限定で特製「脳科学弁当」をご提供します。詳細は別途、大会HPに掲載される情報をご覧ください。 企画:宮川 剛、小清水 久嗣(藤田医科大学)、柚﨑 通介(慶應義塾大学) タイアップ・プレゼンその1:若手PI企画・五十嵐先生によるプレゼンです。 Neuro2019 ランチョン大討論会「日本の若手研究者の現状」 from scienceinjapan タイアップ・プレゼンその2:ダイバーシティ対応委員会・王丹先生のプレゼンです。 Neuro2019 ランチョン大討論会 ダイバーシティ対応委員会プレゼン資料 from scienceinjapan
続きを読む
2019年6月10日
脳科学は次の10~20年に何をどう目指すべきか?
2018.07.12 トピックス
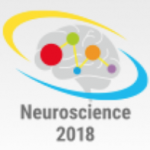
日本神経科学学会とガチ議論のタイアップによる企画を行います。 以下のような主旨で、日本神経科学学会の大会において討論会を行います。討論会では、2時間程度の時間をとっていますが、2時間で議論し尽くすことができるようなトピックではありません。そこで、ガチ議論とタイアップして、事前、事後にネット上でディスカッションを行うことができる場をこちらに設けます。 討論会でたたき台として用いられるプレゼン資料をこちら(OpenNeuro Repository)からダウンロードできるようにしました。 これらの資料をご覧いただいた上で、脳科学は次の10~20年に何をどう目指すべきか、についてご意見のあるかたは Disqus(本ページ下部)に書き込みをお願いいたします。 日本神経科学学会の学会員はもちろん、脳科学研究に関心のある研究者のご意見も歓迎いたします。 脳科学は次の10~20年に何をどう目指すべきか? 日本神経科学学会 ランチョン大討論会 近年、遺伝子編集技術、光遺伝学、ブレインマッピング、単一細胞シークエンシング、ディープラーニングなど、さまざまな新しい技術が開発され、神経科学研究が大きく進展しています。このように研究が高度化・大型化される一方で、個々の研究者が何をどのように研究するのかという問題が議論されるようになってきました。また基礎科学の成果を臨床医学や社会科学、あるいは企業と連携して社会に役立てていくためにはどのようにすれば良いのでしょうか? 本ランチョン大討論会では、来る10-20年のタイムスパンで日本の脳科学を発展させていくには何を、どう目指せばよいのかについて、今大会のシンポジウムオーガナイザーから7名の有志に持論を発表してていただき、その後ホンネでの議論を行います。 ・日時:7月29日(日)12:00-14:00 ※大会参加手続きの上、企画への参加登録が必要です ・会場:第3会場(神戸国際会議場 レセプションホール) ・主催:日本神経科学学会 研究体制・他学会連携委員会 ・後援:日本脳科学関連学会連合・JST 研究開発戦略センター(CRDS) ・企画:宮川 剛, 小清水 久嗣(藤田保健衛生大学); 柚崎 通介(慶應義塾大学) *匿名でも書き込み可能ですが、書き込みに際しては本サイトの利用規約をご一読ください。不適切と判断された書き込みは不掲載とされる場合があります。 *本サイトに掲載された情報の正確性について日本神経科学学会は保証いたしません。また意見掲載は日本神経科学学会の支持を示すものではありません。 *日本神経科学学会は、本サイトの利用により直接的、間接的にもたらされた損害についての法的責任を負いません。
続きを読む
2018年7月12日
政党アンケートの案作成中 ご意見急募!
2017.09.29 トピックス

衆議院が解散され、来たる10月22日に総選挙が行われます。 サイエンス・サポート・アソシエーション(榎木英介代表)が毎年されている各政党への科学技術に関する公開アンケートに、サイエンス・トークスとガチ議論が協力させていただくことになりました。 現在、ガチ議論スタッフでアンケート案を検討しておりますが、アンケートに入れたほうが良い質問・文言のご提案や、アンケートに関するご意見を急募いたします。 この記事のコメント欄に書き込んでいただくのでもよいですし、ツイッターでコメントしていただければできるだけ捕捉して反映させていただきます。 昨年の参議院選での政党アンケートについては、以下をご覧ください。 https://news.yahoo.co.jp/byline/enokieisuke/20160707-00059701/ http://www.sciencetalks.org/senkyo_manifesto/ 基本的には昨年のアンケート項目をベースにして、皆さまのご意見を反映させつつ、それらを改訂・追加するような形にするのが良いのでは、と考えています(手抜きですみません;ガチ議論スタッフも科研費申請などで多忙にしてます…)。 今年の3月に、ネイチャーで日本の科学技術がこの10年で大きく失速していることが指摘され、 タイムズ・ハイヤー・エデュケーションの世界大学ランキングでも日本の大学は軒並みランクを落としていることも明らかになっています。 一つや二つの大学が「失速」しているわけでなく、全体的に失速しているわけですから、これは日本全体の科学技術政策の問題に違いありません。つまり、これは政治の問題なのです。 政治のトップダウン的パワーがいかに強力かは、河野太郎さんのご活躍で、われわれ研究者にもよく理解できたのではないでしょうか。政治家に国民の意見を聞いてもらえる最も良い機会が選挙です。 時間があまりありませんが、研究者コミュニティの考えを国会議員の方々に伝えることができるようなアンケートをぜひ作りましょう。 ガチ議論スタッフ
続きを読む
2017年9月29日
研究公正を推進するためには何が必要か?
2017.07.25 トピックス

研究コミュニティでは近年、研究公正の推進をいかにして進めるかという議論が活発になっています。文部科学省には研究公正推進室が設置され、JST、AMED、日本学術振興会といった関連機関が協働して研究公正ポータルというwebサイトを運営するようになりました[1]。それに伴い、邪悪な研究者個人による不正行為というイメージは、研究活動に必然的に伴う「ミスコンダクト」という認識へと変化し、研究不正には包括的な対策が必要であるという考え方が広く受け入れられるようになってきました。 米国科学アカデミーは最近、Fostering Integrity in Researchという報告書を公開し、近年の研究環境の変化を反映した研究公正への取り組みを提言しています[2]。研究者のみなさまには是非目を通していただきたい内容ですが、そこで強調されていることのひとつは、研究機関が研究公正の推進において中心的な役割を果たすべきであるということです。「連邦規則を遵守すべき上限と考えるのではなく、これを最低限の義務として認識し、率先して高い規範意識をもつ必要がある」ことが述べられています。報告書には独立した非営利の研究公正諮問機関を設けるべきという提言も含まれています。我が国でも2005年に日本学術会議からアカデミックコートの設置が提言されましたが、実現していません[3]。 こうした変化をふまえて我が国のガイドライン等を調べると、研究公正の推進に対して研究機関に十分なインセンティブが与えられていないことに気がつきます。 ・第三者調査委員会の設置、審議、報告書の取りまとめは、研究機関にとって大きな負担ですが、予算として平時から計上できるものではありません。 ・研究不正の認定は、外部評価におけるマイナス材料となります。 ・研究不正の認定は、間接経費の削減というペナルティにつながる可能性があります。 ・研究不正の認定に伴う不正研究者の懲戒処分には訴訟リスクが伴います。不正の程度と処分との関係は過去の事例はばらばらであり、参照できる基準はありません。 ・大型研究費を獲得している研究者の不正では、研究資金配分機関から研究費の返還請求は大きなリスクとなります。 一方で、 ・研究機関による研究不正疑義の告発の無視、あるいは隠蔽に対するペナルティはありません。 ・調査の結果、最終的に疑義がシロ認定された場合、調査報告書を開示する義務はありません[4]。 ・文部科学省をはじめとする調査報告書を受理する側は、その内容の妥当性を評価することはありません。 研究機関は、研究公正を推進しようとしても不正を認定すれば不利益を被るという、利益相反の状況に置かれています。研究者ではない理事からは、わざわざコストをかけて研究公正を推進する意義を問われることもあるかもしれません。研究機関の利益を優先する場合には、以下のような対応が最適解でしょう。 ・疑義の告発には出来る限り対応しない。匿名やweb上のものは基本的に無視する。 ・調査委員会を設置する場合も、指摘のあった箇所に限定して調査を実施し、余分な調査はしない。可能な限りシロ判定になるよう資料を解釈する。 ・完全なシロ判定に到達した場合は、調査報告書の公開請求には応じない。 こうした対応は、いずれも研究公正の推進を妨げるものと言えるでしょう。一方で、調査委員会が、指摘のない論文まで調査し、その訂正や撤回を求めている例もたくさんありますが、これは、当該研究機関が高い規範意識を発露した結果と考えることができます。しかしながら、機関によって対応がまちまちという状況は改善するべきです。 文部科学省のガイドラインは今後も研究環境の変化に応じて見直しがあることが明言されています。そこで、以下の提案を考えました。 ・研究不正の疑義に一定の合理性がある場合、研究機関が研究不正を一切認定しないという結論であっても、調査報告書は全て公開し、不正を認定しない根拠を示す。あるいは、告発者が受け取る調査報告書を公開することを妨げない。(本調査に入る事例では指摘の合理性は認められているはずです。一方で予備調査で却下する場合もその理由は開示されるべきです) ・告発者、あるいは被告発者から調査報告書の結論に異議がとなえられた場合、文部科学省は第三者的な諮問機関に調査報告書の評価を依頼する。この評価にかかる議事は全て記録として保全し、一定期間後にこれを公開する。(第三者性というのは、手続きの透明性を確保することでしか保証することはできないと思います。現状では、関連学会、あるいはAPRINのような組織が諮問機関の候補となるでしょう。) ・アカデミックコートに相当する組織の将来的な設立を奨励する。 告発を無視したり隠蔽していることが発覚した研究機関は低く評価されるべきですが、こうした事例に対する罰則も設けた方が良いでしょう。一方で丁寧な調査報告を実施できた研究機関は高く評価し、調査費用に相当する予算配分を追加することも考えて良いと思います。大型の研究不正では数十億の研究費が雲散霧消することを考えれば、調査費用はそれほど大きな額とはいえないです。 研究不正の容認や、一貫性のない対応は、研究者のモラルを低下させると同時に、誠実な若い人材を研究コミュニティから遠ざけるものです。また、研究機関が専門家の指摘を軽視するという姿勢は、長い目で見れば、その研究機関自身の衰退につながるでしょう。活発な議論をベースに望ましい方向性を模索できればと思います。 田中 智之 1. 研究公正ポータル(科学技術振興機構) 2. McNutt, M., Nerem, R. M. Research integrity revisited. Science 356, 115, 2017 3. 科学におけるミスコンダクトの現状と対策ー科学者コミュニティの自律に向けて(日本学術会議、学術と社会常置委員会、平成17年7月))[PDF] 4. 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(文部科学省、平成26年8月)[PDF] (抜粋) 4−2 告発に対する調査体制・方法 (6)調査結果の公表 ①調査機関は、特定不正行為が行われたとの認定があった場合は、速やかに 調査結果を公表する。 ②調査機関は、特定不正行為が行われなかったとの認定があった場合は、原則として調査結果を公表しない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表する。悪意に基づく告発の認定があったときは、調査結果を公表する。 ③上記①、②の公表する調査結果の内容(項目等)は、調査機関の定めるところによる。 上記の意見は、筆者個人のものであり、その所属とは無関係です。また、ガチ議論スタッフの意見を代表するものでもありません。 アンケート 本記事に関して皆さまのお考えをお聞かせください。
続きを読む
2017年7月25日